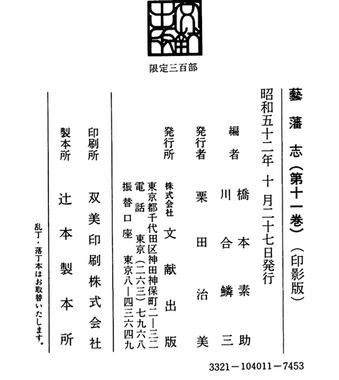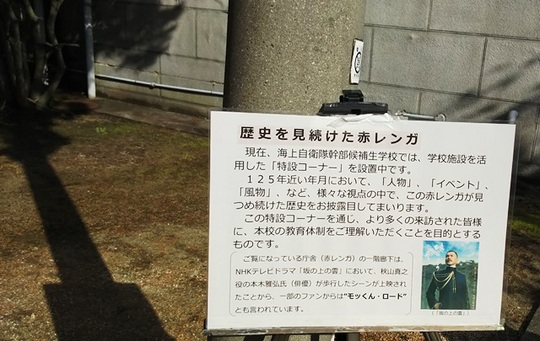小説のなかで、下瀬うた「文久3年~大正15年」という人物を登場させる必要があった。彼女は広島市・鉄砲町で生まれ育っている。その鉄砲町には、長い歴史がある。
*
ポルトガル人が天文12年に、種子島に鉄砲を伝えた。紀州の「雑賀衆(さいかしゅう)」によって、数千挺(ちょう)もの国産化に成功した。江戸時代初期、浅野家が紀州から広島藩に入封してきた。その折、紀州の鉄砲職人「雑賀衆」を広島まで連れてきて、城下に鉄砲町という一角を与えた。
 ここに端を発して鉄砲町には兵器工場、大砲工場、火薬工場が多かった。武具奉行など特別な武士階級と鉄砲職人しか、当時は出入りができない特殊な町だった。幕末には、広島藩は独自に最新銃を国産でライフル銃が製造できる唯一の藩だった。
ここに端を発して鉄砲町には兵器工場、大砲工場、火薬工場が多かった。武具奉行など特別な武士階級と鉄砲職人しか、当時は出入りができない特殊な町だった。幕末には、広島藩は独自に最新銃を国産でライフル銃が製造できる唯一の藩だった。
他藩は、グラバーなどから海外の銃を買うしかなかった。
広島藩・鉄砲町の場合は、手先の器用な鉄砲職人らが、武具奉行の高間多須衞(たすえ)が長崎から手に入れてきた西洋のライフル銃・一挺を見本として、改良に、改良を重ねて進化させていく。品質の高い銃の量産に成功する。
広島藩の神機隊1200人が鍛錬・演習用としても使う。さらには自費で戊辰戦争に参戦したおり、その高性能なライフル銃をもって、上野戦争、相馬・仙台藩と戦っている。(写真は高間省三の銃・広島護国神社蔵)。むろん、大砲も広島藩の製造だ。
火薬工場としては志和(現・東広島市)に複数もっていた。
*
彼女(うた)が、下瀬雅允(まさちか)の実妹だとわかった。この兄と妹は、広島・鉄砲町という兵器関連の機密の街なかで生まれ育っている。
雅允は幼いころから、子どもが花火に興味を持つように、火薬の化学反応に関心を示していたようだ。かれは広島英学校(旧広島一中、現・国泰寺高校)、工科大学応用化学科(現・東京大学)を卒業している。やがて、化学者の道に進み、フランスにも留学し、独自開発で明治26年には、「下瀬火薬」の開発に成功した。
「日露戦争(1904年)は、下瀬火薬で勝利した」
そのことばが私の脳裏に過去から根づいていた。そこで、このたび江田島の旧海軍兵学校を訪ねてみた。
現在は海上自衛隊第一術科学校で、旧帝国海軍関係の資料が収まった「教育参考館」がある。そこの2階には、旧帝国海軍の貴重な資料が残されている。

太平洋戦争の末期、呉軍港はたびたび米軍の空襲をうけた。戦艦・大和を造った海軍工廠(こうしょう)や海軍基地は壊滅した。
ただ、呉の真向いにある江田島の海軍兵学校は、米軍の攻撃対象から外されていた。なぜか。世界の三大海軍士官養成学校のひとつであり、ヨーロッパ・ルネッサンス建築の価値ある建物を遺すためであった。一発の機銃掃射すらなかった。
昭和20年8月15日に、日本が無条件降伏を受け入れた。海軍兵学校の関係者は進駐軍がやってくるまえに、諸々の軍艦関係の機器や資料の大半を焼いた。
多少は宮島・厳島神社、大三島(愛媛県・今治市)の大三島 大山祇(ずみ)神社に奉納品(カムフラージュ)として残したという。
それらが貴重なものが一部、「教育参考館」展示されている。
*
同館の学芸員に下瀬火薬について、「日露戦争は下瀬火薬で勝利したのは事実ですか」と私はいきなり質問した。
「事実ですよ。下瀬雅允の資料ならば、この教育参考館の2階に展示しています」
と言われて2階にあがり、あれこれ見ていた。
そのうち、学芸員の方が来て、わかりましたか、と聞いて、場所はよくわかりません、他のものを見ていましたし、というと、下瀬雅允の展示まで案内してくれた。
「かれは化学者ですか、軍人ですか」
「そうですね、中間ですね。軍の依頼で火薬の研究をしていた。あえて言えば、化学者かな」
学芸員はそんなふうに説明していた。
「参謀の秋山真之が、日露戦争に勝利した最大の貢献者だと一般にいわれていますけれど? バルチック艦隊相手にT字型戦法で」
「その認識は違いますよ。はっきり言えば、勝因はなんといっても、『下瀬火薬』と伊集院大将が発明した『伊集院信管』です。それがバルチック艦隊を撃破したのです」
と明瞭な歯切れの良さで、さらにこういった。
「もし、下瀬火薬と伊集院信管がなければ、どんな戦法を取ろうが、ロシア艦隊にはかなわなかったです。海戦はT字型だろうが、L字型だろうが、あまり関係ないです。双方が艦砲射撃で撃ちあう。戦艦に当たった大砲の威力が問題なのです」
弾が炸裂して爆発力がどのていどあるか。それが重要です、となおも強調していた。

秋山参謀は勝利にさして関係ないとなると、歴史小説家・司馬遼太郎は、売れる小説の創作から、秋山参謀を英雄としてもちあげたのか、と思った。登場人物を英雄にすれば、ワクワク、ドキドキ感から、読み手を魅了する。
小説はフィクションだから、決して悪いことではない。ただ、世のなかの人は司馬遼太郎の小説は歴史的事実に基づくものだ、歴史そのものだと思い込んでいる。ネット時代と違って、司馬が書くとなると、その人物の関連図書が神田古本屋街から消えた、という伝説になっている。だから、すべて事実だろう、と思い込んでしまうのだ。
*
「下瀬火薬は石炭酸を硝化してつくるピクリン酸です。砲弾は当たれば、先端が折れて、信管で発火して炸裂するのです。下瀬火薬は3000度の高温になる」
それは鉄鋼の軍艦に塗られた塗料を溶かし、なおかつ火の海にしてしまう。つまり、戦艦が丸焼けになってしまい、沈没していく。
船体は二重、あるいは何層にも仕切られているので、砲弾の爆発力が弱い、火薬に威力がないと、砲弾が当たっても多少の破壊があっても、船内に浸水が生じても、沈没までいかない。
下瀬火薬は爆発すれば、軍艦を丸焼けにしてしまう。
バルチック艦隊の戦艦が、下瀬火薬で、次々に炎上し、沈没し、海の藻屑となる。一方で日本の小艇がわずかに犠牲になった程度である。まさに、火薬の威力の差だった。
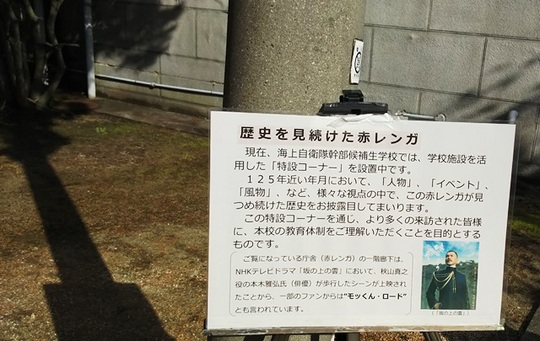
秋山参謀はバルチック艦隊が陸奥湾からウラジオストックにむかう、と具申した。上官で参謀長の加藤友三郎が、「バルチック艦隊の随伴の石炭運搬船が、切り離されて、上海に入港したからには、主力部隊は航行距離の長くなる太平洋ルートを通らない証しである。敵はかならずや、日本海にやって来る」と主張した。
司令官の東郷平八郎は、加藤友三郎参謀長への信頼・評価が高かった。それで日本海で待ち受けた。もしも参謀・秋山真之の意見を取り入れていたならば、バルチック艦隊はすり抜けてウラジオストックに入港していたはずだ。
となると、長期戦となり、戦争資金の薄い日本国はしだいに劣勢に立たされたことは間違いない。その面で、東郷元帥が秋山真之の具申を退けた、その見識は高く評価されるものだ。
かたや、歴史作家・司馬遼太郎は、秋山真之をもちあげた、誇大英雄づくりで本を売る、という商売気の強い作家だったのか、と思わざるを得ない。
*
「竜馬が行く」で、坂本龍馬を英雄として、世のなかに司馬史観を生みだした。近年は龍馬のメッキがボロボロ剥がれてきている。
「船中八策による大政奉還を成した」船中八策などは、大正時代の作り話であって、それが司馬史観で大きくなったものだ。
「いろは丸事件」でも潜水調査がすすんだ現在、海底の船内からは金塊や最新銃など一丁も積んでいなかったと判明した。長崎奉行所で、龍馬は嘘八百をなべて、8万3000両を紀州徳川家から詐取した人物である。
結局、龍馬って、なにした人なの、と疑問が出てくる。

欧州ではクリミア戦争(1853年)が起きている。このときから戦争が鉄砲から大砲の時代になっていた。ちょうど、ペリー提督が浦賀に来て、大砲を撃って威嚇した年である。
第二次長州戦争(1866年)で、坂本龍馬が最新銃を薩長の間で橋渡しをした。小説上では多大な貢献度としているが、冷静に、客観的にみれば、幕府軍が朝敵である防長2州(現・山口県)に攻めてきたので、毛利家は降りかかった火の粉を払っただけである。
その先も長州・毛利家は朝敵のままである。外交的にはなにも勝っていない。となりの広島藩内にも、京都にも、江戸すらも行けていない。
かたや、負けたとレッテルを押された徳川政権は、なおも北は松前藩から南は薩摩藩まで、日本列島支配下に置いているのだ。
徳川家はなにひとつ奪われていない。長州は天皇に弓を引いた藩として、だれも相手にしない。幕末の四候会議(慶応3年・1867年)においても、長州問題は放っておけ、と無視されつづけたのだ。
つまり、司馬史観がいうほど、德川は敗けていないのだ。大砲の時代に、龍馬が斡旋した小銃など、さして威力とならない。「西洋の最新銃」ということばは、とても耳ざわりが良いが、せいぜい自藩を守る程度だったのだ。
その論証として、第二次長州戦争からちょうど2年後、上野戦争が起きた。彰義隊をあいてに、大村益次郎がクリミア戦争と同様に、アームストロング砲を撃ちこみ、半日で決着をつけている。もはや、大砲の時代なのだ。
つづく戊辰戦争でも、大砲の撃ちあい、砲台への襲撃戦争だった。新政府(西側)軍の大砲の威力が奥州32藩よりも勝っていたのだ。函館戦争でも艦砲射撃が威力を発揮したのだ。
こうして見てくると、司馬遼太郎作家は「大砲・火薬の認識が薄い」作家だったのか、と江田島であらためて思った。
広島藩が大政奉還をおしすすめた。幕の口火を切ったのが広島藩だったと明かす「芸藩志」が、明治政府に封印されたままで、近年まで世に知られていなかった。昭和時代に活躍した司馬遼太郎は当時、広島藩・鉄砲町を知る、見る機会がなかった。研究資料もなかった。その面を差し引いてあげないと、気の毒かもしれない。
いずれにせよ、幕末の広島藩、および維新後の広島がクローズアップされはじめてきた今、近現代史がおおきくくつがえるだろう。商業主義に乗った司馬史観は、娯楽歴史小説だ、という狭い範囲内に押し込められていくだろう。

下瀬うたは、タイトル『俺にも、こんな青春があったのだ』のなかで、主人公の母親として登場してくる。背景は日英同盟である。
この軍事同盟が、その後の日本にどんな影響を与えていったか。その一端にからむ内容である。日英同盟はワシントン軍縮条約(1922年、加藤友三郎・全権大使)で解消する。ことばは厳しいが、欧米からみれば、日本がこの日英同盟を悪用したから、破棄させられたのである。
了