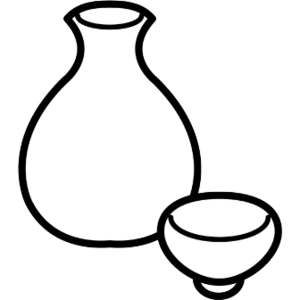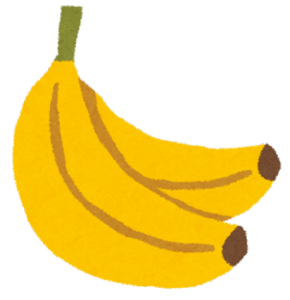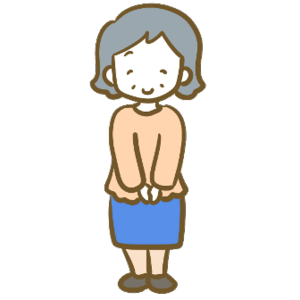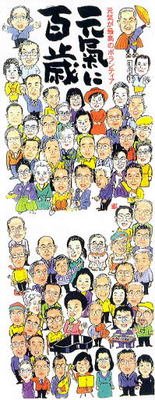ビール讃歌 林 荘八郎
「カンパーイ!」
初夏に飲む生ビールはうまい。ビアホールでのひとときは楽しい。
五〇〇〇年ほど前、エジプトで誕生して以来、利尿作用がある、材料のホップには男性ホルモンが豊富だといって、ビールは身体に良い酒とされ、人気を続けてきた。
大戦後、日本経済が復興した昭和四十年ころからは、ビール消費の伸びは酒類の中では最も高かった。飲食店、中でもビールを大量に消費するキャバレーは賑わい、中元贈答も盛んだった。食事習慣も洋風化し、その味は家庭にも浸透していった。

我が国はビールの作り方をドイツから学び、モデルにした。そのため原材料は大麦、ホップ、水だけに限ると定義された。すなわち、ビールであるためには醸造発酵用の原料は大麦100%でなければならない。その酒税法がずっと続いていた。
日本のビール酒税は他国に比べ、とても高い。業界は価格を下げて消費を増やしたいと考え、課せられている酒税の引き下げを、国税庁へ求め続けた。しかし、国の税収の中で所得税、法人税に次ぐ大きな財源だ。
ビール酒税はその中でも筆頭なので抵抗は強く、引き下げてくれない。
平成時代に入るとその消費が減り始めた。ビールメーカーの格闘が始まった。あるメーカーは、発泡酒を発売した(平成六年)。
原料の大麦比率を99%にして米や澱粉を混ぜた。酒税の安い製品だ。ビールと呼ばれなくても、味はほとんど同じである上に、値段が安い。消費者に受け入れられて発泡酒は大流行した。そのため、ビールの消費は減り発泡酒が増加した。
すると国税庁は酒税法を改定し、大麦の使用比率が67%以上はビールとし、発砲酒の酒税を引き上げた。ビール酒税は七十七円(一缶当たり)、発泡酒は四十七円と定めた。メーカーは発泡酒の大麦比率を66%にして対抗した。
今度は別のメーカーが、大麦を全く使用せず、豆や米やトウモロコシなどを原料にする酒を発売した(平成十五年)。
ビールの風味を持ち、それも消費者に歓迎され、第三のビールと呼ばれた。今では大麦比率が25%未満の酒として立派に君臨している。酒税は二十八円のリキュールに分類されている。
ビールメーカーと国税庁の知恵比べはまだまだ続くのだろう。
残念ながら、ビール・発泡酒・第三のビールの消費量の合計は、十一年連続で減少し続け、ビールメーカーは頭を抱えている。その中で、発泡酒と第三のビールの割合は増え続け、国税庁にとって不都合な結果になっている。
わたしも第三のビールの愛飲者だ。しかし昔ながらの本当のビールは、やはりうまい。その中でも生ビールは美味しい。
いまは、居酒屋でも、回転寿司でも、ラーメン屋でも飲める時代になったが、ビアホールで飲む生ビールは最高だ。天井が高く室内が広いビアホールは明るくて楽しい。プロが、良く洗浄された大きな器に注いだビールは格別にうまい。のどの渇きを潤し、ソーセージが空腹を満たす。何ものにも代えがたい一瞬だ。
仕事に就いて初めてのボーナスをもらった最初の土曜日。半ドンの仕事を終え、ボーナスを懐にビアホールへ向かった。
ビールには、楽しい仲間が欲しい。音楽があると、なお良い。清酒はしんみりと一人で飲むのがわたしは好きだが、生ビールを飲むときは違う。
若かったわたしは、興に乗って中ジョッキを十杯飲んだ。翌日の日曜日は独身寮で二日酔いに苦しみ、月曜日の出勤もつらかった思い出がある。いまでも、中ジョッキ十杯がわたしの最高記録だ。
いまでは世界中から、いろいろなタイプのビールが我が国へやってくる。
ドイツ産に限らず、ベルギー産もデンマーク産もおいしい。外国へ出かけて、その地のビールを飲むと、最初の口当たりは自分の好みとは違っても、暫くその地で過ごすと、その味に慣れ美味しいと感じる。
その伝でいうと、日本人には日本の製品が一番口に合っているということになる。狭い日本で数少ない種類のビールを飲みながら、能書きを垂れていたころがなつかしい。
日本はビール大国ではない。消費量では中国、アメリカ、ブラジルが多く、日本は七番目だ。一人当たりの消費量ではチェコ(年間一八三L)、オーストリア、ドイツが多く、日本は五十番目(四十L)だ。
平成六年に酒税法の改正があり、ビール製造の免許が緩和された。それまでは国税庁は販売能力が二〇〇〇KL/年以上見込まれる企業にしか製造免許を下ろさなかった。酒税の財源確保のためだ。それを、六〇KL/年でも製造することを認め、その結果、中小企業にも道が開かれた。
ビールづくりに各地の日本酒メーカーが参入し、いまでは三〇〇社に達する。はじめは彼らが製造するビールは「地ビール」と呼ばれた。それが、いまでは「クラフトビール」と呼ばれる、新しいジャンルのビールとして育ち始めている。清酒の分野で地酒が人気を博するようになったのとよく似ている。
うまけりゃいいのだ。わたしも昔ながらのビールの定義に凝り固まっていたようだ。ますますビール談義は楽しくなる。「カンパーイ!」
イラスト:Googleイラスト・フリーより