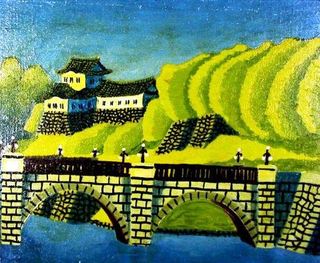エッセイ 「散髪」 = 青山貴文
毎月1回は、散髪をする。
面倒くさいが、散髪するとさっぱりする。
私の髪の毛は、通常の人より伸びるのが早いような気がする。
新陳代謝しないと、艶のある清潔な頭髪を保てないから致し方ないが、手間がかかる。
十数年前、ファミリーサロン・アクアという理髪店が自宅から歩いて15分位のところに開店した。
散髪代が格安で、理髪が短時間でかつ店内が清潔だ。
理髪台が6台あり、数人待ちでも、数分待てば自分の順番が来る。
その理髪店は、年中無休で、朝8時半から、夜7時までやっている。
全国に支店を持つチェーン店で、店員たちの技術の向上や、生活面の指導など行き届いている。
そのためか、店員たちは礼儀正しく、とても気持ちが良い。

この店のモットーなのか、理髪師をいろいろの支店に派遣し、経験を積ませているらしい。
有給休暇を確実に取らせるために、常に新たな理髪師が応援にやってくる。よってしばしば、見知らぬ理髪師に自分の頭髪を任せ ることになる。
新顔が、にこやかに私に尋ねる。
「髪の毛は、どういたしますか?」
「左分けで、耳が出るくらいで、あとは適当にやって ください」
「じゃあ、これくらいカットして、もみあげはこれくらいに……」
と、鏡の中の私に応える。
初対面だが、阿吽(あうん)の呼吸で、チョキチョキやり始める。
途中で、「眉毛の下は剃りますか?」「整髪剤は何にしますか?」などと聞いてくる。
「剃ってください」とか、「リキッドでお願いします」
とか、必要最小限の言葉で答える。
昔の話になるが、私は幼少のころから高卒後二浪するまで、坊主頭であった。
亡き父母がバリカンでカットしてくれていた。
「貴文のおつむは、右に片寄っているね」とよく言われた。
大学生になって、立川市富士見町の自宅近くに、バラック建ての床屋があった。オールバックの背の高い30才くらいの独身の お兄さんが店主だった。
彼の母親らしいおばさんが洗髪などしてくれた。
私は、丸坊主から、頭髪を伸ばし初めて、髪の格好を気にする年頃であった。
その兄さんが、「おたくの髪の毛は、癖があって、カットが難しいね」と言っては、首を傾げる。
何度も櫛を通してカットしていた。
自分は、なぜか肩身が狭かった。
アクア店では、洗髪の時は、清潔な洗面台が前面に備えてあり、前屈みすれば、豊富なお湯のシャワーと石けんで2回要領よく洗ってくれる。一人30分弱で終わる。
全店員の「ありがとうございました!」という声掛けで、2、090円を支払って出てくる。
すごく合理的で無駄がなく、さっぱりする。
今から40年前、私が40才のころ、シカゴ空港の理髪店で怖い体験をした。
当時住んでいたミシガン州アルマ町近郊のランシング空港へのフライトまでに、待ち時間があった。
シカゴ空港の散髪店で、時間をつぶそうと、書類が一杯入った手提げ鞄を抱かえ気軽に入った。
二人の大男の黒人理髪店員が、店内で暇そうにしていた。
若造の私をみて、にやにやしている。いやな感じであった。
米国滞在も2年目に入り、こちらの生活にも慣れ、自信に満ちてきたころだ。
空手などからっきしできないが、さも出来そうな日本男子然として、不敵な面構えをしていたと思う。
月曜から4日間、移動時間も含め5社の出張も無事に終わり、明日は金曜日で、1日工場へ出勤すれば、休みだという気楽さもあった。
かたや、空港の理髪店の椅子のカバーは、黄ばんで油臭かった。
私も無精髭で、革靴も埃まみれで、疲労した面持ちで椅子に座り、ひげを剃るよう頼んだ。
大きな目玉をした黒人店員が、横たわった私の顔を横柄に覗き込む。
こちらは無邪気にニコリとした。彼は私の品定めをしている。
剃刀をふりかざして、もう一人の黒人の店員に向って、大声でわめいている。
カミソリを上段に振り上げて、私を揶揄する。お客に対して、失礼な奴だ。日本ではこんな無礼は許されない。
何をしゃべっているか良く解らないが、こちらは、ムッとする意外に、意思表示する方法がない。
彼はカミソリで、私のあごひげを、無造作に剃り落としては、へらへらしている。
あのころ、私は何かあれば日の丸を背負って、敢然と対峙するという気迫を持っていた。相手の目玉を目の隅で睨みつけて、泰然としていた。
相手も、下手をするとまずいと、私をチラチラ睨んで逡巡しているようだった。
ひげを全て剃って貰ったが、さっぱりするどころか、冷や汗をかいていた。
それ以後、空港での散髪は一切やめたものだ。