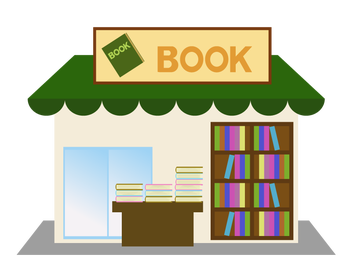サソリの話 桑田 冨三子
先だって、有栖川公園桜見物を口実に家にやってきた友人が、偶然こんなことを口にした。
「『イソップ』にサソリの話があったと思ってね、調べてみたンだけどないンだよネ」
彼は物知りでいつも私に種々雑多な知識を提供してくれる人だ。
「サソリ...サソリってどんな話?」
「川を渡りたいサソリが居た。泳げないのでカエルに『背中に乗せて川を渡っておくれ』と頼む。カエルはサソリが刺すから「嫌」と断ったが、サソリは『川の中で刺したりしないよ。そんなことしたら二人とも溺れて死んでしまう。』カエルは(なるほど、そうだ)と思い、サソリを背中にのせて川を渡り始めた。しかし、川の中ほどに来るとサソリは、カエルを刺してしまう。死にかけたカエルが『刺さないって言ったじゃないか。何故だ?』と言うと、サソリは『だってぼく、さそりなンだもン』とキッパリ言った、というのだ。」
この動物を使った寓話が、最近ビジネス界でもてはやされているらしい。

その心は、ちょっとすぐには理解しにくいが、
「悪質な人々は、自分の利益にならない場合でも、他人を傷つけることに抵抗は出来ない」
という。
「へえ、イソップにそんな話、あったかなア。でもイソップ寓話は旧い国々のいろんな寓話が集まっていて興味津々。私も探してみるね。」
そう言った私には、あるひらめきのヒントがあった。幼いころ、私は悪魔が出て来る絵本がたいそう気に入って何冊か大事に持っていた。黒いトンガリ帽子の悪魔は手の爪を長くのばし、魅惑的にふるまい、脚は長くてエレガント、何しろ格好良かった。いつも優しそうな猫なで声で「悪いことをしなさい」とささやく。私はそんな絵本が大好きだった。昔のことである。
(ひょっとすると、このサソリはトルストイの童話だったのかもしれない。)
そう思った私はいろいろな本棚を歩き廻り、調べてみた。しかし、残念、トルストイの本には、どこにもそんな話はなかった。その代わり、私はこの寓話が最初に出たのが1933年、ドイツ人地区に棲むロシア人・レフ・ニトブルクが書いた小説、ということをウイキぺデイアでみつけた。
(やっぱりロシア人だった。)
私は納得がいった。そう、この話、なぜかは知らねどなんとなくロシア人に違いないと私は思っていたようだ。
この寓話を私なりに解釈してみると、生まれつき他人を傷つけたい悪い性格の人間は、たとえそれが彼の利益にならない時でさえ、傷つけてしまう。本来からその人に自然に備わっている性質には、逆らえないものだ。言ってみれば、人の性(さが)とでもいうのだろうか。
「だってぼくサソリなんだもン」というサソリは約束しようがしなかろうが、 「なんて言ったってサソリはサソリ。サソリには自然に備わっている衝動には抵抗できないようになっているのです。それはぼくの本来の性質だからです。」 この寓話では、カエルもサソリも死んでしまう。
余談ですが、
(人間てそういうもンだよ。だってぼくサソリなンだもン)プーチンはそんなこと、つぶやいているのかもしれない。