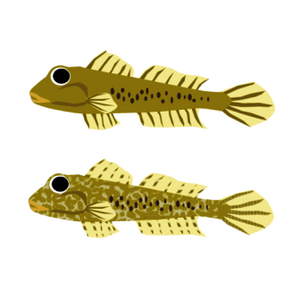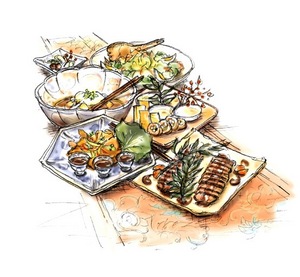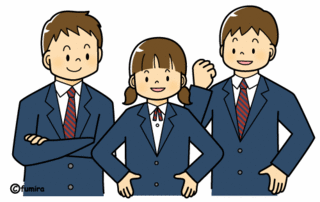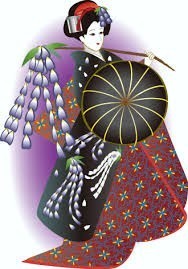遺された足あと = 石川 通敬
古希を過ぎたころから、人生の締めくくりをどうつけるかと考えつつ、何もせず今日に至っている。
そんな時ふと「足あとを遺す」という言葉が頭をよぎった。
なぜ、この言葉を思いだしたのか、原因を考えてみると、次の二つの出来事が思い当たる。一つは、父が遺した巨大な足あとが一つ片付いたこと。二つ目が、家内の母が昨年亡くなり、親世代の遺した足あとの整理が、ほぼ終了したことだ。
そこで気づいたのが、足あとにも、いろいろあるという発見だ。
まず、私の父は大小おびただしい数の足あとを遺した。共通しているのは、自分の体験を、文書にまとめ、「生きた証」として遺すという考えだ。
 主要な著書の4冊を中心に、生涯にわたり、書き残した文書は、多岐にわたり膨大だ。その中で最大の足あととなったのが、ライフワーク『国家総動員史』(全13巻)だ。
主要な著書の4冊を中心に、生涯にわたり、書き残した文書は、多岐にわたり膨大だ。その中で最大の足あととなったのが、ライフワーク『国家総動員史』(全13巻)だ。
戦前、内務省の若手官僚として働いた父は、「国家総動員」プロジェクトに携わった。その時、父が担当者として入手した資料を、国家的貴重な記録だと考えたのだろう。戦中はもちろんのこと、戦後も、度重なる転勤にもめげず、生涯大切に持ち歩いていた。
戦後、世の中が落ち着きを取り戻した時、職務を通じて、見聞きした事実を遺し、後世に伝えることが、自分の使命であり「生きた証」と考えたのだ。
その背景には、戦勝国による敗戦国の一方的な裁きに対する疑問があり、事実の記録を遺せば真実がわかってもらえる、と父にはつよい信念があったからだ。
そこで、父が取った行動の第一歩が、直接関係していなかった部署の人たちへの聞き取り調査である。同時に、その証言を裏付ける資料を収集し、さらに関連書籍にはお金に糸目を付けず書店から買いあさってきた。
現役を退職した後も、15年間かけて、これらを集大成し、世に送り出した。それが『国家総動員史』(全13巻)である。完成までの歳月は、50余年に及んだ。
その結果、父が亡くなった時、遺されたものは同書の在庫200セット、さらには段ボール箱300個に相当する書籍、同150個の資料という巨大な足あとだ。
この足あとの処理に、私は父が亡くなってから、30年を要した。書籍は古本屋を経由し市場で売却できた。だが、市場で売れない資料は、神戸大学の先生延40人の方々に、8年かけで整理していただいた。
それが昨年の夏、トランクルームから、国立歴史民俗博物館に送り出されたのだ。
これが冒頭で述べた「巨大な足あと」が一つ片付いたということだ。同博物館は2年かけて整理し、その後、一般公開されることになっている。
これで、父の足あとは、日本の子孫のために残ることになる。
この本稿を書いているうち、私はこれまで母のことをまったく評価していなかったことに気づいた。
父が家中に放り出す紙の山を、母は結婚以来、半世紀以上にわたり、整理保管してきたのだ。最後には、母屋の書庫と、屋外の3棟の物置に、ていねいに整理し、収納していた。
天井が2メートル以上もある物置に、重い本や資料をぎっしり詰め込むのは、どんなにか大変な仕事だったかと思う。
父の足あとを、縁の下で支えたのが、母だったのだ。今頃、母の貢献を再評価していることを申し訳なく思う。見事な夫婦の連係プレーだったのだ。
私の両親が遺した足あとと対照的なケースが、家内の両親である。
義父は、銀行を卒業したあと事業会社に移り、経営不振の会社を立て直し、同社で「中興の人」と言われる業績を上げていた。義父は偉大な足あとを会社には遺した、その一方で、家庭にはお金以外はなにも残さなかった。
趣味が、ゴルフと英語のパズル程度だったので、自然にお金が残ることになったのだ。
この状況を見事に生かしたのが義母である。
専業主婦として、ただ家庭を堅実に守るだけではなかった。よく勉強し、財テクで大きな実績を挙げた。
私が、とくに義母を尊敬するのは、経済に対する目の鋭さだ。日経新聞は毎日2時間近くかけて精読していた。その上、証券会社のアドバイスを得て、義父が使わないお金をタイムリーに投資し、資産を着実に増やしてきた。
それだけではない。バブルの頂点で、義母は所有不動産の入れ替えを断行したのだ。その結果、家族の資産構成は確たるものになった。
義母が遺した足あとは、子供はもとより孫、ひ孫に及ぶほど、計り知れない大きな経済的な恩恵だったのだ。夫婦の連携プレーの妙がここでも発揮されている。
これまで考察した結果、私が得た結論としては、次の2点だ。この年で、私ができることには限界がある。著書も、財産形成も、いまから取り組むには遅すぎる。
そこで決意したのが、まず夫婦で要らないものを捨てることだ。
消極的だが、私の経験から痛切に実感したのが、不要な物の処理がいかに大変か、という問題だ。子供たちに負担のかかることは、遺したくないと思っている。
第2は、生きた証として『ファミリーヒストリー』としてまとめ、足あとを遺すことだ。
父の七回忌に当たり、兄弟で「愛する孫たちに」という文集をまとめた。母が亡くなったとき『私の自分史』という思い出文集を作り、親族に配った。
その際に集めた写真、メモなどの他に、これまで整理した日記、ノート、写真、和歌集、手紙、書籍など、捨てかねる思い出の品々がまだ残っている。家族の個人情報の整理は、これから行いたいと思っている。
子供たちは結婚し、我われ夫婦にも、孫ができた。将来は、我われ子孫のなかで、自分のルーツを知りたい、という希望を持つ子が出てくるかもしれない。
いまや家族制度が崩壊し、核家族社会になった。ドン・キホーテ的かもしれないが、親族の痕跡がきれいさっぱり何も残っていない、というのは申し訳ないと思う。
親族のつながりを知る手がかりとなる『ファミリーヒストリ―』を、どうまとめるかが当面の課題だ。
イラスト:Googleイラスト・フリーより
【了】