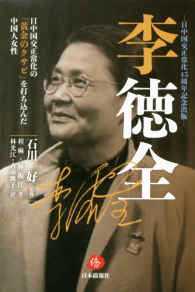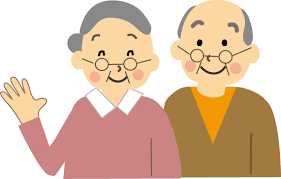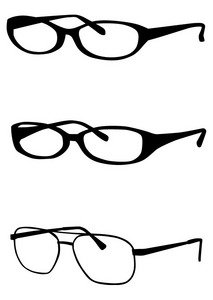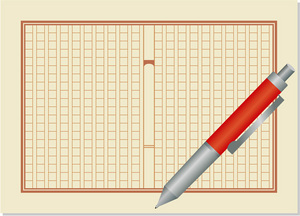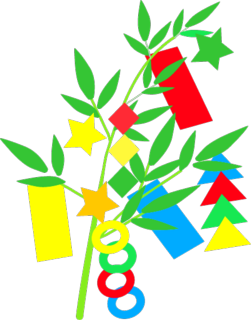パリ祭の日の恐怖の一人旅 武智 康子
2001年7月14日、私は国際学会に出席する主人に同道して、スペインのマドリッドに居た。
ちょうど前日、学会も終了したので、主人は仕事でスペイン北部の鉄鋼会社に行くことになっていたため、私は一人でパリ経由で帰国の途についた。ただ、それは私にとって初めての海外旅行の一人旅だったのだ。
パリでの乗り換えもあり、不安がいっぱいだった、
 マドリッドの空港で主人と別れ、旅券検査場も無事に通過し、予定のエアフランスに搭乗した。
マドリッドの空港で主人と別れ、旅券検査場も無事に通過し、予定のエアフランスに搭乗した。
しかし、予定の時刻を過ぎてもなかなか飛び立つ気配がない。始めは落ち着いていた私だが、パリでの乗り換えのこともあり、だんだん不安になり、スチュワーデスを呼んだ。そして、拙い英語で尋ねた。すると彼女は
「時間が来ても、搭乗していない人の荷物を降ろしているところだ。」と言う。
よくあることなので、その時はさほど驚かなかった。
これが恐怖の前ぶれだった。
私が乗った飛行機は、約50分ほど遅れて出発し、2時間後無事にパリのシャルルドゴール空港に到着した。
トランジットの時間は、十分にあったので、一応ホッとした。大きなトランクはスルーにしていたので、機内持ち込みの小さなピギーを引いて、乗り換えのJALのカウンターに行った。
東京行きの手続きが済むとJALの制服を着たフランス人の女性が「どうぞ、こちらへ」と案内をしてくれた。私は不思議に思ったが、彼女の後に続いた。
案内された先は、ビジネスラウンジの特別室だった。
私は驚いて怪訝な顔をしていると、彼女は、私の一人旅を心配して主人が、事前に連絡をしていてくれたことを、明かしてくれた。
せっかくなので私は、コーヒーを飲みながら一休みすると、未だ時間があるのを見て、ラウンジのフロントにいた彼女にピギーを預けて、免税店に出かけた。
そして私は、一つの店でフランス刺繍の施された素敵なテーブルクロスを買った。
その時である。
広く大きな空港に、けたたましいサイレンと早口での放送が鳴り響いた。何だか意味は分からなかったが、その様子から緊急事態が起きたことは理解できた。
私は、慌ててピギーを引き取るために、ラウンジに向かった。が、そこには既に警官がロープを張っていて、「逃げろ」と言う。
私は、ピギーを諦めざるを得なかった。中には、昨日マドリットの市内で買った、ジアドロのお人形が私のパジャマなどに、くるまれて入っているのだ。
しかし、そんなことは言っていられない。
私も、ハンドバックとテーブルセンターだけを持って、他の客達の後を追ってラウンジと反対方向に逃げた。
それから、15分位経っただろうか。先ほどまで私が居たラウンジの方角の外から「ドカーン、ドカドカーン」と言う大きな爆発音が聞こえ、一瞬建物が揺れた。
周囲の人達と顔を見合わせ、生きた心地がしなかった。気がつくと、隣に居た黒人女性と手を握り合っていた。肌は黒いが手の平は白い。ちょっと違和感はあるが同じ人間の手だ。その時私は、人はみんな同じで通じ合うものがあるのだ、と心に強く感じた。
30~40分後にやっと緊急事態は解除されたが、その放送の直後に、広い空港に私の名前が響いた。私は急いで指定された場所に走った。
そこには、チェックインの時私をラウンジに案内してくれたフランス人のJALの女性が、私のピギーを大事そうに持って待っていてくれた。
私は、驚きで言葉が出なかった。彼女はあの緊急事態の中、私のピギーを持って逃げてくれたのだった。
一度、諦めたピギーが今、私の眼の前にある。ジアドロの人形も戻ってきた。こんなに嬉しいことはない。
私は咄嗟に彼女の手を両手で握って「ありがとう」を繰り返した。そして、持ち合わせていた京都の舞妓さんの絵が描かれている縮緬の風呂敷を、感謝の気持ちをこめて渡した。
彼女も喜んで受け取ってくれた。
彼女の話によると、不審物は、私の居たラウンジにあったそうで、私が買い物に出た直後に発見され、建物の外に運び出されて、爆発物処理班によって爆破されたそうだ。
その日は7月14日、ちょうどパリ祭の日である。大勢を狙ったカタルーニヤ地方の民族テロだったのだろうか。
彼女にとっては、仕事の一部だったかもしれないが、私は買い物に出かけた運も味方してくれて、何事も無かったようにJAL便に搭乗して帰国の途に着くことができた。
機内では、偶然、隣り合わせになった日動画廊の女性社長と、美術談義ヲ交わしながら翌日の昼に私の一人旅は、無事に終った。
イラスト:Googleイラスト・フリーより