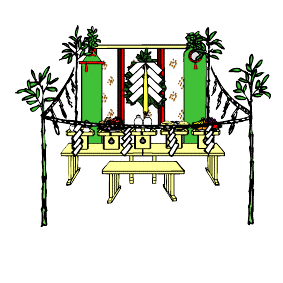ふたりでひとり 森田 多加子
夫婦という単位になって58年。男女の役割は、結婚したころのままずっと続いていた我が家だが、最近、夫婦間の仕事の役割が曖昧になってきた。
重い荷物を持つ、ビンの蓋を開ける、電球の取り換えなど、今までは夫がやっていたのに、いつの間にか私の仕事になっている。
電球の取り換えを、私がやるようになったのは、夫に比べると、高いところに上るのは、まだ私の方に安定感があるような気がするからだ。
 しかし怖い。若いころには、このくらいの高さに登ることなどは何でもなかった。たかが電球の取り換えじゃないかと思うが、足元が安定しないこの作業は、非常に怖い。おまけに頻度が高いのだ。
しかし怖い。若いころには、このくらいの高さに登ることなどは何でもなかった。たかが電球の取り換えじゃないかと思うが、足元が安定しないこの作業は、非常に怖い。おまけに頻度が高いのだ。
平成元年に家を建てたときに、蛍光灯の明るさが嫌いだという夫が、室内の大部分を電球にしてしまった。リビングには装飾的な室内灯が二か所あるが、それに4個ずつ付いている。ほかに単独に天井に直接ついている電球が4個、合計12個だ。
LEDという半永久的な電球ができたので、室内灯など変更できるものは徐々に取り替えていった。しかし、天井の4個は調光システム(明るさを調節できる)になっていて、LEDが使用できない。
同じものが寝室にも4個ある。
門灯などを含めると、調光システムの10個の電球を取り替える作業は、私にとっては、わりに早めにまわってくる。
どうしてこんな不必要なものにしたのかと、少々腹もたてている。
1個でも切れると、光は弱くなる。暗いのは嫌だ。仕方がないので、天井につくくらいの大きなスチールの脚立を買ってきた。重いが安定感はある。それでも足元がおぼつかないので、夫にしっかり支えてもらう。
電球一つ取り替えるのに、夫婦二人で大変な思いをしなければならない。脚立に登れるのもいつまでか、と心配になっている。
夫はというと、キッチンに立つことが少しずつ多くなった。料理教室に月に一度参加していて、かれこれ7年になる。
ある日、帰宅してみると、食卓に二人分の料理が並んでいた。「ジャガイモのガレット・ベーコンエッグ添え」なるものだそうだ。
一見、ちょっとした店のランチに出てくるようにきれいに盛り付けてあった。
「おお、やるじゃない!」
ジャガイモを細い千切りにして固めたガレットは、なかなか美味しかった。
最近は、レシピを見ながらの料理ができるようになったのだ。子どもたちが来るというと、張り切って何やら作る。
勿論、必要な買い物も自分でする。正月には、ココットを買ってきて、「筑前煮」を作った。レンコン、ゴボーなど、硬い野菜が、ほどよく柔らかくなっている。
悔しいけれど味も良い。子どもたちからも大変評判がよかった。
……が、考えてみると、何をするにもまず形からの夫。テニスをするからと、ラケット、シューズを揃えたが、何度やったのだろう。
登山のリュックと靴、キャンプの道具一式、一番長く続いたゴルフの道具もたくさんあるけれど、今はやっていない。
ココットが同じ目にあわなければいいのだが。
ともあれ、最近の二人は、今までの男の仕事、女の仕事を越えてしまった。
二人とも体力が落ちてきているので、どれが男の仕事か、女の仕事かなど考えることもない。二人でできることをやっていくしかない。
結婚した58年前には、夫が料理を作るなど、思ってもいなかった。
夫「作る人」私「食べる人」。ああ、善きかな。
イラスト:Googleイラスト・フリーより