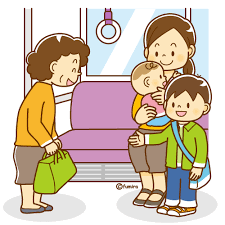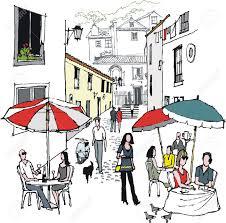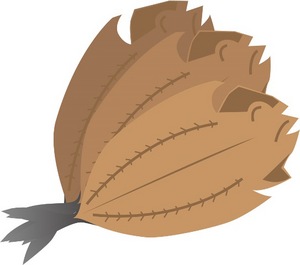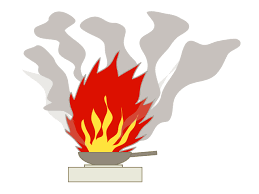孤独な生活 = 和田 譲次
五木寛之さんが昨年、晩年の生活をテーマにしたエッセイ集を出した。人生の晩年に自由な時間が出来て孤独を楽しんでいるという。
私は若いときにこの人の著作をよく読み、親近感がある。それに五木さんは音楽にも造詣が深く歌謡曲、ポップスなどについてラジオ深夜便で歌詞などを取り上げて解説をされていて、面白く聴いている。
皆さんと楽しく酒を飲みながら騒ぐのが私の本来の性格で、周りの人達もそのように理解している。
ある席で、「美術館で好きな絵をぼんやりと眺めているときが最高に幸せだ」と話したら、「あなたにそんな一面があるの」と、言われてしまった。
現役時代、人前で話す機会が多く、人材育成の講師などを務めていた。そのような時、始まる前の30分ほどは控え室で静かに過ごすようにしていた。
私が話しのための準備をしているとまわりの人たちは感じていただろう。私は、何もしないでぼんやりと過ごしていただけである、
 音楽活動の場でも同じで、本番の前短い時間、仲間から離れ静かに過ごすのが習慣になっている。多くの仲間は緊張を解くために冗談を言ったり、お菓子などをほおばっているのだが。
音楽活動の場でも同じで、本番の前短い時間、仲間から離れ静かに過ごすのが習慣になっている。多くの仲間は緊張を解くために冗談を言ったり、お菓子などをほおばっているのだが。
私の中に孤独な環境を求める静の部分があり、大事な事態に立ち向かうときには緊張感を求め独りぼっちになりたがる。
ところが一人ぼっちの孤独な生活が続くとマイナス思考になり悲観的になる。
昨年3月に肺炎になり、治療のためにステロイド剤を大量に長い期間、飲まされ、体調が狂った。これが回復した6月後半に、今度は転倒し首を痛めた。70日ほどカラーを首に巻いて過ごした。この間、医師からは人込みを避け、遠出も避けるように指示されていた。
病院通いと家の周囲を散歩する生活が半年以上続き、引きこもり状態の生活をおくった。
何もしないで無為に過ごした日の方がいやな感じの疲労が残った。不思議なことに、手帳に予定がいっぱい書き込まれ忙しく動き回っている方が体に疲れは残るのだろうが、充実感はある。
「あなたの部屋の中にCDや本が何冊も乱雑に散らばっている」
と家内から何度も注意された。音楽を聴いたり、読書にかける時間は十分にあるのだが、集中力が欠けているのか、すぐ飽きてしまう。ぼんやりとテレビを観て過ごしていた。
暇だから好きなことに時間が使える筈だが、心身が健康でなければ満足のいく生活が送れないことに気が付いた。このような生活を続けていると、精神的に落ち込み、うつ状態になる。幸いにも重症化する前に、これではいけないと気が付いた。
五木さんは、孤独だから人生豊かに生きられると書かれている。しかし、心が充実していないとみじめな生活を送ってしまう。特に病気療養中だと、その傾向が強くでてくる。
日野原先生は「人との触れ合いから、ときめきの心がおきる」そして、ときめきの心が沸かないと、美しいものに接しても、美味しいものを食べても満足に受け入れられないという。今になって先生の言葉が実感できた。
イラスト:Googleイラスト・フリーより