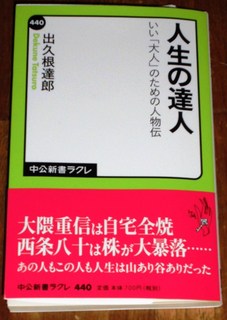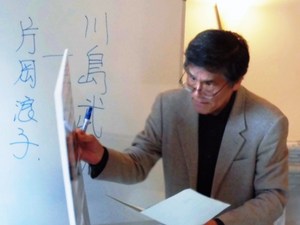朝日新聞・書評委員会メンバーの立石ツアー・深夜まで悦に(中)
朝日新聞・書評委員会のメンバー13人が、京成立石駅の線路側にある、『呑んべ横丁』に驚嘆していた。古い飲み屋街だ。日本国内を探しても、これほど古い飲み屋街はそうもないだろう。

アーケードは低く、細長く、2本通っている。『終戦後』『敗戦後』という言葉が似あう。そのことば自体がもはやはるか彼方に遠ざかり、それを使う人もほとんどいない。むしろ、『昭和の町が似合う』と置き換えた方がわかりやすいだろう。
『呑んべ横丁』は閉店した店もあるが、いまなお数軒が細々と営業している。昼過ぎから開店する飲み屋もあれば、かなり遅い時間から開けるところもある。さまざまだ。
同メンバーたちは興味の目で、『呑んべ横丁』の路地を何度も往復する。
「軒が低く、暖簾の下がった店入口が低い造りばかり。それは終戦後の日本人が栄養不足で、背が低かったから、当時の身長に見合ったものです」
昭和史研究家の保坂さんがそう語っていましたよ、と出久根達郎さんが教えてくれた。
「なるほど」
私はやはり研究家は観る視点が違うなと思った。
朝日新聞「文化くらい報道部」の記者が、「横須賀にはレプリカでこれに似た、『昭和の飲み屋街』をつくっているんですよ。行列ができるほど繁盛しています。この「呑んべ横丁」は本もの。これをなぜ、もっと生かさないのかな?」と首を傾げていた。

この先『のみや横丁』は取り壊される、そうした運命にさらされているようです。京成電車の路線拡張とか、高架線とか、駅ビル開発とか、いろいろ取りざたされている、と私が説明すると、
「残すべきですよ。横須賀などは町おこしで、あえて創っているんですよ。もったいない」
同記者は、そう強調したうえで、あらためて取材にきますと話す。彼は経済関連の書評の担当記者のようだ。
書評委員会のメンバーの一人は、ネットで事前に知り得た「鳥房」が火曜日休みで残念がっていた。
立石駅の踏切警報機が鳴る音がひびく。それを聞きながら、わき道、さらに折れ曲がった細道へと入っていく。夕方4時で、まだ日が高いけれど、駅裏の飲み屋の一部は営業している。むろん、客は入っている。立ち食い鮨屋などは客があふれている。
「立石はこんなにも、早く店が開いているんですね」
それが奇異に感じるらしい。
「もっと早くに店は開いていますよ。人気店の『うちだ』などは」
その背景の説明をした。