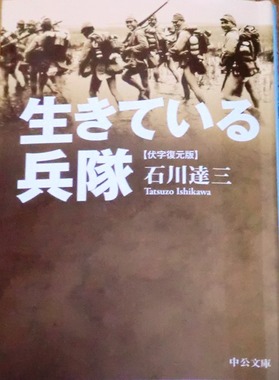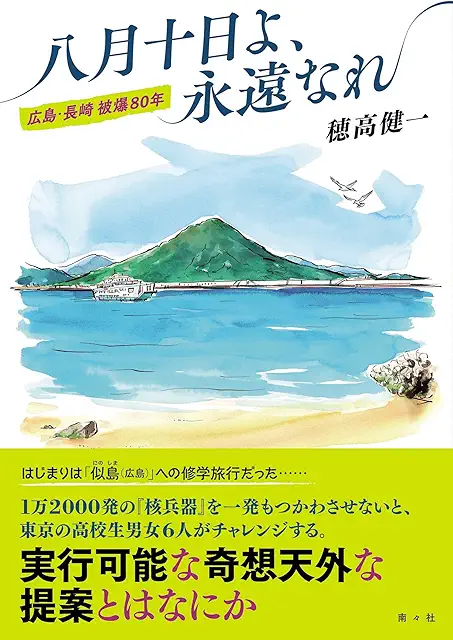戦争抑止は民がなすべきだ。 「元気に百歳・エッセイ教室」90回の序文より
歴史作家は歴史年表で書く。それはかならずしも史実ではない。
数年前の国政選挙では、脱原発か、2~3%の経済成長か、と二つの政権が争った。国民は2~3%の成長を選んだうえ、憲法改正ができる3分の2の議席という大きな政権力を与えた。
『経済(食べること)が、政治を動かす』
それは如実な証明だった。
 この国政選挙は、後世の歴史年表にはまず記されないだろう。では、どんなものが50年後、100年後の歴史小説に描かれるのだろうか。
この国政選挙は、後世の歴史年表にはまず記されないだろう。では、どんなものが50年後、100年後の歴史小説に描かれるのだろうか。
1945年から戦争孤児、満州引揚げ、安保騒動、公害の空気汚染、イタイタイ病・水俣病、浅間山荘事件、内ゲバ事件、地下鉄サリン事件、秋葉原無差別殺人、3・11東日本大地震、フクシマ原発事故とつづいてきた。
『とてつもなく危険な時代に生きていた』
これを知りえた、後世の人はきっととてつもない時代に生きてきたと思うだろう。
しかし、葛飾区内にすむ私は、これらの事件・事故とほとんど無関係だった。
動乱期の幕末をみると、寺田屋事件、池田屋事件、禁門の変、第一次、第二次長州征伐、薩長同盟(実際には成立していない)は、倒幕活動へと結び付ける。
そんな幕末小説がほとんどだ。当時の葛飾村の民は、京都・長崎・江戸の斬り合いなど、地下鉄サリン事件とおなじで、人々の話題にはなるが、庶民生活には関わりがない。
江戸時代は『家』社会である。個人の考えは後回し。女は子どもを産み、男が「家風」に見合った教育をする。『お家のために』『お家の存続』がすべてに優先する。
家臣は扶持をもらう「島津家のため」「毛利家のため」に尽くすとなる。それなのに、江戸時代を「藩」で見ていると、歴史の事実誤認を起こす。
第二次長州征討で、将軍家の徳川家は長州藩を消す気持ちなどみじんもなかった。毛利家を叩きつぶす。それだけなのだ。
毛利家を打ち負かしたら、長州藩の大名家はいずこかの「家」と入れ替えるのみ。
毛利家の立場からみても、勝っても負けてもいない。現・山口県から火の粉を払ったにすぎない。
第二次長州征討の半ば、トップの德川家茂将軍が死去した。
「喪に服するから、各藩の軍隊はひとまず国もとに帰れ」
と一方的に停戦しただけなのだ。
慶喜はさらなる第三次攻撃を思慮していた。
この戦争には大きな後遺症があった。国内経済が急激に悪化し、物価高騰で、庶民の生活は圧迫された。となると、武器を持たない民衆だが、許しておけない。大反発のパワーが「ええじゃないか運動」となり、愛知から広島・尾道まで、男女を問わず一気に荒れ狂ってしまった。
将軍家の徳川家といえども、民衆に武力で鎮圧できない。為政者と民衆が血と血で戦うと、国家の破滅に及んでしまうからだ。
徳川慶喜には外交能力はあるが、優秀な経済ブレーンがいなかった。
結果として、「大政奉還」で、天皇家に政権を返上したのだ。だれも「徳川家」を倒していないのだ。これは倒幕ではなかった。
「薩長による倒幕」は、明治政府が自分たちに都合よく作った、歴史のわい曲だった。
攘夷(外国人へのテロ)を叫ぶ下級藩士たちが、戊辰戦争を引き起こした。そして、東京に明治軍事政権をつくった。
政治家となった、毛利家の下級藩士の山縣有朋が武力主義で、明治6(1873)年に「徴兵令」を発布した。国民に武器を持たせたのだ。
明治22(1889)年には、それを法律にまで昇格させた。それが第二次世界大戦まで77年間もつづいた。国家総動員令で、婦女子までも巻き込まれたのだ。
戦国時代まで、戦争は武士のしごとだった。農商は戦場へと荷運びを手伝わされても、戦いが始まれば、逃げてもよいのだ。流れ弾に当たらなければ、畑仕事をしていてもよい。
その意味において、国民皆兵を導入した山縣有朋の罪は末代までも重い。
一度飲んだ麻薬の味は忘れられないという。
私たちの子孫が、外交の失敗で戦争にでもなれば、自衛隊の隊員数だけでは国が守れない、国民皆兵制が早急に必要だ、と政治や軍人は言いだすに決っている。
『戦争は起こさせない』
それしか徴兵制を防ぐ道はないのだ。それには、他国にたいして強硬策を取れ、と民が熱くなったり、政府を突き上げたりしないことだ。
日露戦争の前に、新聞が三国干渉のロシア攻撃をやたらくり返し、戦争へと誘導した。こうした先例があるだけに、マスコミの論調にも目を光らせておかないと、民がいつしか戦争への軌道に乗せられかねない。
戦争をひとたび起したら、民は銃を持たされるのだ。「生ある人間を殺せ」と。そして、「みずからも死ね」と。
【補足】
元気に百歳が主催する:「エッセイ教室」がことし(2016年)6月で、100回になります。10回ごとに、記念誌を発刊しています。私は記念誌の序文を書いています。それを随時取り上げてみます。
こんかいは元気に百歳:「エッセイ教室90回記念誌」 平成27年7月より