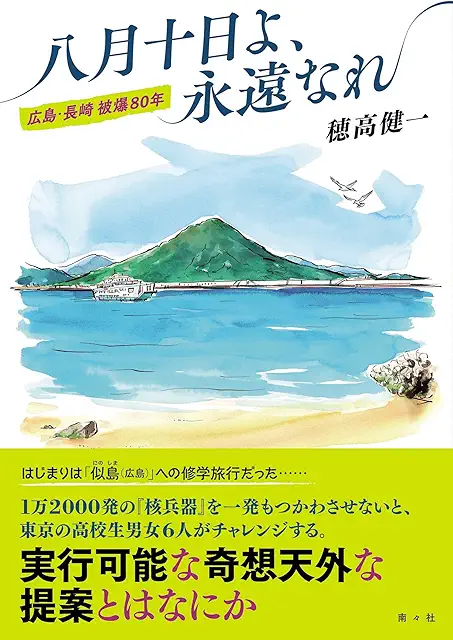32回「元気エッセイ教室」作品紹介
エッセイ作品では一般的に会話文が少ない。私はできるだけ、会話を入れなさいと指導している。
上手な会話文の挿入は読者を引き込むうえ、登場人物が立ち上がってくる。散文において、会話の効果は高いものがある。小説でもいえるが、上手い会話は文章を生き生きさせる。
「会話文」は、「話しことば」とは違う。ここが最も押えどころだ。
日常会話をそのまま文字にすると、ダラダラと冗漫な会話の連続になる。必要で、外せない、限られた会話文のみに限定することだ。
会話文の技法(コツ)として
①ムダな言葉は書かない。とくに時候の挨拶、別れのことばは省略する。
おはよう。暑いですね。さようなら。お元気でしたか。久しぶりですね。
②会話のなかで、説明文を展開しない。
作者の説明が会話で入ると、読者が遠のく。
④読者が予想しなかった、会話を連ねて行く。
⑤会話から、人物の動作や心理がわかるように書く
⑥双方の意見が違う。対立する。それを会話にすると、良い流れがうまれる。
これら①~⑥の項目について、会話文の実例をもって説明した。
今回の作品紹介は、心に響くもの、国内外の物珍しい体験、旅行先で心痛むもの、過去に遡って両親を想う懐古の情などと、幅が広い。他方で、日常の些細な出来事だが、一気に読ませるもの、動物、植物との心底からの触れあいの作品が並ぶ。
森田 多加子 セピア色の写真
36階のレストランから眺めは、五月晴れで素晴らしかった。「私」たち4人は静かな雰囲気で料理をいただいた。コースが終った頃、同席のM氏が幼少の写真を数葉見せてくれた。母様に抱かれたものが、「私」の目をひきつけた。
帰りの電車から、私の母親の懐古に入るのだ。母は死の前、5年間は寝たきり。面会に行っても、私をみる母の目には反応がなかった。いま実母の顔を思い出す時はいつもこの顔である。
帰宅してから、古いアルバムを広げた。写真はセピア色だ。最初のページは父と母が一人ずつ写っている。次が私のお宮参りの写真。丸髷を結った母に抱かれた私と、7歳年上の姉が立っている。父の姿はなかった。
「宮参りといえば、生まれて30日後くらい。父は何をしていたのだろうか」という疑問につながる。そこから、父が一緒に写った家族写真はない。父と遊んだ記憶もない。
『今まで考えたことのない、母の哀しみが襲ってきた。若かった母の顔が泣いている。母の若い時の笑顔を思い出そう。笑った顔を忘れないようにしよう』と結末に導いている。
母の死期の痛々しい状態と、若き母親の悲しみが二つ重なりあった、良い作品だ。作者は語っていないが、父親という男の身勝手が読み取れる。
吉田 年男 クンシランの植替え
ベランダの西側には、父が遺したクンシランが6鉢ある。ヒガンバナ科の多年草で、茎が細めで長い「普通種」だ。花は限りなく赤に近いダイダイ色で、雨に濡れると一段と鮮やかに映える。赤みを帯びた神秘的な色だ。
葉は熱さ寒さに弱い。11月頃になると、鉢を家の中に取り込む。3月の終わりにはベランダに持ち出す。6鉢となると、重い作業だが、毎年繰り返えしている。
ベランダは光線の強い日もある。銀色のアウトドア用シートで、日よけする。それでも日の当る葉には、火傷のあとがある。柿の枝が大きく伸びて、日よけの手伝いをしてくれている。日影をよい事にして、猫が鉢の上に乗っている。
花が終わると、植替えの時期だ。
『花がついていた茎を元から切り取る。茎から液体がシューと出てくる。元気に立っている茎にメスを入れているようで、可愛そうな気がして、何か後ろめたさを感じる』と作者の心温かい心情が描かれている。
鉢から慎重に株を取り出す。細く白い根がたくさん絡まっている。
『古い根を取り去り、根と根の間に指を入れて、手櫛のようにして土を払う。子株が出来ていれば、親株から切り離さなす。狭い鉢のなかで、しっかり親子の絆を温めていたと思うと、切り離すのに気が咎める』とわが子の惜別のような心境で描かれている。
来年も、赤みを帯びた神秘的なダイダイ色をぜひ見たい。他方で、クンシランの植替えは、つねに申し訳ないと思う。
人間と植物、その生命がふれあう良質の作品だ。
高原 真 青春のカーニバル
妻は手術後から1年半以上も経っている。膵臓3分の2、十二指腸と胆嚢も摘除している。胃に小腸を接合したから流れも悪い。便秘が続く。
お腹を温めたらどうか。「私」は区の入浴券で、『四季の湯』に妻を連れて行った。大衆浴場を改装したものだ。受付のある広間だ。男女で休息できる。テレビ、マッサージ機、飲み物もあった。
二人は湯上りの約束場所を広間とした。
強力噴射のジエット、薬湯、サウナがあった。『強力噴射ジエットなら、家内のお腹をほぐしてくれる、マッサージ効果がある』と期待した。
「長風呂」の妻、「烏の行水」の私。時間を費やすように薬湯に入ったり、噴射風呂にも入ったりした。
新婚のころ、ふたりは味噌醸造業の「離れ」を借りていた。六畳一間で、台所と便所はあったが、水道はない。風呂は近くの銭湯に揃って行った。
湯上りで待たされるのは私だった。『寒いときに待たされるのは困る。男湯と塀一つの女湯だから、私が出る頃に口笛で知らせることにした。曲はその頃ハヤっていた歌謡曲だった』。すると、新妻が笑みをたたえ、洗い髪を指で櫛上げしながら出てきた。ふたりは寄り添って家に向かう。ほのかに匂う湯上がりの香が心地よく漂っていた。
「四季の湯」で、そんな追憶から、出る合図として口笛で知らせよう、と考えた。曲名も歌手も忘れたが、メロデーは覚えている。『いざ青春のカーニバル』という一節が入っていた。
私は時間を見計らって、合図の口笛を吹こうと試みた。音がかすかにでるくらいだ。意外だった。
『頬や唇の筋肉を必至で動かしたが、高音がでないし、滑らかに曲が流れないのだ。やっているうちに、かろうじて新婚早々のメロデーが曲がりなりに高く奏でられた。家内に聞こえたろう。どう感じたか』と案じる。
妻はなかなか出てこない。私は牛乳を飲んで広間で待った。マッサージ機にかかると、眠気がでてきた。妻に肩をつつかれて起された。
「口笛が聞こえたか」と訊いたところ、なにも聞こえなかった、と妻は言う。
私は帰る自動車の中で口笛を吹いてみせた。妻が助手席で「若き日の憧れを胸に抱き・・」と、口笛に遅れてたどたどしく口ずさんでいた。しかし、中途でしぼんで、二人とも無口となった。
切れ味の良い、完成度の高いエッセイである。新婚時代と現在の差異が口笛に集約されている。それぞれのエピソードで夫婦愛がにじみ出ている。
中澤 映子 犬猫の仲 動物歳時記その22
「犬」の独白である。「私」と西洋猫のムーちゃんは、とても仲のいい『犬猫の仲』だという。
オス猫のムーちゃんは社交的で、女好き。かつてガールフレンドがいたころ、「私」には目もくれなかった。彼女が死ぬと落ち込んでいた。一年も過ぎると、「私」に興味を持ちはじめた。屋根付きテラスで日向ぼこをする私の鼻先に、ムーちゃんが近寄ってくるようになった。
初夏の陽射しが強くなると、暑いのが苦手な私は母屋の冷たい廊下にベタと伏せている。ムーちゃんが、私の目の前に身体を横たえ、私をジーッと見つめている。『やはり、私に気があるのかしら?』と思う。
私が小俣一家に仲間入りした歴史を紐解く。日吉の街で奥様に出遭い、拾われたという。1年後、ムーちゃんが同家にやって来たのだ。
『犬猫の仲』の仲良しな二人ですが、時々ムーちゃんの奇行に驚かされる。
リビングキッチンで、突然『猫ドア』が開いた。外から帰還のムーちゃんがそれに突進した。私には目もくれず飛び越えていく。ビックリした私は『ワン!ワン!』と吠える。ご主人から『アイ、やかましい』と怒られるのは、私なんだから。翌日ムーちゃんが私のそばに寄ってくれば、まんざらでもない顔をしちゃう。
犬猫のラブラブが、犬の独白で書かれた、独特のスタイルだ。主人公(犬)の恋する心理描写が人間的で、作品を盛り上げている。
山下 昌子 風 薫 る
夕食の支度をする「私」は、テレビのニュースを聞くともなく聞いていた。
オバマ米大統領がプラハで、「核を使用した唯一の保有国として、行動する道義的責任がある」と演説したという。これはすごいことだと感動した。
翌日の新聞を読むと、アメリカ国内事情からの発言だ、と冷ややかな意見もある。理由は何であれ素晴らしいことだ、と私は思うのだ。
『今後、核に対するアメリカのニューリーダーの姿勢が、世界中に伝わり、大きなうねりとなっていくことを期待したい』と続く。
夫は半年に一度の句会が迫っていた。題は「薫風」で、作品の推敲に余念がない。家のなかで、「薫風や」、「風薫る」などと、常にくり返している。「私」の耳にこびりついたのだろう。
「風薫る オバマ語るや 核廃止」
私の口から、ふいに出てきた。日ごろ俳句を作ることもない「私」なのに。「風薫る」という爽やかな言葉が、オバマ演説にぴったりだと思ったからだろう。
「オバマ語りし、このほうが良いんじゃないの」
夫が横から口をはさんだ。
夫の意見を受け入れた私は、オバマの薫風を心から感じて過ごした。それもつかの間、北朝鮮が予告もなく核実験を強行した。この不条理な悪あがきに、心は冷え切ってしまった。オバマ大統領の歴史的発言は、期待だけに終わるのだろうか。不安な気持ちで、結ぶ。
作者の核廃絶の信条、信念が無駄なものがなく、ストレートに描かれている。それだけに、読み手は共感をおぼえる。他方で、夫婦愛が底流に流れている。
二上 薆 小説とは 思い出すままに
今年は太宰治、生誕百年の記念の年である。読書会は太宰治の「斜陽」で、論評が求められた。
「私」はもう半世紀ほど前、太宰の菩提寺、三鷹の名刹禅林寺の界隈を散策をしたことがある。玉川上水に沿った、人影まばらな静かな道。太宰治が三十九歳で入水心中した場所かなと思いながら歩いていた、という記憶がある。
このたび文庫本で115版の「斜陽」を改めて読んでみた。
『筆の冴えは誠に見事ではあったが、読んでがっかり。心に残る爽やかさは何もない。残るものは澱(おり)ばかり。鮮やかに周りを描き、この世の辛さ、生きることのはかなさ、苦い思いを極めて明快に述べる、著者の筆の見事さがかえってそうさせたのかもしれない』
そんな感想から、読書会への提言はやめた。他方で、読み物、小説って何だろう、と考えた。
小学生時代は毎月、少年倶楽部、少女倶楽部を読んだ。楽しい、面白い、という思いがあった。山中峰太郎の「亜細亜の曙」、江戸川乱歩の「怪人二十面相」、平田晋策の「昭和遊撃隊」、佐藤紅緑の「花咲く丘」、などなどである。
最近は殆ど読まないが、いまの小説はつまらない、という思いも再燃した。先ずは読んで面白く、爽やかな感慨が残ってほしいと思う。小説は時代に応じた風潮で創作される。高年者には合わないかも知れない。
坪内逍遥の「小説神髄」で、小説は芸術であるという。多木浩二著「戦争論」の末尾で、「もし思想、芸術を作り出す能力や、日常生活を維持してゆく知恵がなければ、人類はとっくに滅亡しているに違いない」という。
もう一度、小説とは何だろう。改めて問い、小説の面白さを呼び戻して欲しい、と導く。
作者の意見が明瞭な作品だ。太宰治「斜陽」の論評としても、価値あるもの。時代と年齢によって、一つの小説のとらえ方が違ってくる、と上手に運んでいる。
上田 恭子 七十代最後の夜
高層ホテルの21階から眺める夜景は、霧雨にけぶって、おぼろに見えていた。 眼下には新幹線、山手線、京浜東北線、東海道線が模型のように、行き来する。私の脳裏には、かつての子育ての思いが浮かんだ。
長男が中学生の頃、HOゲージに夢中になっていた。次男も真似て9ミリゲージの模型を集める。お年玉や小遣い、誕生祝、それらを全部注ぎ込む。
その次男が中学生3年のとき、私に見せたのが、ベニヤ板に9ミリゲージの線路を貼り付けて、小さな列車が3台ほど繋がって立派に走っているものだった。途中には引き込み線まであった。
父親が外国旅行から、9ミリの列車を3台ほど買ってきた。次男はとても嬉しかったようで、ジュータンに顔をつけて、目を光らせて見ていた。
21階の窓辺の私は、明日は80歳になる。
『長い人生、悔いはいっぱいある。涙もたくさん流したけれど、いま私は幸せ。飲めないワインにふと酔って、70代最後の夜は更けていく』と結末で、情感深く結ばれる。
濃密な人生が凝縮された良品だ。
塩地 薫 ひ げ
「私」は傘寿記念で、ひげを生やすことに決めた。妻は大反対である。八歳の孫娘が横から
「おじいちゃんは、ひげが似合うよ」
と賛成する。孫娘は、35歳の頃の「私」のひげ面の写真を見たらしい。
当時の私は、静岡の新設事業所の責任者だった。激務で、1日3、4時間の睡眠が続き、肺結核になってしまった。個室での絶対安静を宣告された。
妻以外の面会は謝絶。新聞やラジオなど、東京オリンピック情報からも隔離されていた。全くの無の世界に閉じ込められた。私はひげを剃ることもしなかった。
3ヶ月後には、肺はきれいになり、空洞も消えた。他方で、無精ひげは立派になった。廊下を歩くと、すれ違う人たちが、私より先に通路を空けようとする。
妻は毎日、病室に来て、私の体を熱いタオルで拭いてくれていた。それを知った空巣狙いがいた。留守番の二人の息子を手なずけて、カメラとビデオカメラを堂々と持ち去ったのだ。
外出許可をとって一時帰宅すると、捜査官のなかに、立派なひげの警官がいた。その警官が、私を見て身構えた。私のひげの方が、手入れしていないだけ迫力があったのだろう、と見なす。
これを気に、ひげを伸ばすことに決めた。100日ほど、ひげ剃りをやめておいた。紹介された床屋に出向いた。椅子に座ると、背もたれが倒され、ひげ剃りができる体勢になった。床屋職人は私の顔を眺めて、
「あなたのひげには、ムダ毛がない。このままが一番いい」
といって奥に引っ込んでしまった。
こんなエピソードをもった私だ。カストロひげが似合うと思う。妻は、無精ひげを決して認めようとはしない。孫娘はリンカーンひげのイメージで、伸ばすことを勧める。『リンカーンは小学生の少女にすすめられて、ひげを生やしたのだ』という。
私の夢は、立行司の19代「ひげの伊之助」のあごひげだ。米寿には、妻も認める白いあごひげを鷲づかみして、ぐいとしごきたいのだ。
テーマが『私のひげ』に絞り込まれ、妻と孫娘の意見の違いが作品に求心力と説得力を与えている。床屋職人の態度はすがすがしいものがある。
作者のひけは写真がなくても、カストロ、リンカーン、立行司の伊之助という運びから想像できる。
藤田 賢吾 初めての海外ゴルフ
「私」はカリフォルニアで、海外初のゴルフをすることになった。サン・ディエゴ動物園に隣接するゴルフ場だった。
朝10時ごろに、『バルボア・リンクス』というゴルフ場に着いた。海外ゴルフは初めてだけに、フロントで、あれこれ聞く。順番待ちの間、ヘンリーという人と話がはずんだ。と同時に、同じパートナーになった。
他の人にも「日本からやってきた」と挨拶すると、「わざわざ日本からきたのか。オーナー特権で最初にどうぞ」と言ってくれた。第一打のボールは、グングン右へスライスした。
このグループは高齢者ばかりが、上手なプレーヤーだ。「年に何回ぐらいプレーしますか」と聞いた。小柄の一人は1週間に2~3回だという。シニア割引から、ワンラウンド20ドルぐらいでプレーできるらしい。暇ができれば、コースを回っているようだ。
私の二打は藪の中。次のボールは、ゴルフ場脇の道路を越えて民家の庭に飛び込む。それらミスの多いエピソードが書き込まれている。
9番ホールを終えると、プレーヤーはそれぞれバッグから、サンドイッチ、バナナ、コーヒーを取り出し、食事をはじめた。僕のバッグは借りたものだから、何も出てこない。ヘンリーは丘の上にある売店を教えてくれた。
プレーが再会すると、スコアカードに記入する人は誰もいない。高齢者のゴルフは、スコアではなく、歩いて回ることだと知るのだ。
最終ホールで、私はようやくパーがとれた。うれしくなって、ヘンリーに向かって、「パーだ、パーがとれたっ」と叫んだ。彼は振り向いて「だから、どうなんだ」と、そっけない返事だった。スパイクシューズのまま駐車場まで歩いて、そこで履き替えて去っていった。
日米のゴルフの違い、考え方、とらえ方の違いが上手に運ばれている。と米国シニア層のゴルフのプレーは巧い。ゴルフが日常的なもの、という根拠がさりげなくしっかり書き込まれた作品である。
和田 譲次 ストレスの痛み
5月の連休明けの頃、左腕が痒く、妙な痛みが出てきた。そのうえ、虫に刺されたような発疹が、首筋から指先にまで広がってきた。痛さは我慢の限界を超えた。ネットで調べると、帯状疱疹らしい。
土曜日で近所の医院は休診日。音楽仲間のK医師に電話してみると、診察を受け付けていた。本職は整形外科。「この際は何でもいいや」と出むいた。
典型的な帯状疱疹だが、軽度だという。抗ウィルス剤が投与された。一週間服用したら快方に向かうという。
左指の麻痺を説明すると、「時間はかかるけど、感覚は戻りますよ」とあまり心配してくれない。この医師はバイオリン弾きだが、私の心配ごとにきづいていない。
5日間ほど薬を飲み続けると、痛みは和らいできた。強い副作用で、胃腸の調子がおかしく、気力も萎えてきた。薬の服用を止めたい。ふたたびK医師をたずねた。「少々辛くても薬は最後まで飲みなさい」という。心身のストレスが高まり、免疫力が落ちると、帯状疱疹はできやすい、と説明を受けた。
「貴方はいま、がんと向き合っている。ストレスをためたらダメです。好きなことを思う存分やりなさい」とアドバイスしてくれた。
現役時代はストレスには強いと自負していた。集中力を高めるために、あえてそれを利用していたきらいがある。管理者対象の研修会で、私はストレス・マネジメントの必要性を説いてきた。他方で、「仕事で成果を挙げるためには、それに見合った、遊びも大切です。美味しいものを食べ、好きな音楽、絵画、芝居なども楽しみなさい。時間やお金を自分の楽しみに投資しなさい」と説いてきたものだ。
いま振り返ると、他人にはあれこれ能書きを述べてきたが、「貴方はどうなのですか」と問われるとウーンとつまってしまう。現役を離れた後は全てが不完全燃焼だった。ストレスを追い払うために何をしようか。音楽、旅行,読書、絵画鑑賞、酒、料理など、あれこれ考えると、またストレスが溜まる。
作者は病気である。病状とむかいあう姿が距離感をもって書かれている。それが作品の厚みになっている。仕事人間時代のストレス賛歌と、現在との対比とが際立つ良品だ。
中 村 誠 百足(ムカデ)の出現!
食卓から立ち上がろうとすると、百足がズボンのベルトを這っていた。
「ひゃー、この野郎め」
と払いのけて、床に叩き落とした。スリッパで力いっぱい踏みつけた。床上はじゅうたん。「私」が踏みつけても、百足は頭を左右にして暴れる。
板の間まで引きずり出し、さらに強く踏みつけた。少し弱ったところで、庭石の上に投げつけた。まだ動く。シャベルで一撃し、胴体と切り離し、息の根を止めた。完ぺきな退治だったと、こまかく、粘っこく、格闘が書き込まれている。
昨年、夏と秋にも、同じように百足を退治した。妻はそれを思い出したようだ。
「もう一匹、つがいの相手がいるはずよ」
妻は真剣な目つきで、ごみ取りを片手に持ち、周りをキョロキョロと見まわす。
「まさか、ズボンの上まであがってくるとは、驚くよ」
私は一撃の退治で、気分も落ちついてきた。
踏みつけて首はね飛ばす百足かな 誠人
数日後、シロアリ検査の業者がやってきた。五年契約の満期がきたのだ。
20代の検査員は20分ほど床下でゴソゴソやっていた。額の汗を拭きながら出てきた。デジカメで撮った5、6枚の写真を見せながら、
「これがカビです。大分出ていますね」
とシロアリ防止の薬品散布を強く勧める。ほかの写真をさして、
「くすりが切れたのでしょう、百足が多いいですね、これがゲジゲジです」
「百足退治も出来るのかい?」
先ずは百足やゲジゲジなど普通の虫退治が先決だ。それにこちらの方が費用も安いと知る。
検査員はシロアリのおそろしさを何度も口にして、引き揚げていった。
ムカデ退治の描写は迫力があり、圧巻である。「ムカデの怖さ」が一点に絞り込まれており、求心力がある作品である。
奧田和美 運命の出会い
娘がヘアメイクとしてフリーになった。名刺を作り、一人でCM制作会社に営業に行き、仕事をもらう身になった。「私」たちの自宅は神奈川県川崎市で、交通の便が良いところにある。娘は「川崎市」が気に入らず、都内に事務所を探しはじめた。
最初は代々木上原駅から徒歩6分の物件だった。山小屋風のアパートで、道路から建物までの景観はとてもよかった。家賃9万円で「更新料なし」が気に入り、『運命の出会い』だと娘は思ったそうだ。
一階の奥の部屋で、日当たりが悪くて暗い。事務所だから日当たりは関係ない。友人知人の意見から、「ここはやめた」と娘は見切りをつけたという。パソコン検索や、お気に入りの駅のまわりを歩き回り、何軒もあたったようだ。
私は亡母の墓参りをした。そして、娘と原宿で落ち合った。「少し時間があったので街を歩いていたら、良い部屋を見つけた。墓参りをしたから、お祖母ちゃんが見つけてくれたんだね」という。またしても、『運命の出会い』だという。八十歳ぐらいの大家が、隣に住んでいるので、すぐに室内中を見せてもらうことができたそうだ。大家はおじさんで、広告の部屋の他に、隣の部屋も鍵をあけて見せてくれたという。家賃14万円。娘はこの物件が気に入ったようだ。
私は家賃が高すぎると思った。娘の収入は決まっていない。家賃は毎月必ず出て行く。「私」は娘に同行し、物件を見に行った。大家は、母親の私にはなにかと冷たかった。
「ここの大家は留守中に鍵を開けるかもしれない」
私は娘の『運命の出会い』を崩した。
娘はまた何件も当たり、千駄ヶ谷に見つけてきた。娘は『運命の出会い』を感じたそうだ。小さな部屋だが、角部屋で窓が多く、狭く感じない。4階建の2階。明るく風通しもよい。ここなら一人で切り盛りできる。家賃八万円+消費税。これならやっていけそうだという。
母が、娘の住まい探しをあたたかい目でみている。娘の口癖『運命の出会い』が一過性だという、ユーモラスな作品だ。
濱崎洋光 母親と牛のなま首
6月のマレーシアは熱帯ムードがみなぎり、結婚式の多い季節である。「私」がマレーシアに赴任した翌年6月に、現地人のAさんから、「妹の結婚式に来ませんか」と招かれた。
Aさんは50歳に近い。妹の結婚式? 娘の間違いでは、と思った。私にはどちらでも良かった。よそ者の私を身内の祝い事に招いてくれた。仲間として迎え入れてくれた、その証と思えて嬉しかった。
結婚式の場所はカンポン(村)である。そこは海沿いに広がる、ヤシ林の中に伝統的な高床式の家が点在する、マレーシア古来の集落だ。Aさんの実家は村長(むらおさ)の居宅らしい、ひときわ大きな家だった。
私がお祝いを述べ、祝儀袋を手渡すと、Aさんは「有難う」といって、無造作にズボンのポケットに入れてしまった。
男女別に設けられた天幕で、昼食が振舞われた。アルコール類はまったくない。食後は家の中を案内された。裏庭が炊事場で、大勢の手伝いで賑う。
ヤシの実の殻が燃料だった。近くには牛のなま首が3個飾られていた。それにはぎょっとさせられた。
新郎新婦が雛壇に着席し、簡単な儀式が行われた。続いて、縁者の家族たちによる祝福。記念写真が撮られる。Aさんが家族を紹介してくれた。弟妹が多いので、数を聞くと、14人の兄弟姉妹という。
翌朝、会社での雑談で、
「Aさんの弟妹が多かったのには驚いたよ」
「母親は何人いましたか?」
一瞬、私は考えた。
ここはイスラム圏の国で、一夫多妻が認められているから、弟妹が多かったのだ。牛のなま首の数がその家の財力、社会的地位を示す。「母親と牛のなま首」の数が、その家のステータスになっていると知った。
異国の結婚式が上手に紹介された作品である。作者の驚きが、そのまま読者を巻き込み、ラストまで引っ張っている。
筒井隆一 師匠との四十年
「私」はフルートのレッスンに、師匠の家に出むいた。師弟関係は40年近い歳月が経つ。練習不足で、気が重い。家に上がると、前の生徒がレッスンしていた。私は終るまで2、30分間待ちながら、練習不足の言い訳を考えていた。
他方で、師との出会いをさかのぼっていた。
私は大学で土木工学を学び、ゼネコンに入社。いきなり北海道支店の配属が命じられた。赴任まえに、芸大の女子学生に、
「山奥の現場に行ったら寂しくなるから、何か楽器でもやるかな。フルートなんかどうだろう・・・・」
と相談を持ちかけた。彼女は楽理科だった。そこで教養課程が一緒だったフルート専攻の女性を紹介してくれた。紹介後から4年経って、北海道から東京に戻ってきた。それから正式に習いはじめた。
仕事も遊びも忙しい中、フルートを生涯学習の核にしようと、懸命に練習してきた。練習の機会が多ければ、それなりに上達する。そうなればやる気が出て、また吹きたくなる。
フルートの先生はレッスンの基本方針は、「豊かな音色で、聴く人の心を打つ演奏をせよ」というもの。単純明快だが、極めるには奥が深く、難しい。生涯学習に相応しいテーマを与えられたと、私はいつも思う。
先生は、生徒の長所を伸ばし、短所をカバーする、という指導バランスが当を得ている。
40年も経つと、師弟関係は円熟期に入るらしく、最近のレッスンは世間話で始まる。笛に関係ない話題が多い。レッスンに入ると、私が今後もよい音色を保ち、末長く笛を吹き続けるには、どのような練習をしていけばよいか、という話題が中心になる。
肺活量や筋力は残念ながら着実に低下している。それらの対策として、正しい姿勢、横隔膜の拡大、腹筋の強化などの指導を受ける。
師匠からは、まだ吹いていない名曲に取り組むことも勧められる。優しく大きな心で弟子を指導して頂ける。
レッスンは厳しい。緊張と反省の連続で、終わるとガックリくる。そのあとは居酒屋に直行し、私は独りで、ストレスを解消している。
40年間、大好きなフルートを通じ、弟子で居られることの素晴らしさ。それが心理描写を中心に展開されている。良い師弟関係が貫かれた、読み手には快い作品だ。