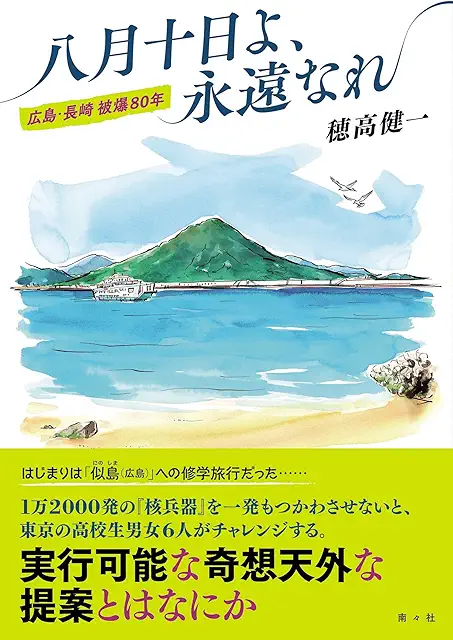第27回 『元気100エッセイ教室』作品紹介
エッセイは日常の出来事を書く、歩んできた記録を書き残す。この二つが最も多いだろう。今回のレクチャーでは、この二つについて述べた。
「日常生活の一こま」や「身辺の小さな出来事」を素材に取上げ、読者を感動させたり、印象深い作品としたりする。それには素材の切り口が大切だ。
常識の目で見、常識的な書き方は、読み手には退屈な作品になる。素材(対象)をやや斜(はす)から見たりすると、切り口がシャープで、新たな見方、新しい考え方の作品がうまれてくるものだ。つまり、些事な素材でも、読者にはおどろきやショックや感動などを与える作品になる。
今回の提出作品から、素材の切り口や、その処し方などを中心にみていきたい。
奧田 和美「赤ちゃんの名前」はタイトルからも日常的な素材だ。
『どの子の名前も、親または祖父母が一生懸命考えてつけるのだろう。うちの娘も「新菜(にいな)」という。新春に菜の花の咲くころ生まれたから。初孫の名前も可愛い。「小妃那(こはな)」だ。息子が姓名判断の本を読んで、字画や読み方を選び抜いてつけたそうだ。次の子は男の子で名前は「耀允(かいん)」。真実・誠を表しているという。こうした名まえも、エッセイ作品の素材になるのだ。
長谷川 正夫「三郎戯歌」(さぶろうざれうた)が、切り口として驚かされる。
『「私」は犬が大好きで、中年になってから4匹ほど飼った。皆オスの柴犬で、名前は4匹とも三郎と名づけた。4匹めの三郎は不思議なことに人語を解し、特に戯歌に興味をもっていた。数首を取り出し、往年の三郎を偲んでみることとした。』
東海の小島の磯の白砂に
われ泣きぬれて蟹とたはむる 石川 啄木
世田谷の小庭の中の片隅に
われ寝ころびて枯れ葉とたはむる 三 郎
白鳥は哀しからずや空の青
海のあをにも染まずただよふ 若山 牧水
わが宿は楽しからずや世の憂ひ
けがれ水にも染まずくつろぐ 三 郎
函館の青柳町こそかなしけれ
友の恋歌矢ぐるまの花 石川 啄木
世田谷の松原町こそたのしけれ
友の吠え声紅梅の花 三 郎
こうした戯歌が連続する。ユーモアやウエットや機知が豊かに盛り込まれている。読みながら、くすっと笑う。作者には知力でねじり伏せられた。
中澤 映子「再び、エリザベスに 動物歳時記その17」は、素材自体が切り口の良さになっている。
作者は得意とする擬人法を使う。主人公は3本脚の犬である。耳の病気の「線維上皮性ポリープ」という犬の病状が、「犬の語り」で説明される。
『耳道内の腫瘤(子供の指先位ある瘤のようなもの)をとる手術を受けたの。麻酔をかけられたので、痛さは感じなかったけどね。麻酔が切れて、術後、3時間くらいしてご主人が迎えにきてくれた時は、すでに大きなブルーのエリザベス・カラーが、わたしの首についていた』それはスタンドの傘のようなもの。『うっとおしいし、行動はせばめられるし、まるで拷問を受けているみたいなの。昔、罪人が首に板をかませられて、市中をひきまわされた格好に似ている、何もわたしは悪いことなんかしていないのに』と犬の心理描写が切り口を鋭くしている。
和田 譲次「背が縮んだ」は病院の入院時におこなう患者の身体計測の描写から入る。長年172・5センチだと思い込んでいたが、2センチも低かったのだ。
『整形外科の医師に聞いたところ、歳と共に骨密度が薄くなり骨量が減るという。そのために骨折もしやすく、身長にも影響をおよぼすらしい。50代からは老化が始まり、20年間で男性の場合1%ぐらい背が縮む。(女性の方が縮む率が高い)そのうえ姿勢が悪くなり前かがみになり、骨も曲がってくる人も多いようだ』と情報提供が、加齢に対する怖さを募らせていく。
『老化現象は足腰が弱くなる、聴力、視力が弱くなる、歯がもろくなるなど、個人差はあるが体のあちこちにその症状が現れる。骨の場合は進行もきわめて遅く、症状としても、他の老化と比べて自分では、日常生活上、気がつかない。』と身長も、大切なバロメーターだと教えてくれる。
濱崎 洋光「人情に国境なし」は、貴重な海外で病気になった体験エッセイだ。「身辺の小さな出来事」でも、それが海外となると、強い緊迫感となる。
マレーシア生活も半年が過ぎた年の暮れだった。ある日、朝から高熱に襲われたのだ。『夕食後になると、冷房を止めても、日本の寒中に屋外へ裸で出たような酷い寒さに襲われた。家主の紹介で約60キロ離れた病院に出むいた。夜の10時を過ぎていた。
『急患窓口の医師の簡単な診断で、即入院となる。『入院保証金として約10万円を請求された。所持金は無く困惑。5万円もあれば一ヶ月の生活が十分に出来る国なので、普段は大金を持ち歩かない』とたんに苦境に陥る。クレジットカードで切り抜けた。
『翌朝、二人の看護婦が採血に来た。一人が私の右腕をゴムひもで締め、注射針を静脈に刺そうするが、手元が震えている。先輩格の看護婦が、なにやらマレー語で指導している。恐ろしさで此方の心臓が震えた』という。医療の底流にはヒューマニティーが流れているのだが、ことばが満足に通じないので、治療一つにも恐ろしさにつながるのだ。
中村 誠「銀杏のいろいろ」は、エッセイのなかに自作の俳句を組み込む。韻文(俳句、短歌など)を持ち込むと、それが重層化し、作品に奥行きがでる。
『先月の句会から一ヶ月も経ったのに、自由句が一つも出来ておらず、午後の句会を思うと気が重い』、という心理から書き出す。『1時間の車中で何とか一句作ろうと、そのまま家を出ると、裏山に上がる石段のたもとに、二本の銀杏の木がある。すっかり葉を落としていた』。
『大船より乗った横須賀線の車中で、手帳を取り出した。携帯辞書を片手に句作に試行錯誤をくり返す。保土ヶ谷駅をすぎると、国道には銀杏の木々が目一杯の陽をあびており、黄金色でまだ葉が落ちていない』
句会の場所は新橋学習センターで、元桜田小学校の教室。校庭には銀杏の樹がある。まだほんの一部しか黄葉していない。
《 木の葉落ち凛と天さす銀杏かな 》 誠人
『句会は54回目の皆勤を続けているが、いの第一番目に「天賞」を貰ったのは今回初めて』と喜びに展開していく。気象条件の差異よる黄葉の違い。それに俳句を重ねることで、描写に厚みをつけている。
山下 昌子「もういっかい、もういっかい」は、植物と小鳥と、観察力のある描写文だ。
『ピラカンサは、毎年枝がたわむほど真っ赤な実を付けるのに、今年は少ない。去年、枝を掃う時期が悪かったのかもしれない。餌の少なくなる頃に赤い実をつけるピラカンサは、小鳥たちのご馳走だ。ピイピイ、チチチ、ギーギー幾つもの鳴き声が葉陰から聞こえる。その食欲は旺盛で、2、3日もすると鳥たちの声がパタリと聞こえなくなり、窓から見上げると赤い実は一粒残らずなくなっている』と庭の描写から、室内へと運んでいくのだ。そのうえで、主婦が料理と時間と向き合う姿が克明に書かれている。
高原 真「人生の一里塚」は、年行事から読者を誘い込み、関連情報を提供する。正月を素材にして、一里塚の知識を提供している。
『むかしの元旦は、一つ歳をとるという数え年の慣習で、全員の誕生日だった。元旦は、私にとって「人生の一里塚」で、近づくと「門松や冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」と一休が詠んだ歌が反射的に思い出される。』
一里塚は旅程のメヤスとして作られた。東海道は、家光の時代になって整備されたといわれる。「標識としての「一里塚」に植える木を何にするか、ということが問題であった。将軍の意向を訊ねる土井利勝だ、既に齢を召している。家光が「松の中に松では目立つまい。余の木にせよ」と言った。「余の木、つまり他の木にせよ」という意味である。
『利勝は耳が遠かったので「ははっ、『榎の木』とは妙案。松の中で直ぐ目立ちまするし、夏は青々と茂り、くまたなく日陰を作りまする。冬はことごとく葉が枯れ落ちて陽の光が差し込みまするため、旅人の休息にもよく、重ね重ね結構」と、「祝着」で終わった。「余の木」の聞き間違えが「榎の木」となった』という史実(一説)の挿入が効果を発揮させている。
二上 薆「あの戦争は何だったのだろうか ―ある読書子の感想より―」は、作者の戦争史観がベースになった書評だ。過去からの定説に、疑問を投げかけてみる。そう信じ込んでいた、常識をくつがえしてみる。すると、真実の一端が見えてきたりする。それを書評で展開している。
『あの戦争、日本の侵略との断定は間違っている、と言った田母上空幕長の論文事件(十一月三、四日新聞ニュース)、マスコミが、わっと取り上げ、忽ちすーっと消えた。大東亜戦争(太平洋戦争ではなくて)、日本にも一理あり、と正当性を匂わせる発言には、全て口を覆い疎外する、この国の現在の風潮。特に明治はよかった、それに比べて戦前の昭和は暗黒、と近年、定着したような史観がある(自虐史観、司馬史観ともいう)』
『外交の一つの手段として、といわれる戦争、周りの環境を考えなくて、一国の勝手としての戦争は考えられない。また、勝った国が正義で、負けた国が全て悪だということはあり得ない。勝った国にも間違いはあるし、負けた国にも主張や言い分はある』と公平感が打ち出される。
『太平洋戦争の視点を限定すれば、日本・米英・中国の三つ巴の闘争。日本は防共と東亜経済圏の確立、英国はアジアの既存権益の確保、米国にとっては中国の門戸開放、蒋介石にとっては中国本土統一と共産党撲滅が目的であった。結果は日本の敗戦、英国は植民地の全てを失い、米国は共産党の統一で門戸開放の夢を断たれ、蒋介石は共産党に本土から追い出されてしまった』と導く。戦争を知る世代が少なくなった。あらためて、太平洋戦争とは何であったか、と問うのだ。
青山 貴文「集う友 ハワイアンバンドの結成(三)」は、シニア層に一つの生き方を示している。戦争を前後して生まれた世代で猛烈に働き、余暇の過ごし方を知らないうちにリタイアした。年金生活に入っても、趣味の世界か、ボランティア活動か。いつまでも迷い、やるべきことが定まらない人にはヒントにもなる。
かつての勤務先の同期会が、石川県の温泉旅館で開かれた。15人ほどが出席した。N君は卓越したギターで、「私」はウクレレで伴奏し、数曲を歌った。
『N君のギターは学生時代から衆目の一致するところ。退職後は油絵とオペラを演ずる多才な人だ。ところが、会場では私のウクレレの方が皆の興味を引いた。音楽とは無縁に見える私が、楽器を弾いたからである』。
同期会の多くが年金生活者になり、これから何をしようかと迷っていた。「私」はかれらに向かって、「ウクレレは、ギターより小さく持ち運びが楽である。指先を動かすので、脳の働きを増長する。よって、われわれの年代には最適の楽器である」と一席ぶった。すると、「青山が出来るなら、俺にもできる」と興味を持ったのだ。
これを発端に、バンド結成まで、いろいろな人物が集ってくる。その群像をていねいに描いている。
上田 恭子「双子プラス・ワン」はタイトルで興味を引く。タイトル上手な作者は、それも切り口の良さの一つになる。
『「お姉さんのところ、双子だったのよ。悪いけれど、用意した産着とおむつを持って来てくれない?」母のあわてた電話の声にびっくりする』それは昭和29年10月で、物資不足の貧しい敗戦後の生活だったころだ。
『初産の私は産まれてくる子にはさらしの白いおむつをしてやりたいと、ミシンを踏んで縫っていた。本を見て産着も縫った。我ながら可愛い産着が出来たと喜んでいた』ところが、姉の三人目が双子だったのので、「私」はわが子のために作ったはずのむつを届けに行った。
家に帰ってから、また始めからやり直しの産着縫いが始まるのだ。
藤田 賢吾「哲ちゃんの技―手造りの戸棚―」は歩んできた道を振り返り、強く印象に残るものを取上げる。記録エッセイとは、より事実にそって、実体験で書き残すもの。
『札幌から磯子に住むようになった当時、食器棚の上と天井との間に棚を作った。幅は1メートル以上、高さは約30センチの大きさだ。本体は普通の板、扉は軽いベニアを使う。ノミで、枠に溝を彫ってはめ込む手法だ。完成するまで一ヶ月以上もかかってしまった』という思い出の上置き戸棚だった。
『大工作業は、殆どは哲ちゃんから学んだ。哲ちゃんは12歳上の二番目の兄だ。教わった技は、数え切れない。のこぎりやノミの使い方、カンナで板を削る方法、糸鋸で丸く切るやり方、カンナの刃の研ぎ方などだ』哲ちゃんは、工業高校を卒業した。学校で学んだ細工や技術をいろいろとやって見せるので、幼いボクにとっては何だか魔術師に思えた。
『捨てようとした戸棚には、哲ちゃんから伝授された技が詰まっている。どうしても捨てることは出来ず、ベランダで縦に置いて再利用。戸棚の上から紫色の花が、弦を伝って滝のように流れる風情となり、花好きの妻を喜ばせている』と現在に戻っている。
吉田 年男「桑の木」は、小学生の記憶にある、一つの観察記録の思い出。それを記して残すものだ。
『わが家から徒歩五分の公園は、蚕糸試験場の跡地だ。一周700百メートルのジョギングコースもあり、約一万坪の広さだ。「明治四十四年 蚕糸科学技術発祥の地」という石碑が門扉の近くに立っている』。
試験場は20数年前に筑波学園都市へ移った。公園には何種類かの「桑の木」が今でも残っている。桑は和紙の原料になる「コウゾ」、観葉植物の「ゴム」、クワ科の「ヤマグワ」などがある。
「桑の木」を眺めていると、小学2年の時の、貴重な体験を思い出した。『試験場は、高い塀で囲まれていた。好奇心の高まりから、塀の壊れた小さな隙間から敷地の中へもぐりこんだ。そこには「桑の木」が沢山植えられていた。木造平屋の試験室が何棟もならんでいる。建物の外には生きている蚕が積み重なっていた。蚕の動く様子が、なんだか気味が悪かった。』
「私」は元気のよさそうな蚕を、何匹か恐る恐る箸でつまんで、桑の葉と一緒に家へ持ち帰ってきた。蚕は、桑の葉をカサカサとおおきな音を立てて食べていた。瞬く間に大きくなった』と蚕の観察が展開されるのだ。それは学校の実験などでは、味わえない貴重な体験だった。