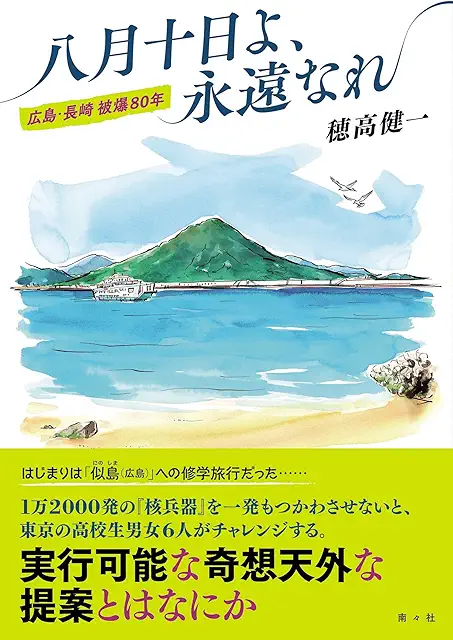第12回『元気100エッセイ教室』作品紹介
受講生にはつね日頃から、『隠したいこと』『言いにくいこと』『過去にしゃべったことのない失敗』などを書いて欲しい、といっている。自慢話は日経新聞の『社長の履歴書』に任せればよいのだから。もう一つ、孫の話は避けて欲しい、と。
最近、あることに気づいた。受講生どうしが酒席で、旧知のように語り合っているのだ。
提出するエッセイは本音で、自分の心を裸にし、恥部に触れるところまで書けるようになってきた。失敗談ほど、講師や仲間から高い批評を受ける。良い作品だと言われる。とりもなおさず、それは作品を通して、筆者の人間性を知ることになる。
もしも自慢話、鼻持ちならない話題、過去の出世物語などだったら、面白くない相手になってしまうはずだ。
相手の人間性を知れば、『胸襟を開いて語れる』、相手の考え方を知れば、『警戒心を取り払って語れる』という交友関係につながってくるようだ。
60歳過ぎて、相手の腹を探ることなく語れる。そこには新たな人間関係が生まれる。学生時代以来ではなかろうか。
今回の作品批評も、自分の恥部をさらけ出したり、心をのぞき見たり、諸々の失敗が盛りだくさん。読み手には興味深い作品ばかりだ。
中 村 誠 思い出の四十年前、一九六七年
1961年、23歳から商社の社会人生活がはじまった。商社マンならば5、6年も経てば、海外出張とか、海外駐在とかを経験したくなる。そのチャンスが来たのだ。
67年夏、28歳のときに単独で、豪州シドニーからパプアニューギニア、シンガポール、マレイシアをまわりフィリッピンのマニラ店を訪ねた。全行程は3週間の強行だった。
『初めて飛行機にのったのが、前年春の関西への新婚旅行だった。今回は外国の航空機の旅で全てが初チャレンジだ』。英語は得意ではないが嫌いでもない、要するに流暢にこなせないのが実力だという。
シドニーに向かう機内で、水割りを頼んだ。スチューワデスから「支払いは何でするのか」と聞かれた。意味が解らなかった。彼女が米ドル紙幣と豪州ドルを見せて「どっちだ?」と首を傾げた。納得。貴重な米ドルを払った。
1ドルが360円時代。現金100ドルと旅行小切手400ドルだけだ。これで21日間のやり繰りだ。
シドニーから南洋の僻地であるポートモレスビーに着いた。だが、出迎え無し。黒人ばかり。ホテルに入ったが、エアコンなどはなく、天井の大きな扇風機がゆっくりと回る。
夕食後は一人で町中に出た。街灯はなく、薄暗い町角に立っている黒人たちにギョットされられた、という。孤独感と不安感が描写されている。
会社を訪ねた時に、相手の豪州訛りの英語と、私の英語の発音が異質でお互い困った。翌日の商談日には、2人の白人と、1人の日本婦人がいた。彼女は戦争花嫁でオーストラリア人と結婚しており、通訳だった。『おぼつかない英語を話した私との打合せをうまく進めるために、通訳を頼んだのだ』という。
商談のなかで、買主のオーストラリア人に納得して貰えないのが、英ポンド切り下げだ。大英帝国時代からの強い通貨ポンドの切り下げなど、想像もしたくないのだ。
『英連邦の一つである豪州人には当然かもしれない。商売の分からない通訳の婦人と、語学が不十分な私との二人三脚の商談は何とか乗り切れた』。オーストラリア人はやっと「私」の言い分、切り下げの場合には、契約価格の値上げを納得してくれたのだ。
ニューギニアでの苦労を終え、週末には豪州ブリスベンに向かった。翌朝の新聞は、『ポンド切り下げが断行された』と報じていた。『思わず辞書を持ち出し『切り下げ』の単語を再確認した。間違いなかった』という。
その後、予定通りの日程で帰国した。21日間の冷や汗の出張だった。
前半は、熱帯の情景のなかに、「私」の身をおく。穏やかな異国情緒が描写されている。
拙い英語の会話の商談から、緊迫感が高まっていく。大英帝国のポンド切下げの条件付きの要求がかろうじて通った。
直後、世界経済に大きな反響をもたらした『ポンド切り下げ』が起きたのだ。強いインパクトで盛り上がる作品だ。
作者が自分自身を客観的に見ている。手柄話ではなく、外国の孤独感の心情がすなおに書けているから、好感が持てる作品に仕上がっている。
長谷川 正夫 沖縄慰霊の旅
第二次世界大戦の末期、昭和20年6月13日、米軍の猛攻撃を受けて、陸軍と海軍の司令官が2人して自決した。
戦後、この日を「沖縄慰霊の日」と定めた。そして、軍人、住民合計19万人の戦没者の慰霊が行なわれている。「私」は毎年6月になると、沖縄慰霊の日に思いをよせている。
平成5年には沖縄の「ひめゆり平和祈念資料館」と「旧海軍司令部壕」を訪れた。『ひめゆり資料館に足を踏み入れた途端に、思わず息をのんだ。真っ暗に近い部屋の中央に、戦没ひめゆり隊二百余名の遺影だけが、淡い照明に照らされ浮かびあがっていた。二列に整然と並んでいる写真をみていると、鬼気迫るものを感じて足が進まない』と無駄なことばが一つもない情景と、複雑な心象を重ね合わせている。
『年齢は皆、十代後半。写真の半分は皆嬉しそうに笑っているのが、哀れを誘う』。この生徒たちは、平和なときに育っていれば、南国の陽光をあびて青春を謳歌していた筈だという思いを持つ。米軍猛攻撃の第一線にいた運命とはいえ、不憫で「私」は胸が熱くなってしばらく動くことが出来なくなったという。
つづいて、旧海軍司令部壕に向かった。司令官や幕僚たちが自決した地下壕である。『手榴弾の破片の痕がいくつも残っている部屋があった。自決のために手榴弾を爆発させたのだ。これらの破片で幕僚たちの体が四散したと思うと背筋が寒くなってくる』と心情を描く。『よく見ると人の名前だ。修学旅行でここを訪れた生徒が落書き気分で書いたに違いない。これはひどい」。心ない仕業を目の前にして、「私」はただ腹が立つのみ。作者の怒りは共有できる。
観察力が優れ、細かいところまで書かれている。作品は大袈裟なことばもなく、素直に感じたまま、思うままに表現されている。それゆえに歴史の重み、人命の重みが伝わってくる。
山下 昌子 女の生き方を求めて (二)
1956年のころ、高校卒業後は成績優秀な人でも、当たり前のように銀行などに就職していた。父親が結核で病死とか、戦死とかの母子家庭が多かった背景もある。
母は「女子は四年制大学を出ると、婚期が遅れる、短大が良いという意見。日ごろ何も言わない父が四年制大学を薦めた。父親のことばで、「私」は目覚めた。
好きな国文科を選ぶのが自然だが、英語の時代だと思って、英米文学科を選んだ。前橋市に住んでいたことから、寮のある女子大学を受験した。
しかし、寮生活の夢は消えた。東京には家があり、都立高校に通う弟と自宅に住むことになった。『これが幸いだったことが入学してみて分かった。6畳1間に3人から4人の学生が住み、門限は午後5時、外出日も週1回』と厳しいルール。親が届けた人のみ、文通が許される。
新宿御苑で、寮生が出会った男子学生から写真が寮に送られてきた。寮生は呼び出され、手紙は寮監に開封された。これが朝日新聞に報じられ手紙開封事件となったという。
英米文学科生は40人余りで、途中で10人ほどが辞めていた。カリキュラムには選択の余地がない。詰め込み授業だ。
「私」のクラスは、自主的な文集を発行したり、英語劇を上演したりした。三年生のとき、大学祭を学生企画で実施するために、自治会を作りたい、と大学当局に申し出た。それが大きな問題になった。そのうえ、署名活動が知れて、学長に呼び出された。リーダー2名は1週間の停学、あと5名は戒告処分を受けた。クラス全員の血判書も「学籍簿に記録するので、結婚にさしつかえる」という脅し文句によって粉々にされた。
それだけで収まらなかったのだ。卒業前にして、スポーツと学業の両方で評価された賞が急に取り消しになった。そのうえ、3年生の停学を理由に、卒業そのものが延期にされたのだ。『反省文を書いたら卒業証書を渡す』と学校当局は要求してきたのだ。
「私」は卒業証書なんて要らないと思った。母は、教員資格もあるのだから、卒業証書を貰っておきなさい」という。父は「自分の信念が間違っていなかったと思うのなら、私が悪かったと書く必要はない。大学の意に沿わなかったのは残念である、と書けばよい」と言ってくれた。
私は思慮した結果、将来のことを考え、卒業証書は受け取ることにした。反省文を書いた。冷静を装い卒業証書を手にして、校門を出た。母と二人で、ほっとしたが悔し涙が流れた。
女子大時代の停学処分。稀有な体験がテーマと緊迫感を持って貫かれている。他方で、両親の考えの対比が、作品を盛り上げている。
二上 薆 日本の航空、栄光と挫折 自分史のよすがに
東京大空襲で、自宅が焼け落ちた。書籍の灰の白さと、赤いブリキ製の小さな飛行機の玩具だけが眼に残っていた。書き出しの描写とリード文としての役目がはたされている作品だ。
赤い飛行機は、昭和2年5月、ニューヨーク・パリ、大西洋単独無着陸飛行に成功した、チャールズ・リンドバーグを記念したものだった。
明治36年2月17日、米国ライト兄弟が人類初の飛行したとされている。日本人の二宮忠八がそれより12年も前に、模型ながら空飛ぶ器械を発明実験に成功した、と世間の通説を覆す。
『空翔ることは自然の冒涜か、リンドバークもライトも後半生は必ずしも幸福ではなかったといわれている』
昭和12年、飯沼正明操縦士と塚越賢爾機関士が、朝日新聞社の神風号に乗務し、東京からロンドンの亜欧連絡飛行を94時間で飛び、100時間以内の飛行に初めて成功した二人であった。そして、明治神宮外苑で、報告祝賀の会が行われた。しかし、支那事変で二人とも非業の死を遂げた。
敗戦後間もなく、羽田飛行場までサイクリングした。飛行場と境界の金網から格納庫の巨大な飛行機をみた。それは昭和13年5月、平塚→木更津→銚子→太田の上空を周回飛行して、長距離世界記録を打ち立て、航空研究所の長距離試験飛行機だった。戦後進駐したアメリカ軍から廃却された。「私」は航研機の最後の姿を見たのだ。
神風号と航研機の偉業は日本の飛行機製造技術だった。太平洋戦争の真珠湾攻撃、シンガポール沖開戦にはその威力は遺憾なく発揮された。
しかし、昭和17年6月のミッドウエー海戦の敗北から、わが国航空の栄光は生産力の弱小となった。
アメリカが日本上空の制空権を奪い、東京地区無差別爆撃。下町方面で10万の生命を奪い、建物27万戸を焼いた。
人類史上最大の悪逆残忍な行為・広島の原子爆弾投下も、テニアン島から飛来する航空機がなければ出来なかった。
『日本各都市無差別爆撃、原爆投下の発案実行者である米国の将軍、カーチス・ルメイに昭和39年、航空自衛隊育成に努力したという口実で、勲一等旭日大綬章を授けた』。時の内閣総理大臣は、後にノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作である。
『人類文明の大きな利器である飛行機は時に最悪の凶器と化す。自然に逆らうものは自ずと滅びるという』と結ぶ。
作者の目撃証言が、歴史的な記録と上手に溶け合っている。とくに作者の緻密な資料の掘り起しが、作品の骨格の太さになっている。昭和の航空史の貴重な生情報を与えてくれる、価値ある作品だ。
高原 眞 業務改善屋
愉快な夫婦ものエッセイだ。「私」は家事について女房と言い合いになることがある。
「洗い終わった茶碗や皿は、乾燥機に入れっぱなしにしないで、すぐ元の場所に納めよ、場所ふさぎだ」と言っても、家内はまったく実行しないのだ。「乾燥機からなら食べる時、最短距離ですぐ取り出せ、食卓に並べられる」という。
一事が万事。「私」の主張は受け入れられない。「じゃぁ、あなたヤリナサイょ」と最後通牒を突きつける。
「私」はかつて工場や事務所を対象とした「業務改善屋」の経験がある。工場でも事務所でも「能率の第一歩は整理整頓から」だと言ってきた。必要なものはすぐ取り出せるようにし、「捜す」というムダな時間はゼロに近づける工夫をすべきだ、と。
家庭の仕事も、その応用と見ると、妻のやることなすこと、目についてしかたがない。つい口うるさくなるのだ。
皿をしまうときも「先入れ先出し法」の応用が必要だ。女房は面倒だから、今ある皿の上に重ねる。「理論は馬耳東風」である。
食品も同様だ。買ってきて冷蔵庫の下段や奥のほうに入れてしまい、結局は腐らせて捨てる羽目になる。「在庫管理」の応用だから、調達期間や、買う回数を最小にするべきだ。理をまくしたてれば、妻の角が生えてくるのだ。
ところが、わが書斎は仕事が溜まり、床上には書類や雑物が積み重なる。だから、最近は家庭での「業務改善屋」を休業にしているのだという。結末は自分に批判を向ける。
着眼点の良い作品だ。男性と女性の本質的な違いが、うまく対比させ、浮かび上がらせている。論理の構築が実に面白い。度が過ぎたことを真剣にやると、そこにユーモアと滑稽さが生まれる。
石井志津夫(いしい しずお) 「虫がいい」こと考
書き出しは意表をついた作品だ。
『どうも日本人の体の中には、虫が棲んでいるらしい。しかし、どんな虫なのか、誰も見たものはいない。正体不明なのだが、とにかく身体の一定の場所にじっと潜んでいて、何かのはずみに不意に動き出す。体内の一定の場所といったが、そこがどこなのかはっきりしない』。この書き出しは、思わずのめり込んでしまう。
作者は丹念に事例を並べる。
人間は得体の知れない何ものかに左右されている。それを漠然と感じ取り、「虫」のように表象したという。
怒りがこみ上げてくると「虫の居所が悪い」となる。それらの怒りが収まらないときは、「腹の虫が収まらない」となるのだ。
相手をちらっとみただけで、「虫が好かない」と決め付けてしまう。体内の「虫」が怒りだし、特別な液を放出する。それが「虫唾」である。鋭い直観力が働けば、「虫の知らせ」となる。情緒が不安定な人間は「泣き虫」、「弱虫」と呼ぶ。なるほど、と納得させられる。
この先、虫の説明が続く。体内には、九つの虫が棲みつくようだ。短気の虫、弱気の虫、疝気(せんき)の虫、浮気の虫、悋気(りんき)の虫、疳(かん)の虫、ふさぎの虫、癪(しゃく)の虫と、一つのことに熱中する「仕事の虫、本の虫、芸の虫」はまだいいほうだ。
最近では、この他に、点取り虫、金食い虫、お邪魔虫、信号虫(無視)などなど、虫も殺さぬ顔をし、自分の都合だけで増殖している。
従来とは違った視点で、意外性がある作品だ。独創性と機知に富んだ、ユーモアがある作品だ。
たばこ仲間の縁 藤田 賢吾
JTがまだ専売公社の頃、『今日も元気だ タバコがうまい』という名キャッチフレーズがあった。確かに、喫煙者は体調不良になると、とたんにタバコの味が悪くなる。タバコの味は健康に敏感に反応する、バロメーターだ、と「私」は考えるのだ。
96歳で亡くなった母親は、20歳から76年間タバコを吸い続けていた。それだけでも驚きだ。
「私」も元気でいたいと、母に見習ってタバコをおいしく吸い続けている。禁煙をしようと思ったことは、これまで一度もないという。
アメリカ大陸横断のドライブ・インの体験に及ぶ。喫煙者は暗い部屋に案内された。一方「ノンスモーキング」の部屋は、ガラス張りのとても明るいところ。差別の大きさにビックリさせられた。
この旅行では五つの家族を訪問する。どの家庭でも、ご馳走はバーベキュー。タバコを吸う場所となると、庭とか、ベランダなどへ追いやられたという。
定年後、「私」は日本語教師の学校へ通いはじめた。休憩時間は喫煙者が外の非常階段の踊り場に集まる。顔ぶれはいつも同じ。世間話や個人的な会話が楽しめた。授業が終わり、帰りに一杯飲んで語り合うチャンスもできた。
1年半、420時間の授業を終えたとき、タバコ仲間から、米海軍基地で日本語教師の誘いがあった。受け入れた。それが現在もつづいている。喫煙者は冷遇されるが、メリットもあるようだ。
『タバコ』というシンプルな素材で、貴重な体験を数多く盛り込んだ、運びのうまい。同時に、喫煙者なりの言い分に対しても、説得力がある作品だ。
吉田 年男 木 刀
高校時代の仲間と車で、箱根に気楽な旅をした。旧東海道の甘酒茶屋に立ち寄った。店頭の傘たてのような籠には、数本の木刀が立てかけてあった。値札がついている。
『手にとると、なんとも言えない重量感があり、迷わず買ってしまった。ひごろから、欲しいものの一つであった』と心象が描かれている。
木刀は「切れない刀」として、直心流剣術の達人の榊原健吉が、明治9年の廃刀令の後、「倭杖」として考案したものだという。帯刀を禁じられた武士が、刀剣かわりに持ち歩いていた。
現代では、講道館護身術のなかでも使われている。「私」が柔道をはじめたころに講道館でみた。闘争に備えて技芸を磨く武道とか、礼を重んじる、汗臭い柔道などはあまり人気がない。
他方で、仕事帰りのサラリーマンが駅前フィットネスクラブで、高いお金を払って汗を流している。
スポーツの種類も多種多様だが、『いつでも誰でもが、気楽に参加して楽しめる、見た目のよいスポーツが、もてはやされている』と世相を嘆く。
「私」は忘れかけている日本人の古来の精神を、いま一度復活させたいと、木刀に思いを込めて、朝の運動に素振りを加えた。
山本有三の戯曲「米百俵」にでてくる、「刀にかけて物申す」といえば、駆け引きのない、真剣にものごとを訴えていることと、理屈抜きに了解された精神だと紹介する。
この引用は作品の説得力を高めている。
日本人はいまや合理性という理屈のみが先行する時代になってしまったという批判も、素直に受け入れやすい作品だ。
上田恭子 母への詫び状
昭和38年に免許をとった。運転免許証の更新の年だった。車中に置きぱなしの、免許証入れから、免許証を出したら、お守りの入った手縫いの袋が出てきた。可愛い羽裏のはぎれで、母が縫って渡してくれたものだ。
大阪に単身赴任している夫のところに、留守宅の家族全員で、車で遊びに行くことになった。母親が安全を願って、「川崎大師」から貰ったお守りだった。
当時は、女性ドライバーは少なく、トラックに追いかけられたりしながら、600キロほどを食事休みくらいで走りぬいた。東京・大阪のドライブの情景が克明に描かれている。
免許を取った当時は、お守りで安全を願う母親の気持ちが汲み取れなかった。いまや実母の年齢に達した。「私」はお守りを凝視し、実母の気持ちを汲み取った。
『免許証いれの中で四十年近くを事故に会わないように守ってくれている。その袋をにぎりしめると、しみじみと暖かな思いに触れて、鼻の奥の方がじーんとしてくるのだった』と結ぶ。
「お守り」という小道具が、精神的な母子のつながりの再認識を支えている。作者がいちばん書きたいこと、「親子の見えない糸」というテーマがしっかり貫かれた作品だ。
森田多加子 ソ連への旅
1987年6月はゴルバチョフ政権の時代である。「私」を含めた『ロシア文学を読む会』の仲間が、モスクワのシェレメチェボ空港に着いた。ロビーは想像通り、薄暗くて、人もあまりいない。荷物検査はまったくなかった。
寝台急行列車でレニングラードに移動した。『駅を出ると、トーポリ(泥柳)の白い花が散って、まるで雪が降っているようだった。街では頭に大きなリボンをつけて、薄い色のワンピースで着飾った少女によく出合った』。ガイドの説明では、今が一番いい気候なので、精一杯のお洒落をしているのだという。
アパートの壁面は薄暗い色で、窓も開いていない。三つ並んだ窓にだけ花が飾ってあったのが、強烈な印象となった。
ドストエフスキーは12回も引越ししたらしい。1866年、メシチャンスカヤ通りの住居で『罪と罰』を書いた。主人公は屋根裏に住んでいた。「私」はそのアパートに行ってみた。『ラスコーリニコフはここから(いとわしい憂鬱な色彩)を感じたのか。陽の射さない通りに立って考えてみた。時代は違うのに、下町を歩いていると、その頃の様子がわかってくる。作品の一シーンが鮮やかに浮かんでくる』。
白夜の季節だ。夜になっても明るい。夕食は、添乗員の友だちの家に招かれた。食べ物の配給は少なく、貧しいと聞いていたが、ご馳走がずらりと並ぶ。理由は、闇市があり、裕福な人に不自由はないらしい。すべて国営のソ連において、この格差は何だろう、と疑問を憶えるのだ。
ソ連崩壊後、レニングラードはロシアのペテルスブルクという昔の呼び名に戻った。『マクドナルド』も入り、ハリウッド映画の宣伝ポスターまで貼っているようだ。
暗いアパートや、笑顔のない博物館の女性館長も明るくなっているかもしれない。となると、ゴーゴリから始まったロシア文学を感じるには、現在の街の表情からは少々戸惑いを覚えるのではないだろうか。
暗かったソ連はある意味で、ロシア文学の名作の実証ができる、よい機会だった。作者が訪れた、ソ連からロシアに変わる寸前はラストチャンスだった、という作者の思いが伝わってくる。
ロシア文学好き、『罪と罰』を読んだ人には、強い印象を与える作品だ。
濱崎洋光 常識とは
広々とした南シナ海を望むマレー半島東海岸。遥か水平線一杯に、白い入道雲が幾つも横一列に並ぶ。海、青空、朝日、砂浜、椰子の実と葉などの情景が克明に書かれている。
近海でイギリスが誇った戦艦「プリンスオブウエルス」が轟沈したと言う。
「私」は海岸近くに、5年間滞在した。家の四周が高い白壁に囲まれていた。リビングルームからは鉄格子から見える情景も、色鮮やかな花々や熱帯の植物など極彩色の風景だった。小動物が遊びに来る、自由な空間がある。
しかし、住む住人には窓と言う窓が鉄格子で厳重に塞がれている。檻の生活で、ストレスが溜まる。着任当初の連休に旅に出た。『窓に鍵をし、カーテンを閉めた。各部屋の電灯は全て消灯。四重の玄関ドアーの鍵を完全に掛け、門を出て、リモートコントロールのボタンを押して門扉を閉めて出た』。
帰宅すると、家主が飛んできた。留守中に窓ガラスが割られた。盗賊が侵入したかも知れないという。幸い、賊の侵入した様子はなく何も盗られた物はかった。
「外出する時には、要所を点灯、カーテンは少し開けて行くように」との家主の忠告を受けた。
日本人では、完全な戸締り、消灯、火の元の始末をして外出するのが常識であった。先輩にこの話しをしたら、この国では、「日本の常識は非常識と思えばよい」と言われたという。
情景描写の上手な作者だ。観察力も優れているし、豊富な色彩感覚の情景のなかに、読者を溶け込ませてくれる。他方で、防犯対策から、常識面におよび、国情の違いが書き込まれている。現地で海外生活が長い作者だけに、内容には説得力がある。
塩地 薫 新曲「青春」誕生
かつて3000人の会員がいた『青春の会』は宮澤次郎会長の急逝で平成12年3月に解散した。熱い思いを抱いた有志が集り、3年半後、『新青春の会』が再スタートで設立された。
近畿支部長だった、田端尚夫さんからファックスが送られてきた。それは自作「青春」の詩だった。「私」は、「新青春の会のホームページで発表し、作曲も募集したい」と書いて、ファックスを送り返した。
一ヵ月後、会議で上京した田端さんが「私」を訪ねてきた。そして、「西城秀樹に作曲を頼んだ」というのだ。そして、田畑さんはタクシーで羽田に向かった。
ところが、羽田に行くタクシーの中で、田畑さんは急性心不全で急死してしまった。
お通夜と葬儀の弔問者には、田端さんの「青春」と「心ころころ」という二編の詩が配られた。
年が明けて、田端さんの子息から電話が入った。父親が作曲を依頼した頃、西城秀樹は脳梗塞で倒れ、死を覚悟しての闘病中だった。医者からは回復まで最低二年はかかると言われていたらしい。そんな最中、田端さんの「青春」の詩を見たらしい。
西城秀樹は元気づけられ、楽譜があれば歌いたいと感じたようだという。
3年後、「私」は西城秀樹事務所を訪問した。応対に出たチーフ・プロデューサーのKさんは
「西城秀樹は、田端さんの『青春』の詩に励まされ、復活しました。平成16年9月、『あきらめない・脳梗塞からの挑戦』という手記を出しましたが、そこにもそう書いています。この詩をオリジナルだと思っていました」と語った。そして、著作権問題に触れた。「私」は問題ないと伝えた。
第5回総会で、新入会員紹介のとき、「今月、西城秀樹さんが入会しました」と事務局長が発表したのだ。
病に倒れた西城秀樹、作詞家の死。それらの接点が「私」の立場から描かれている。生と死と音楽(曲)という、重みが作品を底辺で支えている。
河西 和彦 賀田恭弘さんを悼む
5月16日、エッセイ教室で、中村誠さんから賀田さんの急逝が知らされた。
賀田さんのソニー入社はたしか昭和36年。「私」がニューヨークの駐在から帰任したとき、広報室に途中入社していた。
賀田さんは若々しく、仕事がずば抜けて良くできた。広報宣伝担当の活躍が認められ、数寄屋橋のソニービルのソニースクエアの展示を15年間、約500回担当した。「銀座の庭師」の異名を貰い、銀座の風物詩の事例に頻繁にマスコミに取り上げられていた。
80年の筑波の科学万博では、国際科学技術博覧会協会へ出向し、広報担当参事で活躍した。ソニーは「ジャンボトロン」という超巨大テレビを出品して話題をさらっていた。
ソニーに戻られた数カ月は、「私」と同じ職場となったが、賀田さんはやがて創業者・盛田昭夫さんの命で、牛場信彦記念財団に出向した。その後、井深大さんが理事長だったボーイスカウト日本連盟に移った。最近まで参与として三鷹の事務所に通っていた。
賀田さんの仕事は、人のやらない仕事、はじめての仕事が多かった。前例や引き継ぎがなかったことから、自分で情報を集め、知恵を出し、工夫してやるしかなかった。大変な苦労があったと思う。
会社以外の交友が役だっていた。そのほかにも、新聞・雑誌はもちろんのこと、図書館で資料を集めたり、美術館、画廊、百貨店の催事など見て回ったり、ヒントを得ては芋づる式発想で企画作りに展開させていた。
「企画作りは体力、気力、好奇心が必要」と賀田さんは説かれていた。
鹿児島から宣伝を頼まれて、「おたまじゃくしを十万匹集めて下さい」といったら「鹿児島名物は西郷さん、桜島大根、薩摩焼酎だ」と怒られたという。だが、何とか了解願って集めて貰った。いざ展示したら大評判。ビニール袋に3匹ずつ入れて、飼育法もつけて配ったら、子供が毎日長蛇の列。NHKのテレビドキュメンタリーにもなり、デパートも真似したりして、結果は鹿児島の人にも喜んで貰えた。卓越したアイデアマンの賀田さんの面目躍如たるものでした。
賀田さんはかっての典型的なソニーマンだった、という。故人の業績を褒め称える、哀悼の意をこめた良い作品である。作品としては、作者と故人との関わり、心情とがよく表現されている。