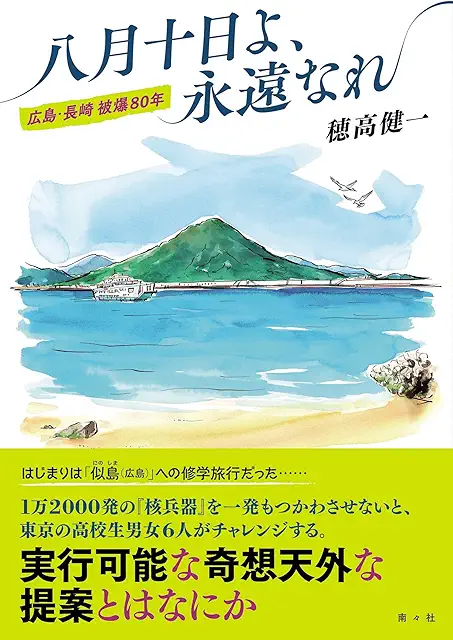花筏(はないかだ)・さきがけ文学賞・候補作品
※著作権付き小説。無断引用厳禁
娘の十三回忌を迎えた。寺の本堂に集まった参列者から、住職を待つ間、あれからもうそんなに経ったのね、早いものね、という話がごく自然にもちあがった。誘拐された10歳の娘が能登の山奥で殺された秋、新聞の大きな記事になっていたと、誰かれなしに語りはじめた。
親戚のものたちは遠慮がちながらも、事件を口にせずにはいられないらしい。
土岐(とき)駿一は殺された娘の梨香を想い、押し黙って聞いていた。かれの心のなかでは、事件は風化せず、きのうのことのように思えるのだった。殺される寸前、娘は雨の山中で泣き叫び、死に物狂いで抵抗したことだろう。梨香の悲痛な叫び声が未だに深夜ふいに耳もとで聞え、目覚めることもある。あの事件の記憶から決して逃げられない自分があった。
梨香の話題は長つづきせず、いつしか梨香とおなじ年のいとこの結納金へと話が移った。法要の席で、縁談の話題など場違いだと思うが、世間はそんなものだし、駿一はとがめる気など毛頭なかった。子どもを殺された怨念や心の奥深い痛みはそれに遭遇した実親でなければ、親戚筋でもわからないものらしい。
本堂の窓から雑木林越しにみる、能登の山並みが雲間の陽光を受け、緑の山肌を鮮明に浮かべていた。駿一は殺害現場となった山の方角を凝視し、梨香への想いを一段と強めた。
住職が現われると、まわりの者は正座となり、神妙な姿勢をとった。読経が一通り終ると、書院造りの広間で会席となった。
老いた肌に日焼けが残る猫背の寅吉が、駿一の横にやってきた。
「可奈子ちゃんが亡くなってから、何年になるかの?」
「女房のほうは来年、七回忌になる」
「もう、そんなになるのか、年が経つのは早いものじゃな」
「女房の法事もこの寺でやるから、来てやってください。寅吉さんにはいろいろ世話になっていたし、可奈子も喜ぶだろうから」
「案内があれば来るよ。ところで、おまえは何歳になった?」
48歳と答えた駿一は近ごろこの辺りが薄くなってきた、歳かな、ついつい隠したくなる、と前頭部をさりげなくみせた。
「まだ50前の若さじゃ。ところで一隻、造ってみないか。引渡しは観光客が能登にやってくる、来春のゴールデンウイークまえ」
寅吉が両手で、鑿(のみ)を打つ真似をした。
この元船頭は40年間ほど能登金剛の観光船の舵をにぎりつづけてきた。いまは息子の代を飛び越え、外孫がそれを引き継ぐ。運航する観光船は木造だが、船体にはプラスチックを巻く、五十人乗りのボート型である。
「いい話しだし、ありがたいけど、娘の事件からこっちは船大工のしごとをやめた」
駿一は寅吉にビールを注いだ。
「伝統的な木造船を造れる大工はこの界隈じゃ、もう駿一をおいて他にいない」
駿一は黙って聞いていた。
「……最近のお客は、金剛海岸の景色だけじゃ、満足せんようになった。福浦の観光船だから、能登の歴史を感じさせる、北前船に似せた船を造りたい。金剛のリアス式海岸を行き来する北前船は絵になるはずじゃ。もちろん外見は帆船だけど、エンジンは据える」
寅吉は70歳の年齢からくるものなのか、地場のものならば知り尽くす歴史の一端を語りはじめた。……福浦は奈良時代、福良(ふくら)の津と呼ばれ、日本海をへだてた渤(ぼっ)海国(かいこく)の使節を受け入れてきた、伝統のある港じゃ。渤海国がいつ滅んだのか、いつ交易は絶えたのか、わからないが、その後の歴史もいっぱいある。
この港は能登西海岸で、唯一の奥深い入り江じゃ。高波の影響がすくない天然の良港よ。この地形が幸し、江戸時代の福浦港は北前船の〈風待ち港〉として、蝦夷の松前から九州の筑前からやってくる帆船が寄航していた。
これらの船は北陸の特産や米などを上方の堺港まで運んでいたと語る。
「帆船に乗せた観光客に、こんなふうに歴史を説明すれば、興味が深まる。採算の問題があるから、50人は乗せたい」
「見た目の帆船なら、鋼船のほうがいい。観光地の湖に白鳥の船が走ってるように。鋼船なら、どこの造船所でも引き受けてくれる」
「味気ないことをいうな。北前船が鋼船だと、まやかしだと客に笑われる。杉の木目が光る帆船に客を乗せたい」
「鋼船に比べたら、木は腐るし、年月が経てば補修や修繕費がかかる」
「それを承知で、船大工の駿一に頼んでおるんじゃ。うちの観光船は代々、土岐造船所にたのんできた。よそに発注するのも面白くない。一隻造れば、よほどの事故で大破でもしないかぎり、15年や20年は持つ。この先、新船のしごとは出てこないぞ。能登杉のええ材料を使い、一隻造ったらどうじゃ」
「知ってのとおり、先の金剛丸を建造中に、梨香が殺された。女房の加奈子は、おれが船造りに夢中だったから、幼い娘を死に追いやったと死ぬまで恨んでた。結果として、事件のあと、金剛丸の建造は断ることになった」
駿一の目が翳っていた。
「気は持ちようじゃ。殺された娘を想えば、いつまでも忘れがたく、口惜しいじゃろう。だからこそ、娘の供養船のつもりで、造ればいいのとちがうか」
「供養船か……」
駿一はつぶやいた。かれは寅吉のはなしに多少のところ気持ちが動かされた。
「二、三日考えてみるといい」
寅吉がほかの参列者の話題に入っていった。
飲食が早々と終り、慣例で食べ残された料理が女手で折り箱に詰められた。それぞれがそれを手にし、自前の車で帰っていった。
挨拶した住職から塔婆(とうば)を受け取った駿一は独り、福浦港が一望できる高台の墓地にむかった。眼下には漁港が広がる。奥深い湾内の対岸には日本最古の木造灯台がみえる。
墓地はきのう草刈と掃き掃除をすませておいた。墓の後ろに塔婆を立ててから、墓前に菊の花を飾り、線香を立て、手を合わせた。そのうえで、かれは墓地から眼下の海岸にある休業した土岐造船所をみつめた。クレーンの鉄塔とか、傾斜面から海に伸びた二本のレールとか、製図場や倉庫とかが過去の面影を残していた。
目を閉じれば、幼いころから聞きなれた木造船時代の鉄鎚(かなづち)の音がひびく。瞼の裏には、手先の器用な祖父がうかぶ。船台にならべた材木に墨(すみ)はで寸法を取り、チョウナや鋸(のこぎり)や鉋(かんな)で正確に板の幅と厚みをつけていく。やがて、恐竜の骨のような船骨が組み立てられる。そんな祖父のしごとをみるのが好きだった。
土岐家は江戸時代から長くつづいてきた造船業者だった。駿一の実父は家業を嫌い、近在の町役場に勤務していた。常日頃から、好不況に影響される造船業はみずものだ、駿一は大学を出て公務員になれ、と勧めていた。
しかし、駿一は造船科がある、遠く広島県の木江(きのえ)工業高校に進学したのだった。設計や艤装などを学んだ。また、ヨット部に所属し、瀬戸の海を快走して楽しんでいた。
卒業後のかれは教師の推薦で、瀬戸内海の因島(いんのしま)の大手造船会社に勤務したが、工程管理の一端を担うだけの仕事に、ある種のむなしさを感じていた。祖父の船造りに魅せられて育ってきた駿一は、木造船の建造には鋼船にない魅力がある、手造りの妙味がある、伝統的な木造船づくりを受け継ぎたいと、たえず考えるようになった。
実父と祖父がつづいて死去したことから、駿一は因島の造船所を退職し、この地にもどり、祖父の後を継いだのである。この年には農家の娘の加奈子と見合い結婚したのだ。
鋼船は工期が短く、船体の安全性が高く、船脚も速い。船体に錆が浮けば、ドック入りして塗装を施すだけで、手入れはかんたんだ。その反面で、木造船は材木の仕入れから建造、儀装まで手間と時間がかかる。進水後、年月が経てば、船体に付着した牡蠣ガラや虫を焼いたりしなければならない。
貨物船は年々、大型化してきて、木造船では対応ができなくなっていた。
鋼船はもはや時代の趨勢で、木造貨物船は骨董品だとまでいわれた。小型漁船すら強化プラスチックの高速時代となってきた。
駿一が木造船に拘泥するほどに、土岐造船所は競争力をなくしていた。受注となれば、手漕ぎの伝馬船など、かぎられた小舟のみ。または木造船の軽微な修理くらいだった。船大工たちは時代の流れに敏感で、溶接工などに転職し、この地から立ち去っていた。
『借金が積み重ならないうちに、造船業に見切りをつけたら』
加奈子は平気で、そのことばを口にしていた。それを聞くたびに、駿一は腹が立ち、口を利きたくない態度をとった。
農家育ちの加奈子が、港から2キロほど奥まった、後継ぎのいない農家が農地と宅地を安く売りに出されていると、物件情報を持ち帰ってきた。この際は農業で生計を立てたいという。加奈子は言い出したら、あとに引っ込まない性格だった。執拗に、毎日おなじ話題をつくってくる。造船所は廃業せず兼業農家。駿一はそれを条件に妥協した。福浦港の150坪の土地と住居は売り払い、その資金で農地と宅地を手に入れたのだった。
駿一は農事にも手を貸していたが、木造船の仕事が入ると、乗用車で造船所まで通った。新造船の仕事は十数年で数えるほどであった。
寅吉から観光船の注文がきたとき、駿一の心は燃えた。いっさいの農事を投げだし、それに夢中になった。そのさなかに梨香が能登の山奥で殺害される事件が起きたのだ。それを機に、造船所は休業にしたのである。
かれは墓地から土岐造船所の歴史をかえりみながら、
『……。供養船のつもりで、造ればいいのとちがうか』
と先刻の寅吉のことばをつぶやいた。
事件以後は造船業から手を引いたけれど、かれの心には船造りの魅力が燻っていた。指には鋸や鉋をあつかう感触が残っているのだ。
駿一は墓前にもう一度手を合わせてから、桶と柄杓を車に積み込んだ。
二階建て農家の自宅に帰りついた駿一は、一人住まいの淀んだ空気の臭いを感じた。折り詰め弁当はだれが食べるわけでもなく、土間の一角にある台所のテーブルにおいた。
かれは台所側の裏木戸から敷地の境目の小川までやってきた。古木の葉桜の影が川に映る。さざ波の川面をじっと視ていると、梨香の面影が映しだされた。二重瞼の眼がぱっちりした、親の欲目かもしれないけれど、顔立ちの整った愛らしい娘だった。春になると、この小川は散った桜の花弁が水面にびっしり張りつく。花をイカダに見立てて、花筏というんだよ、と娘におしえたことがある。
「梨香がお嫁にいくとき、結婚祝に、いい伝馬船を一隻つくってやる。父さんが舟の櫓を漕いで、花筏の海に舟道をつくりながら、嫁ぎ先まで送ってやるからな。むかしから、この地方の婚礼の伝統だから」
「ほんとう、船を造ってくれるの。約束よ」
梨香は悦んでいた。娘の命が絶たれてしまった今、娘の婚礼船などまったく無縁のものとなってしまったのだ。
この小川の縁で、駿一は娘によく笹舟を造ってやったものだ。きょうは法要の後だけに、つぎつぎ思い出がよみがえる。
「負けないよ、父さんの笹舟に」
梨香が徒競走のスタートの構えをした。よーい、どん。小川沿いの簡易舗装の道を走る。息切れして立ち止まり、勝ったよ、と小躍りして喜ぶ梨香の姿があった。
小川にかかる土橋はなんの変哲もないが、ここにも思い出があった。駿一は童話を歌いながら、蝋石で歌詞に登場する船や動物のなどを描いたこともある。突然の夕立で、絵があばたに濡れはじめると、梨香とともに母屋に逃げ帰った。陽が射し、土橋にきてみると、童話の絵は濡れて色が薄くなっていた。
こうした情景を思い出す駿一の脳裏には事件が鮮明によみがえって来た。
観光船の船骨の組立てをはじめた十月半ばだった。ある夕方、可奈子が造船場にやってきたのだ。加奈子の背丈は女にしたら高いほうだが、顔が細面で、目や鼻が小づくりだから、大柄にみえない。着痩せで得しているのよと、本人は自慢して聞かせていた。
「ねえ、梨香が家に帰ってこないの。きょうは、学校はお昼までだったし、うちで昼を食べて出かけたきり、帰ってこないの」
「昼過ぎ、この造船所にきて遊んでた」
駿一の手はノコギリで、原寸を墨でとった角材を挽(ひ)いていた。
「それで、梨香はどこにいったの?」
妻はふだんになく落ち着かない態度だった。
「しばらく仕事を見ていたけど……?」
「いやな予感がするの。一緒に捜して。おてんばな娘だから、海にはまったんじゃない」
妻の目には不安な光りがあった。
「まだ4時半じゃないか。それどころじゃない。この仕事は久しぶりの新造船なんだぞ。来年の4月末には引渡す約束だ。これから雪が降る冬場だ。甲板まで仕上げておけば、雪が積っても船内の仕事ができる。甲板ができていないと、しごとは大幅に滞るんだ。いまは1時間、1分がもったいない」
「あなたは娘が心配じゃないの」
「だいじょうぶだ、海に落ちることはない。ふだんから海岸で遊ぶな、と注意はしている」
かれは海をみた。肌寒い季節だけに、海水と空気との温度差から淡い海霧がでていた。
「誘拐されたんじゃないかしら」
「誘拐? こんな時間に、娘が誘拐されたといって、あっちこっち訪ねまわれば、街なかが大騒ぎになる。梨香は子どものくせに世話やきだし、造船所からの帰り道、年寄りの家に上がり込み、手伝いでもしているんだろう」
「母親の勘よ」
「根拠のない誘拐事件で騒げば、あとあとまで恥をかくことになる」
「もうたのまない。いいわよ」
怒りを残して妻が立ち去った。
まわりの裸電球の光が造船場のなかを支配したころ、可奈子がふたたびやってきた。
「ほんとうに胸騒ぎがするの。怖いくらい」
「もう、こんな時間か」
海岸を縁取る民家の灯火や、海岸通りの車の赤いテールランプが海面に映る。これはただ事ではないかもしれない。かれの心は得体の知れない不安に襲われた。と同時に、可奈子の騒ぎが自分のものとなった。
「海に落ちて流されたんじゃない。梨香は満足に泳げないし」
「可奈子は車で、もう一度、海岸通りから捜してみろ。おれは磯伝いにいってみる」
かれの脳裏には、海底に沈んで水死、という不吉なことばが横切った。
波打ち際に娘の持ち物が落ちていないかと、かれは丹念に捜しはじめた。波で打ち上げられた漂流物までも、一つひとつ確認する。梨香に結びつく手がかりはなかった。岬の突端から先は断崖で、進めない。かれは造船所まで引き返してきた。可奈子の車ももどってきた。千の浦、高岩岬のほうまで往って復たけれど、梨香の姿なかったという。
「あなたが目を離したから、こうなったのよ。造船所に遊びに来たんでしょ。なんでしっかりみてあげないの」
「しごと中だ。四六時中、見張っているわけにはいかないだろう」
「あなたはいつもそうよ。あの子に、何かあったらどうするの」
妻の顔は一段と深刻なものになっていた。
「ふたりだけでは捜しきれない。他人(ひと)の手をたのもう」
かれは急ぎ消防団長の家や駐在所に出むいた。警官を含めた二十数人ほど出てくれた。海に落ちたのではないか、と漁師が捜索船を沖に出してくれた。裏山に迷い込んだのか、と消防団員が手分けして捜す。
駿一は可奈子とともに、梨香の写真を持って警察の本署に出むいた。いくつか質問されたあと、捜索願が正式に受理された。事故と事件の両面から捜査をするという。能登全域の警察署に、梨香の写真が配布される、とおしえてくれた。
駿一は、地域別に割り振られた班の一員に加わった。海と山とで捜索が平行していたが、梨香が発見できないまま、夜が明けた。生死に関わる事態になるのではないか。駿一の脳裏には最悪の状況がちらついていた。
昼過ぎると、今年一番の冷たい北風が吹きはじめた。娘に万が一のことがあれば……、という慄きがくり返しかれの胸を襲った。
夕飯どきになると、各グループは捜索をいったん中断し、それぞれ自家にもどっていった。駿一も家路についた。裏木戸を開けると、
「どうするの、梨香が見つからなかったら」
土間の台所に立つ妻が尖った目をむけた。
「もどってくるさ。きっと」
それは強い願望であり、根拠のない、この場の気休めにすぎないものだった。
「なにかあったら、あなたのせいよ。観光船づくりに夢中で、すぐ捜してくれなかったからこうなったのよ。そうでしょ」
怒る妻を横目でみた駿一は、無言のまま、ご飯を自分で盛った。
「よく平気な顔して食事ができるわね。梨香のことを本当に心配してるの」
癇癪を起こした妻が、駿一の手から茶碗を奪い取った。
(心配しない親がどこにいるんだ)
心のなかで反発した駿一だが、一言も反論せず食事を放棄し、戸外に出た。かれは独りライトを照らし、裏山の小道とか、神社の境内とか、寺の本堂の床下とかを捜しつづけた。光のなかに、降る雨が映しだされた。
かれは雨具をとりに自家にもどり、夜の集合時間となったので、おなじ班の消防団と合流した。夜10
時には捜索の一時打ち切り。
駿一は、妻の目が気になり自宅に帰りづらかったというよりも、吉報を持ち帰りたいと、なおも独り海辺や森林をさがしまわった。警察署にも立ち寄った。期待した情報は入っていなかった。署を出ると、風雨が一段と強まっていた。この冷雨が娘の体温を奪い、死に追いやるかもしれない。わが子へ手が差しのべられない焦燥とやる瀬なさと苛立ちとが、かれの胸の奥で渦巻いていた。
3日目の朝になっても、強い雨は衰えず自宅まえの小川の水量を増す。流水の音が駿一の胸の内で、おそろしく反響していた。
警察は公開捜査に踏みきった。少女が行方不明、と報道されると、かなりの数の情報が集まってきたようだ。なかには有力な情報があると、捜査官が駿一におしえてくれた。
梨香が行方不明になった当日の午後3時ころ、押水町のコンビニ駐車場に停まっていた白っぽい乗用車の助手席に、公開捜査の顔写真によく似た少女が独りで乗っていたと、複数のおなじ情報があったという。金沢在住の若者から、モーター・ドライブで宝達山(ほうだつさん)(六三七メートル)の山頂についた午後4時ころ、サンドイッチを食べている少女と30歳前後の女性を目撃したと通報があった。
警察が確認すると、梨香の着ていた服の絵柄はおなじ。捜査員が金沢の通報者と接触し、梨香の顔写真を示すと、まちがいないと答えたようだ。
『犯人は少女を手荒な方法で、連れ去ったわけじゃないな。ことば巧みに誘ったんだろう』
誘拐事件とみなした警察は本格的な捜査に入った。駿一が警察情報をもって自宅にもどってくると、土間の一角の台所では妻が憔悴した顔で、柱に寄りかかっていた。
「あの子が死んだら、私も死ぬからね」
といってから、心を閉ざした表情になった。
ふたたび警察署を訪ねると、確証の高い話だといい、新たな情報が伝えられた。……おとといの朝、奇妙な女が役場前から高岡ゆきの定期バスに乗ってきたと、その運転手から情報が寄せられた。女の服はすこし破れ、数日間、山中で彷徨した感じだったという。警察は宝達山にいた女と同一人物だとみていた。
(梨香はなぜそのバスに乗っていなかった? 女は梨香を殺して下山してきたのか。殺害していないまでも、雨の降る山中で、10歳の娘を放り出せば、どうなるのか)
能登の山は低い山ばかり。迷い込むと目標となるものがすくないだけに、かえって彷徨し、山奥から出てこれなくなる。事件発生からの日数を考えると、娘は体力をなくし、極限状態のはず。そう推量するほどに、かれは絶望のどん底に突き落とされていく自分を知った。
母屋の電話が鳴った。ここのところ悪質な悪戯電話が土岐家に入ってきた。ひとの不幸を喜ぶ人間がこの世に数多くいるのだと、つくづく思い知らされた。神を信じれば娘さんは帰ってきます、と宗教団体からいかがわしい勧誘電話も入ってくる。腹が立った。
あなたの娘を預かってます、3000万円用意しなさい、と30代半ばと思える女の声が入ってきた。駿一は動転した。それを警察に連絡すると、捜査員が飛んできて録音機や逆探知の機械を据えつけた。おなじ内容の電話がもう一度かかってきたけれど、ものの五分で切れてしまった。
録音機を取りつけた刑事は、悪戯かな、事件のことは新聞情報だけだ、と洩らしていた。
「3000万だなんて。そんなお金はないわ」
妻の顔にはこれまでとちがう深刻な表情がうかんだ。
「警察は悪質ないたずら電話だとみている。ここは様子をみてみよう」
「ほんとうに、犯人からの要求だったら、どうするの。3000万円が用意できていなければ、梨香は殺される。見殺しにする気なの」
「見殺しにするとはいってない。すぐに用意できる金じゃない」
「お金と梨香のいのちと、どっちが大切なの。わたし親戚にたのんでみる。銀行にもいって、家と土地を抵当に借りる交渉もしてみるわ」
「きょうは土曜日で、銀行は終った」
「そんなことばかり言って、あなたは梨香のためになにもしないつもりでしょ」
加奈子が重い足取りで出かけていった。
駿一は捜査員に相談してみた。お金は準備できるにこしたことはないが、安易に渡されたら困る、警察の指示に従ってほしい。お金だけですべて解決ができるものじゃない。犯人の魂胆は人質を渡さず、お金を奪うことだ。だから、金を渡しても、娘さんを帰さないことも考えられる。
「もし、3000万円が用意できなかったら、どうなるんでしょうか?」
警察は偽の紙幣の束で対応します。ただ犯人が偽札だとわかれば、罠にかけられたと思い、娘さんを殺すおそれがある。
(やはり、金がないと、梨香が殺されてしまう。金策が事件解決のカギになる)
駿一は加奈子だけに任せられないと、寅吉の家を訪ねた。一連の事情を説明したうえで、身代金の3000万円の金を貸してくれないだろうか、と持ちかけた。家や田地は抵当に出すからといい、駿一は両手をついて頭を下げた。
手もとで遊ばしている金はないから、銀行に掛けあうが、早くても月曜の話になる、借入れとなるとさらに伸びるかもしれない。いずれにしろ、子どもの命がかかっているから、最大限に協力する、と約束してくれた。
駿一が自宅にもどってくると、加奈子が土間の一角にある小座敷に座っていた。金策に失敗したのだろう、妻はなにも語らず、気のつよい性格が折れ曲がったかのように、うな垂れていた。持ち前の勝気さだけでは、精神的に打ちのめされた自分自身を支えきれなくなったのだろう。
「週明けにも、寅吉さんから3000万円を借りられるメドがついた」
犯人から今日すぐに身代金をもってこいと要求されたらどうするの、という妻の反発を予想していたが、加奈子は無言だった。
「おれが食事をつくろうか」
加奈子は答えなかった。
「食べなければ、からだに毒だから」
ふだんならば、妻のからだよりも、梨香の身を心配しなさいよ、と反論がもどってくる。しかし、妻はただ視線を落としていた。
駿一が畑から夕飯用の菜っ葉をとってきた。プロパンのガス台にかけたステンレス鍋に水を張り、沸騰させ、少量の塩を入れてから、菜を茹(ゆ)ではじめた。奥座敷の電話が鳴った。
夫婦はともに身震いした。いつもは悪質ないたずら電話か、知人の励ましの電話だが、こんどは犯人かもしれない。そんな脅えた目で、ふたりは目線を合わせた。駿一が奥座敷にむかった。
(金が今日じゅうにできなければ、娘を殺す、最後通告だといわれたら、どう答えるべきか)
それにたいする満足な応酬のことばもないまま、駿一は受話器のまえに立った。刑事の目線による合図で、受話器を持ちあげた。
警察署からの電話だった。
──小矢部川の川瀬で、釣人が少女の死体を発見したようです。服装からして娘さんの可能性が高いから、これから確認ねがいます。
梨香とおなじ服……。間違いであってほしい、人違いであってほしいと、かれは祈るのみで、電話の相手に返すことばがなかった。
──現地の警察からの連絡では10歳くらいの女子で、体型も似ているようですから。いまからパトカーで、そちらに迎えにいきます。
駿一がことばを失ったままでいると、
──そばの刑事に代わってください。
とわれて受話器を渡した。
絶望感に襲われた駿一のからだが、おそろしく震えた。台所にむかうかれの足は膝から崩れ落ちそう。梨香の死。それを妻に伝える役から、かれは逃げだしたい心境だった。
廊下側の座敷戸を開けると、土間の片隅で、妻がなおも背中を丸めてうな垂れていた。
「発見されたらしい、梨香が」
「だいじょうぶだったの。そうなんでしょ」
加奈子が、駿一の態度から悪い結果を察し、尖った眼になった。
「場所は、小矢部川の川瀬らしい」
「梨香を殺したのはあんたよ。たのんでも船造りに夢中で、探してくれなかった。あんたは薄情な父親よ」
泣け叫ぶ加奈子が土間に飛び降り、野菜籠を持ちあげると、投げつけてきた。手当たり次第に、周辺の物を投げつける。食器の割れる音がひびく。まるで半狂乱だった。
「奥さん、気をしっかり持って」
数人の刑事が割って入ると、妻は台所の板の間に泣き崩れた。
5分後、パトカーが迎えにきた。駿一が泣き伏す加奈子の脇下に手を入れて起こそうとすると、その手が振り払われた。加奈子は腰が抜けたように、立ち上がれなかった。刑事ふたりが加奈子をかかえあげ、パトカーまで連れて行ってくれた。
現地までは長い道のりだった。いくつかの峠を越えると、小矢部川の上流の景色が目に入ってきた。山間の道をつづら折に下る。無線のスイッチを入れた助手席の警官が、詳細な場所を確認する。川幅が広がり河岸台地になると、赤色灯をまわすパトカーが3台ほど前方に見えてきた。多くの警察官も立つ。
「あそこだな」
運転する警官がスピードをゆるめた。富山県警のパトカーの横に停めた。先に降りた助手席の警官が、後部ドアを開けてくれた。
車外に踏みだす駿一の足はぶるぶる震えていた。河岸の草土手を下ると、青いシートが目に飛び込んできた。
「確認をおねがいします」
警官がシートを剥がす。
その下には頭髪が乱れた少女の死体が横たわっていた。口唇がやや開き、赤いカエデが二葉ほどはみ出す。まるで口もとから血を流す姿にみえた。川魚が肉をつついたのだろう、腕や顔がやや白骨化していた。私服の警官に勧められるまま、駿一は痛ましい死体を深くのぞきこんだ。首筋には大きな黒子があった。
梨香だ。そう確認すると、過去におぼえのないような恐ろしさが全身を駆け巡った。
「まちがいありません」
駿一は娘の死顔をなでた。それは氷のように冷えきった感触だった。やり場のない無念さが自分を押しつつんだ。10歳から先の梨香の人生がすべて空白だと思うと、なおさら憐れで居たたまれなかった。
突如、加奈子が駿一の身体を押退け、死体においかぶさり、わッと泣いた。妻の背中と娘の死体をみつめる駿一は胸が切り裂かれるような、言いようのない気持ちに陥った。
火葬された梨香が白桐の箱で帰宅してきた直後、警察から電話が入り、鳥栖麗子(とすれいこ)という女を誘拐殺人の容疑で逮捕した、とおしえられた。大勢の取材陣やカメラマンがわが家に押しかけてきた。いまとなれば、マスコミの記者になにをどう語ったのか、記憶には残っていない。悲憤の感情がことばで表現できず、なにも語らなかったと思う。
葬儀のあと、加奈子は疲労と心労から体調を崩して寝込んだ。容態はいっこうに回復せず、金沢の総合病院に入院させた。見舞っても、妻の話題はいつも娘のことばかり。
「あなたは梨香に冷淡だったわ」
「何度もいうようだけど、加奈子が梨香を捜して、と造船所に来たときは、犯人はもう宝達山まで連れて込んでいたんだ。手遅れだ」
「あなたが早い段階で、福浦の駐在所に駆け込んでくれていたら、警察は非常線を張って梨香を取り返してくれてたわ」
警察がそんなに機敏に動くのかと、駿一には疑問だった。病身の妻に反論し、言い争っても、梨香は生き返るわけでもない。かれは言い負かされた顔で引っ込むのが常だった。
「梨香は成仏できないでいるわ。いつも夢枕に出てくるのよ」
ということばが駿一の心を痛めた。
かれは梨香を失った落胆から、精魂込めて新船を造る気力が失せてしまった。一方で、妻のことばが脳裏から離れなかった。
『梨香を殺したのはあんたよ。たのんでも船造りに夢中で、探してくれなかった』
この際は造船業から手を引き、休業にすることにきめた。駿一は寅吉に、観光船の建造を未完成のまま断りを入れた。事件からのいっさいの事情を寅吉に説明すると、設計図をまわしてくれたら、ほかの造船所にたのむからといい、承諾してくれた。
加奈子のほうは、さらに膵臓と腎臓を併発した状態に陥った。長患いの身になり、何度も入退院をくり返す。畑仕事は駿一ひとりの腕にかかってきた。毎年のように霜とか、冷夏とか、台風とかの対応にまずさがあり、収穫が極端にすくなかった。生活にも影響を与えていた。
将来を見据えた駿一は、農業に専念するには力不足だし、あれこれ考えた末に七尾市の港湾荷役の会社に応募し、フォークリフトのオペレーターとなった。
梨香の死から数えて6年目のある日、金沢の総合病院から職場に、奥さんの容態が急変したから、すぐいらしてほしい、と電話が入ってきた。七尾から車で金沢にむかった。
妻の個室は無人だった。ナースステーションで、看護婦に訊くと、加奈子はICU(集中治療室)のほうに移されたという。面会を申し出ると、看護婦が担当医に訊いてくれた。危篤状態だからといい、許可が下りた。
ICU専用のガウンをきた駿一は専用スリッパを履いて待機していた。思いのほか長く待たされた。やっと呼ばれた。妻のベッドまわりには人工呼吸器、生体情報監視装置、輸血ポンプなどの医療機器が林立する。それだけでも加奈子が危篤状態だとわかった。
「もうダメみたい」
酸素マスクのなかから、妻はかろうじて聞き取れる声でいった。
「がんばるんだ」
「……、これで梨香と会えるのね。梨香はどこまで迎えに来てくれるのかしら」
と細い声でいう。
「あきらめるんじゃない」
「あの子、許してくれるかしら」
「気をしっかりもつんだ」
加奈子が吐血した。ベッドが真っ赤に汚れた。と同時に、計器が異常を示したのか、看護婦が数人出かけつけてきた。医者もきた。妻の意識は遠ざかり、唇が半開きになった。
医師がくり返し呼びかけても、反応は鈍かった。妻の脈をみた医者が瞳孔ものぞく。その視線が医療計器に移ってから、数分後、ご臨終ですといい、妻の瞼が閉じられた。
加奈子はまだ微かに口を開いている。もっと、なにかが言いたかったのだろう。駿一は深い悲しみに襲われた。駿一の涙が死顔にこぼれ落ちた。かれは妻の顔をやさしくなでた。ふだんの暖かさが残る。一方で、看護婦たちは妻の身体から、手際よく医療器具を外していく。加奈子が人間から人体に変わったのだ。それがまた悲しく、哀れだった。
妻の納骨の日までは、なにかと弔問客が自宅にあった。その後は閑散としたものだった。家のなかを取り仕切る妻がいないとなると、駿一は何事も億劫で、ついつい不精になった。七尾の勤務先から帰宅しても、家のなかは蜘の巣が張った蛍光灯の光で冷え冷えとしている。何時間も部屋の片隅で過ごす、倦怠感が同居する毎夜だった。そのうえ、妻を亡くしたころからはじまった咳に、何年経っても悩まされつづけた。
梨香の十三回忌の法要が終った今、かれは妻子の死を回想する一方で、寅吉からの新造船のはなしに拘泥する自分を意識していた。
かれは奥座敷に入り、仏壇にロウソクを灯し、心の迷いをのぞき見ていた。
「このさい観光船を造ってみるか。寅吉さんのいうように、供養になるかもしれない」
これは加奈子への裏切りか。妻は死ぬまで、梨香の生命よりも優先したといい、造船業を嫌っていた。加奈子の入院先で、二度と船大工はやらないよ、と何度も誓ったものだ。
……わたし、船を造る父さんをみるのが大好きだった。
梨香の声がふいに聞こえたような気がした。
かれの視線が鴨居の遺影にむけられた。10歳の梨香は笑顔で、加奈子は硬い表情だった。かれは遺影を凝視しながら、妻にこう説明した。……能登の海岸線は荒海に削られた、断崖絶壁が多い。海辺の集落や港を結ぶ交通網はかつて陸路よりも、海路が発達していた。伝統的な婚礼は華やかに飾る一枚帆の小船、あるいは伝馬船で花嫁を送っていた。
「おれは梨香に伝統的な婚礼船を造ってやると約束した。娘が亡くなったいまも、その約束が心に残る。北前船を模した観光船だが、帆船を梨香に捧げる、という気持ちと気迫で、精魂を込めて建造したい。これは船大工への未練でなく、梨香の供養のためだ。加奈子、大目に見てくれ」
駿一は妻の遺影から、梨香の供養船なら、いいわよ、という表情が読み取れた。
かれはいまある貯金を調べた。当座の収入がなくても、2年間は食べていけるだろう。明日には七尾の会社に退職届を出すときめた。
駿一はさっそく造船所にむかった。社名が刻まれた鉄製の円い門柱は赤錆がうかぶ。トラック幅で開放できる門扉も傷んで傾く。かれは各設備の点検をはじめた。二本の6キロレールは曲がりもなく、直線だ。レールに乗る船台は滑車に油を差せば、充分に使える。
敷地には建物が三棟ある。ひとつは一階が機材置場で、二階が事務所のプレハブ造りだった。となりは現図場で、屋根と柱だけの吹抜けである。もうひとつは軽量鉄骨でできた作業場だった。ここには木材を削ったり、切ったり、挽いたりする作業台があった。
クレーンの土台はひび割れていた。荷重には耐えられず、危険だと判断した。機材倉庫のなかにはワイヤーとか、溶接棒とか、大工道具とか、それぞれ棚の上で埃を被る。充分に使えるもの、もはや使えないものと、かれは目で区分けしていた。
駿一はふと思い立って北陸電力の営業所に200V動力の申込みに往って復ってきた。
事務所に入ったかれは、過去の建造船の設計図がならぶ棚から、未完成に終った、先の観光船の設計図をとりだした。それらはボート型だから、むずかしい設計ではない。
しかし、こんどは北前船だ。手応えがあるぞ、とかれは気を引き締めた。
かれはまず頭のなかで、多種のスケッチを描きはじめた。総トン数20トン以上、又は長さ15メートル以上は造船法による許可がいる。それ以下の観光船にする。いま寅吉が所有するボート型観光船は55人乗り、総トン数が15トンである。この範囲内で、建造することにきめた。
北前船の現物は残存していないはずだ。明日からはどこか資料館で、北前船の文献を入手し、船体構造を研究する必要がある。そもそも木造船は寿命がつきると、解体されて薪になる。北前船は現存せず、絵馬でしか知ることができないと思う。鋼船も同様だ、スクラップとなり、電気炉で解かされてしまう。船にはそんな末路があるのだ。
七尾の職場に退職届を提出すると、急な辞めかただといい、上司から嫌味をたらたらいわれた。観光船の建造には工期がある、職場に義理立てすれば、引渡し期日に間に合わないと割り切り、即時の退職を推し通した。
電気が思いのほか早く通電した。蛍光灯が灯った事務所で、かれは絵馬の写真などを参考にし、船のアウトラインを描きはじめた。船形は帆船だが、推力は船舶エンジンを使う。
しかし、帆の操船ができる構造にしておかないと、まやかしの北前船になってしまう。高校時代からヨットの帆を操ってきた駿一だけに、それにもつよく拘泥した。
外観は北前船でも、お客の安全が最優先の小型客船に変わりない。金剛海岸には岩礁が多い。船頭のミスによる座礁も視野に入れ、船底は丈夫にする。建造の手間はかかるけれど、荒海の日本海でも乗り切れる木造漁船の構造を取り入れ、四枚(しまい)接ぎ(はぎ)の船にする。それは船底材を中心にすえ、左右に下棚(しただな)、さらに上棚(うわだな)をのせて舷側(げんそく)とするものだった。
北前船の船首と船尾は極端にそそり上がる。荒波に突っ込まないように、浮力が大きい船体だ。そのまま生かす。
観光客が船内で右に断崖絶壁を見、左に焼けた夕陽を見、景観に感動して一度に大勢が移動することもあるだろう。それでも安定度が保てるように船幅を広くとっておく。
駿一はいくつかスケッチを起こし、寅吉に示したが、もっと帆の高い目立つ観光船がほしいという。重心が高い船は波に弱い。しかし、発注者の意向は尊重しなければならない。
かれは構造計算をしがら、何度もスケッチを描きなおした。二本柱の帆ならば目立つが、一本マストに一枚帆が北前船の特徴だ。それを変えるわけにはいかない。船底を深くし、船梁の数を増やし、高いマストにかかる風圧に耐えられる構造にきめた。
50人の観光客が船内から存分に景色を楽しむとなると、窓ばかりが目立つ船になってしまう。工夫が必要だ。北前船の舷側は格子状に組んだ欄干の垣(かき)立(たつ)だから、これを窓枠に利用し、彫刻を施せば、これが〈売り〉の観光船になる。この発想は自身が気に入った。
難航していた設計図が年末にやっと完成した。これからの建造では来春の引渡しはとうてい無理。一年先延ばした再来年の春にしてほしいと、寅吉に申し出た。いまある4隻の観光船で客を捌(さば)けているし、新船はあらたな客の掘り起こしだから、それでもいい。じっくり好い船を造ってくれ、と承諾してくれた。
元旦は初詣客を呼び込むように、神社の太鼓が聞こえた。金剛丸と名づけた船の詳細図が完成したが、寅吉の孫から別の希望が出てきて、最終承認図は2月半ばとなった。
梅の花が咲きはじめたころ、かれはチェックの長袖シャツにコールテンのズボンをはき、地下足袋を履いた。船大工という充実感が全身に拡がった。雪をなでてきた風が吹き抜ける現図場で、かれは設計図に基づいた型紙をとりはじめた。船底や舷側の曲がりにはとくに注意を払った。型紙が出来上がると、かれは材木屋に出むき、良質の杉一級を中心とした角材、平板などを注文してきた。
数日後、製材所の小型トラックが造船所の敷地に入ってきた。いよいよ建造だ、という実感が胸のうちに広がった。クレーンがつかえず、運転手とふたりで荷台からの手降ろし作業だった。春陽の下で、いい汗をかいた。
かれはさっそく大板の厚い杉材に寸法をとりはじめた。墨壷(すみつぼ)から細糸を引きだし、二本の指で弾き、直線を引く。こんどは直角に曲がった計測のサシガネをあてて切り落とす寸法をきめる。墨をふくませたスミサシで印をつけていく。寸法が緻密に決まると、板の両端と、横幅とを鋸(のこぎり)で切り落とす。そのうえで、鉋(かんな)で精緻な寸法に仕上げていくのだった。
船大工のしごとに打込みはじめると、ふしぎにも咳がとれてきた。咳そのものを忘れる日々となった。小学校から正午のチャイムがこだます。ひと区切りをつけた駿一は、現図場の板敷きのうえにポットと赤い急須をおいた。茶の風味だけは凝り性で、いつも茶葉は濃く煎ていた。
先刻から、茶色の犬が地面に胴体を投げ、こちらをみている。尻尾の短い、睾丸の垂れた雑種だった。ここ半年前から迷い込んだ犬で、居座り、飼い主が見つからないまま一緒に暮らす。妻子を失った心の空洞が犬の相手で多少埋まることもあった。
コンビニから買ってきた弁当を開いた駿一が半分ほど食べると、そこから先は餌としてよこせと、歯茎を剥きだして吠えた。
「チャは、食べることだけは忘れないんだな」かれは茶色の犬を単純に、チャ、と呼ぶ。
弁当の残りを目の前においてやった。かれは別に二個のおにぎりをとりだす。
4月半ばから、かれは焚火をおこして《かわら焼き》という作業に入った。杉板の下を炎で熱し、表面から水をかける。板がしだいに焼きイカのように反っていく。板を焼き焦がさないように、じっと見張る。その一方で、舷側の曲線の型紙に合わせた角度(アール)をつける。微妙に、ミリ単位で反りを再確認していく。
かれは長いこと船大工から離れていたせいか、腕が鈍り、最初の板を無駄にしてしまった。失敗した杉は母屋に持ち帰り、風呂場の薪とすることにきめた。入浴は好きで毎日欠かさず、肌が赤くなるほど熱くわかした湯に入るのが常だった。
主要な部材の船底板とか、舷側とかの材木の準備ができたころ、3日間の約束で雇った臨時工の50
代の男女3人がやってきた。と同時に、リース会社のクレーン車が約束時間通り造船所前にやってきた。いよいよ組立作業の開始だった。
駿一の指図で、長い形状の船底板が吊り上げられていく。3人の男女が、空中から降ろす船底板を船台のうえに丁寧に置いた。
「おい、チャ。そこは船台だ。板をならべるからじゃまだ」
犬はとろとろ歩き、離れたところで座り込む。気だるく尻尾を振り、こちらをみている。
クレーン車のワイヤーがつづいて舷側になる下棚を吊り上げた。その板はすでに《かわら焼き》で船形の流線型に曲げられている。そっと降りてくると、駿一が船底板と下棚とをツカミでL字型に仮止めした。寸法はぴったりだ。こんどは上棚が降りてきて下棚のうえに垂直に立ち上がる。これも仮止めする。
船底板の左と右に、下棚と上棚がつくと、四枚(しまい)接ぎ(はぎ)の北前船の舟形ができた。海はすでに夕映え色だった。クレーン車と臨時工が一日の作業を終えて引き上げた。
翌朝、臨時工たちが早目にやってきた。
木造船はかならず二枚の板を張り合わせる。厚い板一枚のままだと、材木の節目が破れた場合、船内に浸水し、沈没するからである。
〈二枚をきれいに張る〉
これが船大工の腕前の一つになる。下棚と上棚の部材一つひとつの二枚重ねが成功するたびに、かれは万力をもちいて仮に固定した。
ここまでの作業は予定通り3日で終えた。「上々の出来ばえだ。これで一杯やってくれ」
かれは三人の臨時工に日当のほかに酒代を加えた。つぎは来月の肋骨状の船梁を組立てで、たのみたいと約束をとりつけた。
その後の駿一は独り黙々と建造を進めていた。船底板と棚板を固定する船釘を打つ。釘の長さは14
センチ、釘の頭も大きい。両ツバノミ(鑿)で、釘の通る穴を四角く彫り、それから釘を打ち、仮止めから本付けへと進んでいく。このところ造船所から、金槌の音が途絶えることはなかった。
5月の太陽が照りはじめていた。和船の主要な構造のひとつ船梁(ふねばり)の作業に入った。船の耐久性に影響する重要な部材だ。いままでとはちがった緊張感が全身に広がる。3人の臨時工の手を借りた、その翌日だった。
チャが突然吠えだした。門柱のそばに、中年女が立っていた。女はセーターを着、緑のパンツ姿だった。チャに吠えられた女性は敷地のなかに入れず、たたずむ。町のものではないが、どこかしら見覚えのある顔だった。
彼女は化粧気もなく、二重瞼の目には暗い翳を感じさせた。年齢は40歳前後だろう。だれだか思いだせず、駿一は吠えるチャを叱ってから、歩み寄った。
「なにか用?」
と声をかけても、彼女は無言でこちらをじっと見つめている。その顔や腕にはシミや皺がやや目立つ。それから判断すれば、40代半ば過ぎにも思える。
「うちの造船所に用かな。こっちにどうぞ」
駿一は木材が積み重ねられた作業場のほうに招いた。彼女は素直にそれに従った。
「鳥栖麗子です」
「えっ」
かれはおどろきの目で、屹(き)っとにらみつけた。梨香を殺した女がここに現れること自体が信じられなかった。
「先月の初め、刑務所から仮出所で出てきました。お詫びにおうかがいしました」
「娘を殺しておきながら、よくもぬけぬけと来れたものだ」
怒りから、駿一の身体がおそろしく震えた。
「出所後すぐにでも、お詫びにうかがいたかったんですが、仮出所の保護観察の身ですから、保護司から仕事や住居が定まるまで、遠出が許されませんでしたから……」
きょう独りで、能登に脚を運ぶことが許されたんです、と彼女はつけ加えた。
「娘の遺体をみたときから、犯人を八つ裂きにしてやりかった。おれの気持ちはいまも変わってないんだ」
10歳の娘を殺した残忍な犯人でも、一〇年以上経過すれば、仮出獄が許される。しかし、娘は永遠に家に帰ってこれない。そう思とはげしい怒りが胸の奥から突き上げてきた。
「お怒りは充分わかっています」
「それがわかってながら、なぜ、のこのこやってきた」
「罪のつぐないをさせていただきたくて、訪ねてまいりました」
「つぐないだって? 梨香ばかりじゃないんだ。娘が殺されたことから、女房は落ち込み、からだを悪くして死んだ。それもこれもみなおまえのせいだ。娘と女房を死に追いやっておきながら、つぐないだって。冗談じゃない」
麗子は黙っていた。
「娘を殺した極悪人に、15年の懲役なんて甘いんだ。おれが制裁してやる」
逆上した駿一は、道具箱から鋭い刃先の鑿(のみ)をつかみ、彼女にむけた。一歩二歩と迫った。「ただの嚇しだとおもうな。このノミでおまえを殺せば、犯罪者になる。それでもいいんだ。山奥で殺された梨香の仇がとれるなら」
駿一は鑿の刃で空を斬ってみせた。
「できることなら、つぐないをしてから、殺していただけませんか」
「命乞いか。本気で、罪をつぐないたければ、梨香が死体であがった小矢部川に飛び込んで死ね。この福浦の海でもいい。こっちの手をわずらわせずに死ぬのが、唯一のつぐないだ」
「自殺して過去の罪がつぐなえるなら、そうさせていただきます」
彼女には駿一の怒りを受け入れる落着きがあった。神経の細いような顔立ちだが、どこか図太いものが感じられた。
「娘を殺しておきながら、そのいいぐさはなんだ。別につぐなってもらわなくてもいい。殺した娘を元通り、ここに連れてこい。それしか許さん」
かれは右手で鑿を振り、左手で華奢な彼女のからだを地面に突き倒した。駿一は、横たわった女の上半身にまたがり、ブラウスの衿をつかみ、刃先を首筋にむけた。麗子は静かな表情で、駿一を見つめている。
くそっ。駿一は鑿を突いた。刃先は彼女の顔からわずかに逸れ、地面に埋まった。殺された親の気持ちがわかってたまるか。かれはもう一度、突きなおした。またしても、地面に喰いこんだ。
仰向けの麗子は、娘の仇がとれない父親をじっと見つめている。こちらの悲しみを傍観しているか、内心は嘲笑っているのだろう。
駿一は、彼女の喉に刃先を刺せない自分が口惜しく、悔し涙が流れた。駿一の両手が麗子の首筋へとのびた。絞め殺そう。このさきどんな罪に問われようとも。
……父さん、殺さないで。
幻聴なのか。それとも潮風の音なのか。すくなくとも梨香の声が聞こえたような気がした。かれは背後をふり向いた。高波がレールに沿って駆け上がってくる光景のみだった。
それは幻聴にしろ潮騒にしろ亡き娘の心かもしれない。駿一の胸のうちから、殺意がすっと消えた。かれは仰向けの彼女から離れた。
「帰ってくれ」
背をむけた駿一は、乾いた藻が張つく海辺まで歩み寄った。唇をかみしめたかれは口惜しさから泣いた。涙を作業服の袖でぬぐい、ふり向くと、鳥栖麗子が重い足どりで門の外に出て行く。家並みがその姿を吸収した。
駿一は小石を拾って海面に投げた。二度、三度とくり返す。かれの脳裏には地方裁判所の法廷の光景がうかんできた。
うな垂れて法廷に現れた鳥栖麗子の頭髪には白い毛がちらつき、頬肉までも落ち、生気がなかった。新聞やテレビでみた顔立ちのよい女とは雰囲気がちがう。彼女の両脇には青い制服の刑務官が座り、手錠が外された。
3人の裁判官が壇上に現れた。
「被告人はまえに」
彼女は打ちひしがれた態度で、証言人席に立った。裁判長から人定質問がむけられた。29歳、本籍は横浜です、と弱々しく応えた。
公判検事が早口で営利誘拐殺人の起訴状を読みあげた。冒頭陳述のあと、検事の尋問となった。被告人は短大卒業後、旅行会社に勤務し、4年後に結婚した。被告人は、2歳の男児を亡くした後、夫から死因は妻の過失にあると離婚を申し立てられ、成立した。
失意と絶望感から被告人は、10月7日の真夜中、実弟の白い乗用車を無断で持ちだし、能登にむかった。翌日の昼には誘拐の犯行現場となった福浦港の高台の灯台に着いた。そこは北陸路の観光スポットで、慶長13年に造られた日本最古の木造灯台がある。
灯台の駐車場には3台の観光客の車が停まっていた。被告人は車を停めると、崖下につづく角度のある道を降りていった。そこには本件の被害者となった10歳の少女が防波堤の袂の乾いた平たい岩礁のうえで、蝋石の絵をかいて独り遊んでいた。赤いブラウスにキュロット姿で、目の大きな少女だった。
「被告人は、少女を見た瞬間、あまりにも可愛くて、誘拐したいという犯行に駆られた」
と検事が述べた。
異議あり。弁護士が立ち上がった。この段階で、犯行の意図はなかったと反論した。壇上の裁判長が左右の陪席判事と打ち合せした。弁護人の主張が取り入れられた。
検事から、被告人の証言が求められた。
麗子は少女の絵をのぞきこんだ。漁船とか、山とか、獅子舞いとかが上手に描かれていた。
「すてきな絵ね。これは獅子舞いでしょ」
「そうよ。こわいのよ。祭りをみていたら、逃げても、獅子は追いかけてくるの」
そう話す少女の口調は可愛かった。
「怖そう。この漁船はなにをとるの?」
「いろいろなお魚」
少女には、魚種の知識があまりなかった。親は水産関係者ではなさそうだ。
「この町に、おしごとできたの?」
「ちがうわ。泳ぐ場所をさがしにきたのよ」
麗子は少女に、死に場所を求めにきたとはいえず、婉曲に語った。
「えっ、こんなに寒いのに。止めたほうがいいわよ。ひとりで海に入ると、海蛇がでるのよ。父さんがいつもいってるの。ちょっとでも足がつかると、蛇ががぶりとここを噛むの」
少女が真顔で太腿を指した。
「蛇は大嫌い。泳ぎはやめたわ」
麗子は恐がる真似をしてみた。実際、蛇は苦手だった。こちらの仕草がおかしかったのか、少女はくすっと笑った。
「お家は、この港なの?」
「小学校の裏から、ずっと奥にいったところ。父さんのお仕事場は、あれよ」
と対岸の造船所を指す。
「父さんのお仕事を終るまで、絵を描いて待ってて、いっしょに帰るの?」
「ちがう。父さんは夜までおしごとだから、梨香ひとりで帰るの」
「梨香ちゃんというのね。いま帰るなら、車で、お家まで送ってあげてもいいけれど」
「知らない人の、車に乗ったらいけないの。学校の先生に怒られるの」
「そうよね。見も知らずのひとの車には、乗らないほうがいいわね。そろそろいくわ。いい絵をいっぱい描いてね」
麗子は堤防の袂から坂道を登った。少女が人懐こい顔で、灯台の駐車場までついてきた。他の三台の車はみな立ち去っていた。
「ここの絵を見て」
先に去った車の下から、蝋石で描かれた灯台とか、神社とか、蝶の絵とかが現れていた。少女はこれらの絵もみせたかったらしい。
「鳥居が上手に描けてるわね。それに蝶が活き活きと舞ってる」
「父さんがいつも宝来山の蝶を観に連れて行ってくれるの。これは山の神社なのよ」
「梨香ちゃんの画いた神社は、ご利益がありそうね。なんの願いごとをしようかしら。海蛇に噛まれませんように」
彼女は蝋石の絵に手を合わせた。
少女は無邪気に笑っていた。
「ほんものの神社でお参りしたら、天国にいけるかしら」
「天国って。死んだところ?」
「いいところみたい。一緒にいってみる?」
「死ぬのはいや」
少女はにらみつけた。
「……この蝶はいつごろ観にいくの?」
「秋。いまごろよ。頂上の池にいけば、きれいな蝶がいっぱいみられるの。ことし、父さんは観光船を造ってるから、忙しくて連れて行ってくれないの」
「それは残念ね。こんなすてきな蝶が観られるなら、せっかくだから宝来山に寄ってみようかな。梨香ちゃんは穴場を知っているみたいだから、案内してくれたら、うれしいな」
「4時まで帰らないと、お母さんに怒られる」
「この港から宝来山まで、どのくらいかしら」
麗子は車内から道路地図を出してみた。
「急いで往復すれば、夕方までに、お家に送ってあげられるわ」
検事が突如として立ち上がった。福浦港から宝達山の山頂まで2時間余りで往復し、なおかつ蝶の舞いを観るのは時間的にも不可能だ。被告人は当初から、少女を家に帰すつもりもなかった。殺害する意図で、少女を車に誘いこんだ、と鋭い口調できめつけた。
弁護人がこの段階でも、誘拐の意図を持っていなかったと反証した。
「地図を見て、4時は無理にしても、日没まで送り帰せるかな、という気持ちはありました。少女が素直に助手席に乗ったので、車を走らせました」
宝来山には何時に着いたのかと、検事が訊いた。午後3時ころでした。蝶は見当たらず、案内板からその時期はもう過ぎていると知り、がっかりしました。ふたりはせめて山の風景を見ながら、途中のコンビニで買ったサンドイッチを食べることにしました。
「食べたら、のんびりできないわ。急いで帰えらなければ、ご両親が心配するから」
白い乗用車は山頂から下り勾配の道をいく。
蝶が観られなくて残念ね、ふたりの話題はつきなかった。分岐点があった。集落に入ったけれど、どうも記憶に残る往路の道とはちがう。ここは自分の方向感覚を信じ、能登の西海岸へと走らせた。意に反して山間部となり、だんだん山奥になる。川沿いの舗装道路の先には小さな無人ダムがあった。表示板を読むと、富山県だった。まるで正反対の方角にきたらしい。
少女をはやく家に帰してあげなければ、と麗子は焦った。ダムの先は三叉路で、広い道を選んだのに砂利道となり、そのさきは途切れてしまった。Uターンする。どこにいっても山間の特徴のない道ばかり。麗子は閉鎖的な気持ちに陥った。
検事が証言を遮った。道路標識も、町の名前も、ダムすらも、具体的なものが何一つない。被告人は殺害する意図で、故意に人気のない林道を選んでいたのだと追及した。
弁護人が異議を申し立てた。この段階で、被告人に殺意があったとする検事の主張は合理性に欠ける、と反論した。弁護人の異議が認められた。
被告人の証言がつづいた。やがて針葉樹の道で、山側は伐採で切り開かれた切り株が点在し、谷側は渓谷へと落ち込む、視界が開けた場所にきた。遠く市街地の民家が見えた。安堵をおぼえた。
そのさきは林間でまた視界がなくなった。秋の日没は早く、薄闇となった。車輪がふいに路肩から落ちてしまった。少女の手を借りても、車体は持ち上がらない。
お家に帰りたいと、少女が泣きはじめた。
「いいわよ。歩いて帰りましょう」
検事が、被告人は帰させる意志などみじんもなかったはずだと追及する。よくわかりません。そう答えた被告人に、検事が証言のつづきをうながした。
ふたりは手をつないで歩きはじめた。ライトはなく、荒道の雑草には何度も足をすくわれた。ときには倒れる。闇は深まるばかり。
「ごめんね。車まで引き返して、そっちで夜が明けるのを待ちましょう」
こんどはその車がさがせず、恐がる少女を抱いて野宿となってしまった。夜露が衣服とからだを濡らす。夜風が体温を奪う。真っ暗やみのなかで、木々が風で擦れる音や、夜行性の獣の鳴き声が不気味な恐怖となった。
少女は泣きっぱなし。もう泣かないで、と抱きしめて頬をすり寄せた。少女の体温を感じ、それを意識するほどに、心をとろかす世界があった。結婚生活に破綻した今、このまま少女と永遠の死の世界にいけたならば最高だと思った。暗く長い夜だが、もう夜明けなど期待しない。その願いに反して森が明るくなり、朝霧が樹木の間を流れはじめた。
泣き疲れた少女の顔には生気がなく、いつまでも抱いていられた。やがて、霧が消え、緑の縞模様の陽光が射す。木漏れ陽のしたで、少女の肌が美しく光った。
森の陽光が純真な顔を映しだす。少女のすべてに神秘な魅力を感じた。両手で少女の頬をつつみこみ、唇を重ねあわせた。少女の抵抗は弱々しく、舌と舌がからみあう。気が遠くなるような陶酔をおぼえた。それは途轍もなく深い感動で、精神が昇華していくような、実に甘美なものだった。
「私は少女の虜(とりこ)となったのです。年齢の差とか、同性とか、そんな概念や理屈をはるかに越えもので、夢中になってしまったのです」
白く輝いた少女の肌にはシミがひとつもない。頬や腕がつややかに光る。うぶ毛がタンポポの毛のように、ささやかに歌っている。
「少女を親もとに帰せば、私から離れる。この少女もいずれ大人となり、男に恋する女になってしまう。顔は化粧でほどこし、涙にまみれ、恋に苦しみ、それでも男が恋しくて追いかけていく女になる。それは悔しいことでした。最愛の恋を永遠に失うように。為すすべもない悲しみが、私のからだの芯まで食い込んできました」
この少女はきれいな身のまま、神様のもとにいってほしい。
「私の意思に反し、少女が執拗に家に帰りたがっていました。根負けした私は少女の手をとり、森林の出口をもとめ、歩きはじめたのです」
それはただの彷徨で、空腹のうえ、かすり傷が増え、徒労感がつのっていくばかり。やがて強い雨に襲われた。樹木の枝葉も役立たない雨宿り。寒さから少女の唇は青ざめ、両頬が途轍もなく冷たかった。抱きしめて体温を与える一方で、死の運命を共有させようという意識が胸のうちに一段と膨れあがった。
「少女を永遠に独占したような、甘い陶酔の、抱擁(ほうよう)はもはや押し止められませんでした」
具体的に説明してほしい、と検事がいった。
「私は両手を少女の背中や後頭部にまわし、自分の乳房がつぶれるほど抱きしめていました。陶酔で何時間も。殺すとか、殺さないとかでなく、陶酔で何時間も少女の純真なからだと密着させていました。少女がいつ息を引き取ったのか、記憶にはないんです」
検事から、解剖結果が証拠として提出された。直接の死因は窒息死。被告人は胸もとで衰弱した少女の口を塞ぎ殺害した。鑑定書から事実として実証できると言及した。
弁護人から、雨に打たれつづけた凍死の可能性があると、反対尋問があった。
「私は、死による少女との一体化をもとめて抱きしめていたんです」
弁護人は、死を求めることと、殺害とは結びつかない、本件は殺人でなく、罪状は過失致死罪にあたる、とくり返し主張した。
「雨があがった翌々日から、少女のからだから腐敗臭が漂いはじめました。少女を沢に運び、泥や落葉で汚れたからだを丁寧に洗い、水葬にしました」
水葬か、死体遺棄か。それが公判の量刑を左右するとばかりに、検事と弁護人がはげしく言い争った。犯行当時、被告人は心神耗弱にあったと、弁護人は主張した。
検事が立ち上がった。被告人の意識はしっかりしており、麓まで下山すると、被害者の家に電話をかけたといい、証拠品を提出した。
《娘を預かってるのよ、3000万円用意しなさい》という録音テープをきかせた。
身代金を要求した被告人の声はしっかりしているし、心神耗弱ではなかった。結婚生活に破綻した被告人は自暴自棄になり、旅先で罪もない少女を誘拐し、殺害した。そのうえ三OOO万円を要求した。身勝手で非情な営利誘拐殺人だときめつけた。
電話をかけた記憶はありますか、と弁護人が訊いた。山中を彷徨い、意識が朦朧としていましたから、下山後の記憶すら薄いんです。逮捕されたとき、なぜ高岡のホテルにいたのか、それすらもはっきりしていません。
電話の声紋鑑定が行なわれた。検事側と弁護人側の鑑定結果は真っ向からちがっていた。あとは裁判官がどちらの鑑定を証拠として採用するかであった。
駿一は公判の都度、傍聴席に脚を運んだ。
毎回のように、裁判での女の証言には腹が立った。許されることならば、この手で私刑にしてやりたいと思うほど、激昂したり、憤慨したりして落着きを失っていた。法治国家では、私刑の報復はできない。そのもどかしさがいつも胸のうちで渦巻いていた。
雨の山中で美少女に惚れたから、死をともにしたかったという鳥栖麗子の釈明には言いようのない反発をおぼえた。身勝手な女だ。これでは殺された梨香が無念で口惜しいだろう。……金品を奪ってひとを殺せば強盗殺人で死刑だ。見方をかえれば、人間の魂や心のほうが金品よりも大切。鳥栖麗子は梨香の心を奪うために殺した。物品強奪よりも、より重い刑が科せられるべきだ。
検事は最終弁論で、被告人にたいして営利誘拐殺人だとし、無期懲役を求刑した。
裁判長はきっと被害者の親の心情をくみとり、求刑よりも重い極刑にするだろう、と駿一は心から期待した。
「被告人は前に」
裁判長がいった。………主文を言い渡します。被告人を懲役8年に処す。
「娘を殺しておきながら、なぜ8年だ」
駿一は我を忘れて叫んだ。
裁判長から注意をうけた。駿一は、判決を聞き入る麗子の背中をにらみつづけた。
法廷では裁判長の声が淡々とひびく。……罪もない少女を殺害し、ひとり娘を亡くした被害者の家族の心情を汲みすると、被告人が背負うべき罪は重い。事件当時の被告人は心神耗弱の疑いもあるが、善悪を判断できる状態にあった。誘拐は計画的であった。雨で抵抗力の衰えた少女を、殺意をもち、胸もとで殺害した罪は重い。初犯で、被害者はひとりだった。電話での金銭要求は麗子本人でないと退けた。よって8年の実刑判決となった。
「なぜ死刑にできないんだ。人殺しの女をなぜ娘とおなじ目に遭わせない。不公平だ」
再度、厳重注意をうけた。
「梨香をもどせ。ここに連れてこい」
退廷を命じられた駿一は、裁判所の官吏に連れだされた。一般待合室のベンチで、駿一は口惜しく身体を震わせた。
その後、弁護士は被告人に、事件当時は心神耗弱の状態だったのだから、量刑不服として控訴するべきだと勧めたらしい。しかし、彼女は控訴を拒否したという。
一方、検察側は営利誘拐の電話鑑定が証拠として採用されなかった、事実認定がちがうと控訴したのである。
二審でいくら争ってももはや死刑はないのだと、駿一は高裁に一度も脚をむけなかった。詳細はわからないが、営利誘拐殺人だという検察側の主張が認められ、鳥栖麗子が一五年の懲役刑となったと新聞が小さく報じていた。
出所した鳥栖麗子が土岐造船所に現れた日から、考えるほどに駿一の心は乱れつづけた。精神が北前船づくりに集中できなかった。
(来春の引渡し期限は大切だ、守るべきだ。大工道具をもったら、犯人のことは忘れろ)
かれは自分にそう言い聞かせた。心の乱れがやや静まると、重要な帆柱の台座づくりに取り組んだ。船体中央には繊細な寸法にして、頑丈な台座が出来上がった。ほぼ行程通りで、蝉の鳴き声が裏山から海岸までなだれ落ちる季節になっていた。
かれは全長14メートルの船内で、床下を客室、エンジンルーム、倉庫などに仕切る《戸立》の作業に入った。
ある日、チャがしっこく吠えはじめた。船内から顔を出した駿一の目が、日傘をさす鳥栖麗子の姿をとらえた。かれは無視した態度で、船造りに専念した。彼女は無言を共有するように何時間もたたずむ。
時折り、かれは薄気味悪い女だという目をむけたが、なお立ち去る気配がない。駿一の神経は苛立つばかりで、癇癪を起こした。
「そうやって、罪の許しを乞いにきているが、娘を殺された親の気持ちがわかるのか。おれが許すといえば、さっぱりする、そうおもって来てるんだろう」
「許しを乞いにきたのではありません。つぐないをさせていただきたいんです」
「おなじことだ。なんど来たって仏壇に線香の一本もあげさせないからな。それで罪が解消されたら、あの世の梨香がかわいそうだ」
怒鳴り散らすと、彼女は暗い表情で帰っていった。かれの心には苛立ちだけが残った。
戸立の作業は盆前に終った。海から照り返す太陽の熱射が毎日きびしい。かれは上半身裸で、外艫(そとども)の製作へと進んだ。これが完成すれば、北前船の特徴あるシャチの尾のような船尾になる。追波の衝撃に耐えるためにも、内側に強度のある補強材が欠かせない。
駿一のからだがいままで暑さを気にしていたが、建造に夢中になっていると、時間の経過が早く、いつしか初秋の鬱陶(うっとう)しい長雨に入っていた。船尾の形状が整えば、来週にでも外板を張る予定だった。
チャが建物の軒下で、濡れない程度に胴体を横たえていた。先刻から気怠るい目で、雨合羽を着た駿一のしごとをみていた。
水色の傘をさす麗子がまたもや現れた。チャは女を一瞥するだけで、吠えることすらも放棄していた。麗子は雨宿りのように、吹抜けの製図場に入った。会釈したあとは見物人の目で、駿一の働きぶりをみていた。
「いいか、おまえは娘を殺した極悪人だ。神が裁けば死刑だ。それとも梨香が森のなかで家に帰りたくないとでもいったのか」
かれは建造中の艫から怒鳴った。
「帰りたがっていました。とても」
「それなのに梨香を殺した。この場で、おれが裁いてやろうか。梨香は抵抗し、帰りたいと泣き叫んだはずだ」
駿一は建造船から飛び降りると、また彼女に鑿の刃をむけた。前回の怒り心頭とは違い、船大工が神聖な道具を殺戮の凶器にして血で汚すとは、職人魂が廃る、と恥じる余裕があった。かれは鋭い刃先の向きを変え、棄材に突き立てた。怒りがおさまり切れず、
「裁判で、なんていった。梨香と死を共有するだと。ふざけるな。てめえだけが生きて帰ってきゃあがって。卑怯者」
「おっしゃる通りです。梨香ちゃんを殺しながらも、自分の生命が断てなかった女です」
「おまえはずるい女だ。つぐないとはさいなまされる罪から逃げることだ。梨香が殺される寸前の恐怖を考えれば、毎日、毎日、自分は人殺しだと思い、苦しめばいいんだ。悩んで悩みぬけ。仕事のじゃまだ、帰れ」
と怒鳴って追い払った。
それから半月後のある日、駿一が二階の事務所で、船舶エンジンの代理店から届いた機械図面を拡げ、機械台に据える位置の精緻な寸法を書きとめていた。
かれの視線がふいに窓下に流れた。麗子が門柱のそばで、チャの頭をなでていた。彼女が茶袋から缶詰をとりだすと、興奮したチャがやたら尻尾を振り、彼女の回りを駆け巡る。
「チャのバカが人殺しになつきやがって」
とつぶやいてから、駿一は携帯電話で新潟の鉄工所と連絡をとった。……まだ半年先になるけれど、鉄工所側が進水前におこなう機械据付の日数とか、こちらが事前に用意する機械台のサイズとか、進水式後の試運転の段取りとか、諸々の確認をおこなった。
打ち合わせが終ると、かれは二階事務所から外階段を降りてきた。麗子が作業場のなかで、風で散った鉋(かんな)葛(くず)のはき掃除をしていた。
「余計なことするな」
すみませんでした。彼女は竹箒を壁面に立てかけた。塵取りのゴミだけは、焼却炉代わりのドラム缶に入れていた。
駿一はエンジンルームの寸法に見合う角材を選び、図面から落とし込んだサイズを鋸で切りそろえた。なおかつ四面は鉋で削り、より精緻な寸法にした。それを建造船に運び込むと、機械台としてはめ込んだ。そして、建造船の真下に潜り込み、船底から機械台へとボルトを通す。狭い場所で窮屈な作業だった。ここは機械台をしっかり固定させておかないと、運航時にエンジンの震動で、不具合が生じる。重要なポイントだ。
麗子がしゃがみ込み、こちらの作業をじっと見ている。彼女は一日中ここで過ごすつもりなのか、昼時になると、近くの防波堤で弁当を広げていた。チャが彼女のまわりで、弁当を欲しがる甘えた声をあげていた。
午後からの駿一は、船底から冷却水を取り込む円い穴を空けた。つぎは上棚にエンジンの排気管を通す作業に進んだ。
「すこし、お話をしてもいいでしょうか」
かれは無言で鑿に神経を集中させていた。
「私の話題といえば、ここ十数年来の刑務所の出来事しかないんですけど……」
彼女は独白の口調で語りはじめた。
女子刑務所は当然ながら、年齢も犯した罪も刑期もみな異なる受刑者の集まりで、自由のない、規律だけの拘禁生活だった。
当初はそんな環境になじめず、眠れず、食事もとれず痩せ細った。……裁判所の傍聴席から、梨香をもどせ、ここに連れてこい、と叫んだ父親のことばが脳細胞に根を張り、頭から離れなかった。取りのぞきたくても、取りのぞけず悶々としていた。
少女を死に至らしめた罪の意識が膨らみ、舎房内で自殺を図った。未遂だったが、懲罰をうけ、要注意人物として二四時間の監視のもとに置かれた。
懲罰が解かれると、運動場に出ることが許された。日溜りの一角で、担当の女子刑務官から、自殺は苦しみからの逃避よ、どんな場合でも希望をもって生きなさいといわれた。
歳月は人間を順応させる。収容生活が日常のものとなった。独房の刑作業から一段すすんで所内工場に出業し、働けるようになった。
カウンセリングの場で、新たに担当となった女性刑務官に胸のうちを打ち明けた。
罪は罪として、あなた自身が更生すること、それがつぐないになるのよ。15年の刑だけど、がんばって仮出所がとれたら、あなたにも再婚の機会ができるし、年齢的にも母親になれる可能性があるわ。一日も早く社会復帰することね。わが子を奪われた被害者の痛みを感じ、しっかり生きていくことよ。
「私は自分の将来や幸福よりも、ご親御さんにつぐないをしたいんです」
なにを、どのような方法で? 担当は受刑者と視線の高さを合わせた態度で訊いた。
「名案も良策も思いつかず、ただ苦しんでいるだけなんです」
仮出所できたら、月に一度はお墓参りしてあげなさい、と担当はやさしい口調でいった。
「線香をあげさせてもらえるでしょうか」
傍聴席で叫んだ父親の姿を思いうかべると、麗子は否定的な気持ちになった。
あなたの努力と誠意しだいよ。
「担当さん、真のつぐないとは何でしょう。 天国から少女を呼びもどせるものなら、そうしたい。親御さんにお子さんをお返ししたい」
あまり力まないほうがいいわよ。まさか産んで返すわけにもいかないでしょ。つぐないには限界があるのよ。いまは将来への希望を持つこと。服務態度が良ければ、それだけ早く社会に復帰できるのだから。
「ありがとうございました」
このまま刑務所に居ては罪をつぐなうことができない。これを機に仮出所を目標にがんばろうときめた。規律一辺倒と囚人仲間とのむずかしい複雑な人間関係のなかで永年、努力に努力を積み重ね、模範囚にまでなり、仮出所が決まったと語る。
「もう止めろ。耳障りだ、帰ってくれ。精魂こめて船を造ってるんだ。仕事のじゃまになる。言っておくが、勝手に梨香の墓参りにいくと、許さないからな」
駿一は強い口調でいった。
「線香もダメでしょうか」
「当然だ。娘を殺しておきながら、立派な模範囚ぶりだったと話されると、むかむかしてくる。梨香はあの世であんたを恨んでるんだ」
早く、帰れ、とかれは苛立って怒鳴った。
駿一は解消できない鬱憤を抱え込んでしまった。ここは気を引き締めるためにも、突貫工事なみにからだを酷使することにきめた。週に一度の休みもなく働いた。その結果、防舷台(ぼうげんだい)の取付けへと順調に進んだ。 それは長い角材を舷側の上棚に取付け、船を一周させる船体の補強である。
かれはまず防舷台の曲がり部分と、直線部分と、四つに分けた部材として製作した。据付となると、クレーンが使えない。ここは人手がほしいところだけれど、節約で日当払いの臨時工をたのまず、独りで試みた。
3本の丸太をやぐらに組み、ホイストで防舷台の曲がった角材を吊り上げていく。上棚の面とおなじ高さになると、下からつっかえ棒で支える。そのうえで、防舷台を船体に仮止めする。独りでは一つひとつ手間がかかる。
鳥栖麗子がやってきて、この防舷台の作業をみている。直線部材の防舷台を持ちあげたところ、ホイストのフックが突然くるくる回りだした。傾いた角材の下で、駿一の身体が転倒してしまった。麗子が咄嗟に斜めに落ちてくる角材の下につっかえ棒を入れてくれた。
「下敷きになるところだった。助かった」
かれは素直に礼をいった。
「自分でもふしぎです。敏捷でもないわたしが、とっさに手が出たんですから」
麗子がはじめて微笑をみせた。
危険な目に遭ったかれは、急須に湯を注ぎ、お茶を一杯飲んで気持ちを落ち着かせた。
「この際だ、事件についてひとつ訊きたいことがある。前まえからの疑問だが、警察に捕まるまえ、わが家に3000万円よこせと、あんたは脅迫電話をかけてきたのか」
「……。二審の冒頭で、私はそれを事実として認めました。はやく刑に服したくて。本当のところは一週間も山中でさまよい、意識が朦朧とし、記憶に残っていません。警察や検察で、おまえの声だ、おまえの声だといわれると、そうかもしれないとおもっただけです」
「梨香は電話番号をおしえなかったのか」
「真っ暗やみの森のなかで、恐さと寒さに震えるふたりでしたから、電話をかける話題など出てくるはずがありません」
鳥栖麗子の話ぶりからしても、信じてもよさそうだ。録音機を取りつけた刑事が、悪戯電話だろうな、マスコミ情報しかないから、とつぶやいていた。駿一もとっさに女の声が三十代半ばだと思った。営利誘拐の面では、彼女は部分冤罪なのだろう。
「私は判決とか、刑期とか、そんなことは問題にしていません。何かしらのつぐないをしたいんです、その一念です」
この女は仮出所された身だ。事件から逃げてしまえばいいものを、と駿一は考えた。
かれはふたたび冷淡な態度にもどり、いまは突貫で観光船を建造している、あんたの相手をする暇はないと手で追い払う真似をした。
麗子の足運びは悪く、角材に躓いた。こちらの視線に気づいたらしい。
「刑が確定するまで拘置所に拘禁され、朝から晩まで静座をもとめられる生活でしたから、膝を悪くしたんです」
「いま、どこで働いてる?」
「富山です。無期懲役の仮出所のわたしですから……、保証人もいらない場末の職場です」
彼女はあまり語りたくない態度でスカートの泥を払うと、海岸通りをいく。
麗子と前後するように、寅吉がやってきた。
「どうだ。北前船は予定通り進んでおるか。来春の引渡しは大丈夫だろうな。人手がないらしいから、心配で寄らせてもらった」
寅吉の目はことばに反し、別段心配したようすでもない。
「約束どおり進水させる。いまは娘の供養のつもりで、懸命に造っている」
「そうだろうな、駿一の目の輝きがちがう。……、杉の香りと艶はいいな。やはり船はプラスチックじゃなくて、木造だ」
鮮明な杉目を掌で摩ってから、寅吉が意味ありげな視線をむけてきた。
「後妻が決まったようじゃな」
「だれの?」
「おとぼけだな。このところバスに乗って福浦まで、女が通ってきてるそうじゃないか。さっきの女がそうか。噂だと、加奈子ちゃんの七回忌が終ったら、祝言だときいたぞ?」
寅吉の記憶には、十数年前に新聞をにぎわした犯罪者の顔写真など残っていないらしい。
「祝言だなんて、とんでもない」
「細身で器量がよくて、好い女じゃないか。でも、ちょっと冷たい感じだな。いずれ、この町で住むなら、こそこそ逢引しないで、町なかの衆に会釈とか、挨拶くらいさせておかないと、再婚後がうるさいぞ」
「あの女は都度、追い払っているけど、つきまとっているだけだ」
かれは麗子の素性を打ち明けられなかった。
「照れてるな。さっき造船所をのぞいたら、女が防舷台の下に、つっかえ棒を入れていた。仲がよさそうじゃないか。邪魔したら悪いとおもい、時間をずらせてきた」
駿一は返すことばがなかった。半時間ほど、寅吉が船体を吟味してから帰っていった。
麗子がまた造船所に現れた。この頻度では町の噂にならないほうがおかしい。これまでの粗末な衣服とは違い、刺繍つきのアンサンブル・ブラウスと薄い緑色のフレアースカートを着こなす。化粧した柔らかな頬の線と細長い首筋とがくっきりうかぶ。これまでにない若返りした艶っぽさがあった。
彼女は門柱の内側で、こちらに会釈してから、チャに餌を与えた。そして、建造中の船に近づいてきて、手提げ袋から、陣中見舞いです、と包装された細長い箱をとりだした。新潟のお酒だった。
「娘を殺した女から、贈り物をもらう筋合いはない。梨香の位牌を見ながら、あんたからもらった酒を飲めるとでもおもってるのか」
「受け取ってもらえないでしょうか」
麗子が失望の淋しい目をむけた。
「娘を殺したという自覚があるなら、ここにいっさい来ないでくれ。他人(ひと)の目もある」
といっても、彼女はすこし離れただけで、立ち去らず観光船の窓枠の作業を見ていた。
鋸を挽く駿一の目が時折り彼女の豊かな胸、腰、ふくらはぎへと流れた。女のからだから発散される、甘酸っぱい匂いを感じ、熟れた裸身を想像してしまう。娘を殺した麗子への敵意や怨念とは別のところで、性的な刺激を与えられて困ってしまった。
(ばかやろう。おまえの娘を殺した女なんだ。そんな女に情欲を感じるなんて、最低の男だ)
かれの心のなかで、自分を怒鳴っていた。「早く帰れ」
かれは語調を強めた。ごめんなさい、と酒を持ってきたことを詫びて立ち去る。駿一にすれば、艶かしい容姿で、独り者の男のところにきたことを詫びてほしかった。
駿一は夕暮まで性欲をもてあます自分を知った。自制そのものが苦痛で、昼間のしごとも身が入らず、夜も眠れなかった。数日間は モヤモヤした気持ちから、単純な作業に切替えた。舷側の板と板の隙間に、浸水防止のヒノキの皮でできた《まきはだ》を埋め込む作業だった。
それが一通り完了すると、気持ちが建造に集中してきた。観光船の窓の製作に入った。防舷台から一段高く、格子の欄干に似た垣立(かきたつ)に、三尺ごとの窓を設けていく。窓枠の支柱はかぎりなく細くした、観光客の視界を広げる構造設計だった。
山頂のブナ、ミズナラ、コナラなどの紅葉が終り、大半が裸木になってきた。飛来してきた枯葉が建造船のまわりで、カサカサ音を立て踊る。鳥栖麗子がやってきた。
「何度きても、線香の一本もあげさせないぞ」
「お怒りになるかもしれませんが、私にできるつぐないは、血の通う子をお返しすることだとおもいます」
彼女は真顔だった。
「他人の子をもらって、どうする?」
「私は仮出所のまえから、罪のつぐないを考えあぐねていました。看守が『まさか産んで返すわけにもいかないでしょ』という言葉から、ひらめきをおぼえたんです。真のつぐないとは、土岐駿一さんの子を産み、梨香ちゃんとおなじ10歳まで育て、こちらにお返しすることだと考えたんです」
麗子は悶々とした歳月のなかで、やっと、つぐないへの道に辿り着けたとくり返す。
「冗談じゃない。そんなのが罪のつぐないか。正気とは思えない」
「半分はあなたの血を引く子です」
「おれは梨香を殺した鳥栖麗子という女が許せないんだ。それなのに、あんたの肉体を抱けるとおもうのか」
駿一は端材を蹴飛ばした。仮想と現実との境目を見失っている、とつけ加えた。
「そうでしょうね」
彼女は肩の力を落として帰っていった。
子どもを産んで返す。それを拒絶されたからだろう、鳥栖麗子は一度も現れていない。化粧をすれば見栄えのよい女だし、大都会の生活に吸収されたのだろう。
造船所のなかが妙に閑散とした仕事場に思えてきた。チャが相手になるだけである。
甲板が完成した。このさき雨や雪が降っても、内装のしごとが進んでいく。年を越すと、客用ベンチは寅吉の要望から、特別に桧をつかった製作に入った。船尾にはタイル張りの水洗トイレを完成させた。
艫(船尾)の甲板には帆のロープを巻きあげる轆轤(ろくろ)を作った。これで帆桁(ほげた)を上下させるとなると、乗組員の数が増えることから、単なるイミテーションだった。実際はボタンひとつの電動式で、かんたんに帆が張れる仕組みだった。
桜の蕾が膨らんできた。帆船の象徴である念願の帆柱の立上げができた。青空に屹立すると、臨時工たちが感動して拍手してくれた。
進水式が来週に近づいた。船体の塗装は指図だけで、臨時工に任せた。駿一は神主の手配とか、祝宴のテーブルの手配とか、紅白幕とか、もろもろの準備で追われた。
昼前から雨が降りはじめた。かれは神社の社務所で打合せした帰り道、梨香が誘拐された、木造四角形の灯台に立ち寄ってみた。そこには傘をさす女が海を見つめていた。自殺を図りにきたのか。そんな雰囲気が背後から感じられた。車を停めると、女はこちらに気づいてふり向いた。鳥栖麗子だった。
彼女の頬が濡れていた。滴る雨粒でなく、涙だろう。かれは透明のビニール傘をさして車外に出てみた。無言で頭を下げた麗子の顔にはずいぶん暗さが漂う。彼女の視線がふたたび雨雲でかすむ海洋に流れた。
駿一がひたすら彼女の横顔をみていると、
「この海で、いま死んだら、私の魂は何色に染まるのでしょうか」
「あんたが海で死ねば、魚が賛美歌でもうたってくれるとでもおもってるのか……」
かれの口からは思わず気取ったことばが出た。それにたいして彼女は無言だった。
「おれはこれまで、あんたには殺された利香と同じように死でつぐなってほしいと考えてきた。それは偽らない気持ちだ。しかし、人間とは不思議なものだ。何度も訪ねてくるあんたをみていると、多少気持ちが変わった」
憎しみはやや弛んできたと暗に伝えたつもりだが、婉曲な表現では意図が伝わらないのか、彼女の視線は海から外れなかった。
「十三回忌をすませたし、梨香の事件はもう深く掘り下げる気などないが、あんたはなぜ横浜から北陸までやってきた? 裁判では離婚の失意で旅に出たと証言していたけど」
「私は自分の不注意から、2歳の息子を死なせてしまったんです」
そう前置きしてから、状況の断片を語った。
勇輝と名づけた子は順調に育ち、いつも親のやることを真似たがる二歳となった。常日頃から、危険な包丁や鋏などは勇輝の手が届かない棚に置いていた。ある日、麗子がベランダで洗濯物を干していると、階下から勇輝の悲鳴が聞こえた。
「思い出すだけでもぞっとします。勇輝が電気ポットの注ぎ口に口をつけ、給湯キーを押していたんです」
100度の熱湯が息子の口腔から気管、肺臓まで流れ込み、瀕死の状態だった。そのうえ、倒れ落ちた電気ポットの上蓋(ふた)が開き、全身に熱湯を浴びていた。
麗子は発狂したかのように泣き叫び、子どもをかかえた。救急車で病院に運ばれたが、数時間後、勇輝は息を引取った。
「その後、子煩悩(こぼんのう)だった夫の生活は乱れ、帰宅はたいてい深夜で、泥酔状態でした。やさしさもなくなり、勇輝を死にやった罪を責めらたてられました。挙句の果てには離婚です」
彼女は話しに間を置いてから、こういった。
「離婚は致し方ないとしても、熱湯で死んだ子の痛ましさを想うと、母親の自分が生きていること自体が罪だと考えました。死ぬ場所を考えた末に、断崖絶壁と荒海の能登半島にきてみたんです。この灯台の下で、梨香ちゃんに出会ったことから、事態がとんでもない方向にいってしまいました」
裁判では、弁護士が検事と誘拐殺人の事実関係ではげしく争っていた。このあたりの鳥栖麗子の情状は強調されず、通り一遍だった。
駿一すら娘を殺害した犯人への恨みから、鳥栖麗子の酌量に耳を傾ける気などみじんもなかった。いまとなれば、わが子を亡くした心の痛みを知る彼女に同情する面がある。しかし、かれはただ黙って聞いていた。
「……。ひとさまの子までも死に至らしめた罪深い私です。梨香ちゃんへのつぐない、それが生きている唯一の理由でした。刑務所で何年間も、苦しみ悩み考えた末に出た結論がありました。何度か造船所にお邪魔しても、私の子宮(からだ)を提供し、土岐駿一さんの子を産み、お返しをしたいと、なかなか切り出せずにいました。昨年の秋、勇気をもってお話したところ、突飛もない発想だと、あざ笑われました。それから半年間、他の方法を考えても、つぐないの妙案はありませんでした」
「それで、きょうここに死に場所をもとめてきた、というわけだ」
「はい。いいところで、お会いできました。あしたには、私のつぐないが見届けられます」「あんたは真からの悪人じゃなさそうだ。一途に梨香へのつぐないを考えつづけてきた、真面目なひとだ。おれはこれまで、鳥栖麗子は誘拐殺人犯だ、極悪人だときめつけていた。いつまでも罪を許さず、自殺に追い込んだら、残るおれの人生が暗いものになる。きょうはこれから車で、わが家に案内するから、梨香に線香をあげてやってくれ」
というと、耳を疑った表情のあと、麗子は肩を震わせ、嗚咽を洩らした。よほどこの日を待ち望んでいたのだろう、彼女の横顔をのぞく駿一も胸にジーンときた。
15分後、駿一と麗子は仏壇がある八畳間の和室に入った。麗子は鴨居にならぶ妻子の遺影を一瞥し、線香を立てた。鉦を鳴らし、長く手を合わせた。
彼女が梨香の遺影をみつめた。
「助けてあげられなくて、ごめんなさい」
それは殺人者の言葉に思えなかった。
「あんたは胸もとで、窒息死させたのとちがうのか」
「いまさら信じてもらえないでしょうけど、私は死の道連れにする気など、毛頭ありませんでした。いま遺影の梨香ちゃんに証人になってもらい、すべてお話します」
裁判で証言した、白い車の車輪が路肩から落ち、あちらこちら彷徨するうち、太陽は沈み、方向を見失った。そこまでは事実です。
麗子は手を取り合った梨香に何度も、ごめんね、怖い想いをさせて、と謝った。暗くなった山奥で、下山道を見つけるのは無理。一晩の野宿と麗子はきめて梨香に伝えた。
『離れないでね、一人ぽっちになると怖いから。ぜったいよ』
もちろんよ。梨香ちゃんをお家に帰すまで、手を離さないわ、とつよく握り締めた。
『山で迷ったらね、葉っぱを一杯かぶって寝ると、暖かくて死なないんだって』
父さんがおしえてくれたの?
『ちがう、母さん。茸狩りの山で迷うひとがいるんだって。落葉が夜露で濡れないうちに、掛け布団にすると、助かるんだって』
よく知ってるのね、心強いわ。私は横浜育ちだから、森や山のことは疎いの。いろいろおしえて。ぜったい家に帰してあげるから。
枯葉を集めたふたりは、大樹の下で野宿に入った。夜風の音が不気味で怖かった。
お話しをしましょう、黙ってると怖いから。学校の成績から、訊いてみようかな。
『いやな質問ね、先生みたい。体操が一番好き。次が絵なの』
梨香ちゃんが大人になったら、オリンピック選手か、画家か、どっちになるのかな。
『花嫁さんになるの』
すてきなお嫁さんでしょうね。可愛いお顔だし。私も観てみたいわ。
「父さんがお祝いに、梨香に花嫁さんの船を造ってくれるのよ。櫓(ろ)を漕いで、花イカダの海にきれいな花道をつくるんだって」
花吹雪の散った海って、すてきでしょうね。
『結婚式にきてくれたら、お船にいっしょに乗せてあげる』
うれしいな。
夜が明けると、梨香は活発な少女にもどり、木に登ってアケビを取ってくれた。少女は森の精のように、身軽く森林の急斜面を登っていく。早くおいで、と手を振る。
『山で迷ったら、谷に下りないで、山の頂上に行けば、助かるのよ』
どうして?
『山の頂上はたいがい道があるんだって』
無名の山頂には、少女のいうとおり細道があった。下山をはじめたが、踏み跡が途中で消える細い径だった。雑草や張出した枝や雑草の刺が行く手を阻んだ。それでも進んだ。
夕方からの雨は最悪だった。樹の下でも雨宿りとはならず、全身がびしょ濡れ。昨夜と同様に枯葉を集めて頭まで潜りこんだ。夜半には豪雨になった。全身に悪寒が走った。
2日目の夜が明けても雨は止まず、行動する気力すら奪われた。少女にかぶさる落葉がぶるぶる震える。麗子は梨香の冷たい手足や顔を擦ってあげた。山で迷ったら歩き回らない。それが鉄則と聞いたことがある。
『死ぬの』
少女が涙を流した。
ぜったい助かるから、泣かないで。ここから動かなければ、捜索隊がきてくれるから。
そんな励ましの言葉をむけるが、その実、捜索隊がこんな手がかりのない場所を見つけられるのかしらと、麗子は絶望感に襲われた。
梨香の衰弱が目に見えてわかった。話し掛けても、精気が取り戻せない。麗子も体力の消耗がはげしく、梨香をマッサージしながら睡魔に襲われた。はっと気づいて、梨香の顔をのぞき見る。少女の唇は真っ青で、目線も虚ろで、呼びかけても、意識が朦朧としていた。……このままでは、少女が死んでしまう。
麗子は泣きたい心境だった。またしても眠気に襲われた。野宿は3晩か、4晩か。時間の感覚がなくなった。森林のなかに夜明けの気配が漂う。麗子はカラスの集団の鳴き声を聞いて、はっと目覚めた。
濡れた枯葉が梨香の顔を塞いでいる。麗子は少女の口や鼻から落葉を払い除けた。からだを揺すってみたが、反応がない。呼吸の気配がなく、慄きが麗子の全身を走った。
少女の心臓は停止していた。ごめんね。ごめんね、と少女のからだにかぶさって泣いた。
仏壇の前で、じっと耳を傾ける駿一は、小矢部川で発見された梨香の遺体を思いうかべた。口唇からカエデの葉が出ていた。それと重ね合わせたならば、直接の死因は落葉による窒息死だろう。麗子が胸もとで殺した殺人でなく、事故死だ、と駿一は見方を変えた。
「死後のお話をしても、いいでしょうか」
この森に少女を残して離れれば、地理や方角はわからないし、だれにも場所を示すことができない。森のカラスが集団でおそろしく鳴いている。あの嘴で、少女のからだが啄ばまれてはあまりにもかわいそう。ここは沢を見つけて梨香の遺体を流せば、河口に辿り着ける。ひとの目にふれて遺体が家に帰れる。
「たとえ、死後とはいえ、私は梨香ちゃんを心から自宅に帰してあげたかったんです」
彼女はハンカチで目をぬぐった。
「梨香の遺体は下流で受けとれた」
「それだけは願いがかないました」
「あんたは嘘をついてない。女房の加奈子は梨香に山で迷ったときの心構えをよく話していたものだ。婚礼の伝馬船も、花筏の話も事実だ。なぜ警察に真実をしゃべらなかった?」
「話しました。最初は何度も……。逮捕容疑は誘拐殺人です。殺意をもって窒息死させたと思い込んだ刑事は、真実を語れば偽りだといい、責め立てました。私の愚かな行為が死に到らしめたことは事実です。殺したも同然なんです。その罪をつぐなうためなら、どんな刑でも、死刑でもいいと考えました」
殺したも同然と、殺人とは明瞭にちがう。罪状や刑期は異なる。裁判の傍聴を通して駿一にもわかっていた。
「作り事の自供だと、素直だ、その調子だといい、刑事は書き綴っていました。できあがった供述調書には不満も残り、反発もおぼえました。でも、心にきめるものがあって拇印を捺しました。私は裁判で、梨香ちゃんを聖少女のように、美しく語り、法廷記録に残してあげよう、ときめたんです。事実、溌剌と森の精のようでしたから」
裁判の証言人席で、少女を語るうち自己陶酔から、少女とのキスへと話がおよんでしまった。同性とのキス。裁判記録のなかで、かえって少女を汚してしまったと、いまでは後悔になっているという。
「宝達山で直接手をかけて殺さなかったにしろ、梨香を誘い出した以上、あんたが無実とはおもえない。しかし、梨香は森のなかで、あんたに心を許し、婚礼船の話しまで聞かせている。おれはいま梨香の船のつもりで魂を込め、観光船を造っている。もうすぐ進水式だ。2週間後、この港に訪ねてきな。おれといっしょに花筏の海で、梨香を供養してやってくれ」
「いいんですか。本当に」
彼女の口調が半信半疑ながらも、その目が光った。
「天国の梨香は花筏の海で、あんたと再会したがっていると思うよ」
窓から急に陽が射し込んできた。雨雲の切れ間から青空がのぞいていた。
翌週、紅白幕が張られた門柱には《進水式》の立看板があった。拡声器から軽快なマーチが流れる。近隣の住民も集まり、ある種の祭り騒ぎだった。神主のお払いがすむと、駿一と臨時工がウインチを利用し、新造船が乗った船台を動かす。船台はレールに沿って海底に沈みこみ、船体が満潮の海にうかんだ。
見事な北前船じゃ、よくやった、と寅吉が褒め称えてくれた。駿一は胸が熱くなった。
進水式の夜の祝宴では、駿一は鼻が高かった。思いきり呑んだ。
機械メーカーが中心となった試運転が完了した。その2日後、チャが甘えた鳴声で、造船所の門外まで駆けだした。そして、ハーフコーを着た麗子を連れてきた。
「きょうは受け取っていただけますか」
麗子が祝い酒をさしだす。ふたりの足元で、チャがなおも興奮状態で駆けまわっていた。「気を使わせたな。あんたがいつ来るのかと、気をもんでいたところだ。あした新造船が船主に引渡されるから、リミットだった」
「間に合ってよかった。保護司から、頻度の問題で許可がすぐに出なかったんです」
「いろいろ大変なんだな。きょうは梨香の婚礼の伝統行事だ、北前船のように帆だけで航行させる」
かれは乗用車に麗子とチャを乗せてから観光船乗場に案内した。海に突き出た細長い桟橋から、駿一が麗子に手をそえて金剛丸に乗り込ませた。チャは一足で飛び乗り、舳先で前足を突っ張り、気取った姿勢をとった。
出帆だ。錨をあげたかれはマストに白い帆を張った。帆船が海面を滑りはじめた。操船する駿一に寄り添うように麗子が立つ。
福浦港の岬をまわると、観光船の運航ルートにそって北にいく。波間では海鳥がブランコのように上下にゆれて遊んでいた。右手には美観の断崖がつづく。潮流が速くなった。金剛海岸は千石船の時代、難所の一つだった。
速い潮流と入り江からの緩慢な潮が岩礁のまわりで合流し、複雑な動きをする。海面が渦巻き、波が立つ。エンジンを使えば、かんたんだが、かれはどこまでも帆走に拘泥した。
「帆船としての処女航海が終ったら、江戸時代からつづいてきた土岐造船所は廃業だ」
「もったいないはなしね。いろいろな帆船を復元させたら、すてきだとおもうけど?」
「木造船の建造は経営として成り立たない」
はげしい潮流の岬をまわりこむと、白い砂浜の湾曲となった。海面には周辺の老松が写り、浅い海には小魚が群れて回遊する。入り江の奥にむかうと、山桜の花弁が青空の下で吹雪いていた。潮流で集められた桜の花弁が海面に無数に張りつく。
「海から観る花筏はすてきね」
彼女は感動を語る。
駿一は目を閉じた。……梨香の花嫁衣裳に花吹雪が舞う。花筏の海にも婚礼の歌が聴こえる。金槌のひびく造船所もうかぶ。
それらがみな消える現実の寂しさを感じた。
「帆船造りの話しだが、残れた人生の取組みとしては面白いかもしれない。漠然と建造していては魂が入らない。あんたの息子、勇輝くんといったかな、その児の供養船を受注したつもりで造ってみるか」
「建造費はずいぶんかかるんでしょ」
「金の心配は無用だ。おれは生活のためにまたどこか勤め先を見つける。休みのたびに、勇輝丸の建造に精魂傾けるだけさ。進水は何年先になるかわからないが……」
かれは決意を固める口調でいった。
「私も、建造費の一部がつくれるように、一生懸命に働きます。ときどき勇輝丸の進み具合を見に、造船所に訪ねてもいいですか」
「断る理由はない。息子さんの供養の船だ。ただ、町の派手な噂にならない頻度にしてくれよな」
「田舎はうるさいんでしょ」
彼女は生き甲斐が見つかったような、さわやかな表情だった。
「まあ、な。沖の潮の流れが変わった、もどるぞ」
駿一が一枚の帆に風を集めた。加速がついてくる。海の花筏で泳ぐ親子の鳥があわてて飛び立つ。子どものほうは海面ぎりぎり幼稚な飛び方で逃げていく。
……父さん、新しい船ができたら、また花筏まできてね。
梨香の声が聞こえたような気がした。かれはもう一度耳を澄ませた。風の音か、梨香の声か、それはわからなかった。
ふり返ると、花筏には船脚があざやかに引かれていた。