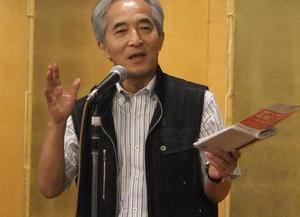反骨精神、臨書の展覧会=東京・銀座
書宗院展が東京・中央区二丁目の「東京銀座画廊・美術館」で、7月20日から6日間にわたって開催された。古典を手本して書いた、「臨書」の作品を集めている。昭和32年から年1回実施され、今回で54回である。
過去の開催は武道館、中野サンプラザ、銀座画廊などである。なぜ銀座なのか。
芸術の森の上野では、書の大展覧会が開催されている。それらは創作もの重視である。臨書は物まねだ? として受け入れていないからだろうと、同展の作品解説者は説明する。
書の古典は長い時間をかけて鑑賞に堪えてきた、芸術性の高いものだ。最古は3500年前の中国から伝わるものもある。
芸術・文学はすべて古典から学習する。どの世界においても、先人に学び取る姿勢が大切だ。書の場合は、とくに初心者は古典を手本にして、筆の運び、筆の動きができるようにする。
「臨書は奥行きと幅が広い」と吉田翠洋さんは語る。
一通りの筆遣いが出来たならば、手本から離れ、創作ものに移る必要があるのだろうか。どこまでも臨書の世界を追求する姿勢、古典に近づく、それを越えようと筆を執る。それはあるべき一つの書の道だろう。
それはもはや真似事とはいえない。創作もの書道との差はない。