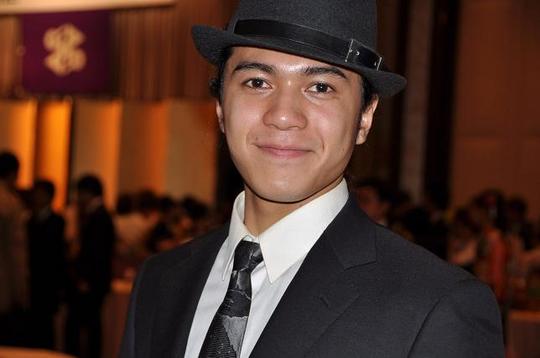死刑囚の首は誰が絞めるの?
私には、『獄の海』という文学賞の受賞作がある。当初は、死刑囚を書くつもりだったが、とても書けないと解ったから、少年受刑者を主人公にした作品である。選者の藤本儀一、田辺聖子、眉村卓、難波利三の4氏から、作者は刑務官だろう、と言われるほど、取材が利いた作品だった。
さかのぼること、私は広島拘置所の元副所長(当時50歳前後)から、小説を書く上で、死刑囚について取材を申し込んだ。何度かの手紙のやり取りの末、彼=元副所長が取材に応じてくれた。3時間余りにわたって、赤裸々に語ってくれた。
退職時には、同拘置所には3人の死刑囚が収監されていたと話す。毎日、死刑囚の観察記録をつぶさに書くという。
「なぜですか?」
「死刑囚が精神異常になれば、刑が執行されないからです。日誌で、正常か、異常の兆候がないか、報告するのです。罪の意識がなくなった精神異常者を殺せば、ただの人殺しですから」
私にはすべてがはじめて聞く話ばかりだった。
「死刑に最も反対しているのは誰だと思いますか。刑務官ですよ」
その言葉が強く印象に残っている。
「なぜですか」
「いいですか、刑務官の募集要項には罪を犯した人の更生を図る、大切なしごとです。そう書かれているんです。人間の首を絞めて殺すこともあります、と一行も書かれていません。死刑囚を殺すのは刑務官です」
殺す。その表現にはどきっとさせられた。
死刑執行は東京拘置所など、高等裁判所が所在する拘置所である。(高松は大阪に護送)。
「なぜ拘置所ですか」
「裁判で懲役刑が確定すると、刑を執行するために、刑務所に送られます。しかし、死刑囚の刑を執行すれば、それが死ですから、拘置所で終わりです」
「だから、拘置所なんですね」
「東拘(東京拘置所)などに勤務の辞令が出ると、ぞっとしますよ。人間を殺す、そんな任務が自分に回ってくる可能性があるんですから」
刑務官は転勤で、鑑別所、拘置所、刑務所、少年院と動く。だから、刑務官になれば、だれでも死刑囚を殺す可能性がある、という。
法務大臣が印鑑を押せば、死刑の執行命令が拘置所にとどく。所長など数人の幹部が、「どの刑務官に、どの任務をあてがうか」と思慮する。
独房から連れだす人、首に縄をかける人、ぶら下がった遺体を降ろす人、そして安置所に運ぶ人、すべてが複数で行われる。(私の推測・仮に3人ずつにしても、十数人の刑務官で構成される)。
「当日、出勤してきた刑務官を呼び出し、指示・命令すると、殆どが青ざめます」
「なぜ、前日に教えないんですか」
「死刑執行日が、所内に漏れたら、全刑務官が休みますよ。法の執行とはいえ、人間が人間を殺すんですからね」
ということばがいまだ耳に残る。