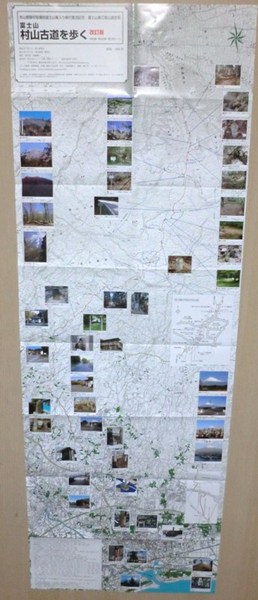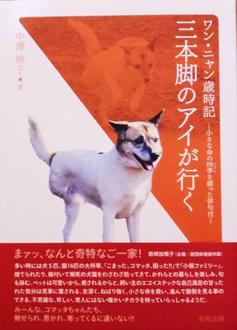第5回・文学仲間たちと『谷根千(やねせん)』を歴史散策、そして居酒屋
日本ペンクラブの広報委員会、会報委員会の有志がごく自然に、3カ月に一度は集まり、歴史散策している。第1回目は昭和の町・葛飾・立石だった。そこで意気投合し、次なるは小江戸の川越、浅草・隅田川、深川・門仲と歴史的な町を散策してきた。

こんかいが何回目か忘れていると、新津きよみさん(推理小説作家)がメールで5回目です、と教えてくれた。7人のメンバーが同一日に集まれる日取りとなると、ピンポイントの1日のみで7月11日(水)だった。集合場所は、日暮里駅と決めた。井出さん(PEN事務次長)は急に担当委員会が入り、不参加となった。総勢6人である。
谷根千(やねせん)とは谷中、根岸、千駄木の地名の総称である。明治時代から文豪たちが好んで住み、それら情景を作品に取り入れてきた。文学散策のコースとして人気がある。
清原さん(会報委員長、文芸評論家、歴史家)がコースを選定する。

日暮里駅前から、整備された石畳の御前坂を登っていく。セミが鳴く。女性陣の山名美和子さん(歴史小説家)と新津さんは日傘を手放せない、つよい夏日差しだった。と同時に、水分・アイスクリーム補給である。
通りの右手の経王寺(きょうおうじ)は、1868(慶応4)年の上野戦争の時、彰義隊を匿ったために、政府軍の攻撃を受けている。
現在も、砲弾を受けた珠の傷が寺門に残っていた。
谷中の商店街は、古い建物のデザインを残しながら、観光的にも整備されている。物珍しいものが多い。「錻力屋」(ブリキや?)という店構え、鉄製の灯籠、薬膳カレー、とか目を凝らせば、ひと昔前の日常生活の店が並んでいる。
赤穂浪士ゆかりの寺、谷中七福神の寺なども、足を運んでいく。

平成4年に『まちがど賞・台東区』を受賞した、観音寺の築地塀.は見応えがあった。屋根瓦を葺いており、黒色を基調とした、横縞模様が重みを感じさせてくれる。塀の長さは約50メートルくらいだった。
この辺りには土壁でなく、木製の格子造りで屋根を葺いている、真新しい塀があった。新旧の町の変化が感じられた。
路地で横たわる猫が多い町である。猫を素材とした、置物販売店もある。
全生庵墓地には、剣豪で、なおかつ江戸開城の功労者だった「山岡鉄舟」の墓がある。もう一人、落語中興の祖として有名でな、初代三遊亭円朝の墓もある。
円朝の囃子が新聞で、言文一致体(口語体)で載ったことから、それ以降の文学に大きな影響を与えた人物である。