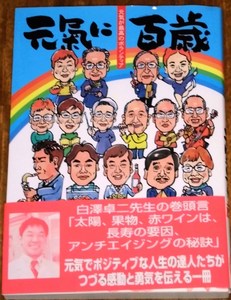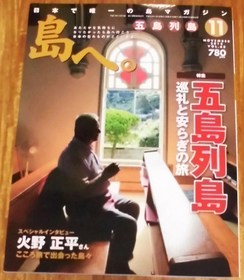わがジョギング・ロード、東京スカイツリーを見ながら、ノコノコと
だれかれ問わず時おり、「最近は走っていないのですか。HP『ランナー』に書き込みがないようですけど」と訊かれる。

「週に2度かな、3度かな、10.5キロを走っています。ときには7キロになりますけど」と応えている。
なぜ、10.5キロ、7キロと端数が出るのか。『中川左岸・右岸緑道公園ジョギングコース』には200mごとに路盤に距離表示があるので、シビアなタイムと距離が測れるからだ。
私の住む葛飾・東立石は海抜ゼロメートル地帯だ。大災害が起きれば、最も弱い地域だ。その反面、わが家からすぐ近くに、中川、荒川放水路があり、ジョギング・ロードとしては都内では最高の環境に恵まれている、と思う。
ともに護岸には信号機はないし、景色には恵まれているし、ロングコースである。最近は東京スカイツリーの完成で、いっそう風光明媚な河岸となった。

平和橋と奥戸橋と、右岸・左岸を回ってくる。3.5キロだ。
3~4年前はマラソン市民大会に出るために、中川や荒川に出て、多少の雨でも走っていた。
夜明けとともに起きて河川の護岸に出て走っていた。タイムを競う、筋肉を弛めない。継続は力なり。そんな気力に満ちていた。
最近は荒川の河口に向かうこともないが、東京湾まで行けば、往復20キロだし、1キロずつの標示がなされている。信号機はないし、どこまでも一直線だ。
JRや地下鉄の高架鉄橋とか、道路の大橋とかが、頭上を越えていく。だいたい1キロずつだから、飽きない景色だ。
最近は出向いていないので、中川の奥戸橋・平和橋ばかりになっている。