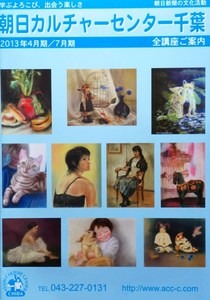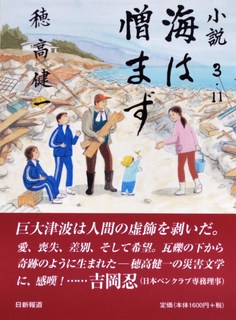第7回・歴史散策・文学仲間たちと=王子~巣鴨
日本ペンクラブの広報委員会、会報委員会の文学仲間7人による、「歴史散策」は7回目となった。4月17日(水)午後1時、JR王子駅に集合した。私は福島取材でいわき市から戻ってきたが、乗り物のタイミングが悪く、皆を改札前で20分も待たせてしまった。

王子周辺を歴史・文学散策してから、都電に乗り、巣鴨へ向かう。そして居酒屋にたどり着く、というコース設定である。
参加者は左から、井出さん(日本ペンクラブ事務局次長)、吉澤さん(同事務局長)、山名さん(歴史小説作家)、新津さん(ミステリー作家)、相澤さん(作家)、清原さん(文芸評論家)、そして穂高(作家)の7人である。
王子駅から音無親水公園に出むいた。
「案内板」には、江戸時代から名所として知られていたと記す。当時の資料には、一歩ごとに眺めが変わり、投網や釣りもできれば、泳ぐこともできた。夕焼けがひときわ見事で、川の水でたてた茶はおいしいと書かれていたという。
現代では想像もつかない。まるで人工の川だ。
王子神社はJR王子駅から徒歩5分くらいで、音無川の左岸の高台にある。門前から参道奥へと樹木が茂り、静寂な境内である。
権現造の社殿は大きく、見るからに威厳がある。祈れば、願いごと(入試)が叶う、と思うのか、学校帰りの学生が立ち寄るところだ。
神社の境内で出会ったのが「毛塚」です。この塚はなんだろう。
理容、美容業、かつら屋などが髪の供養のために、昭和36年に建てたもの。世のなかには、いろいろな供養があるものだと、妙に感心させられた。
珍しいだけに小説、エッセイ、コラムなど、執筆の材料になるのかな。7人のうち、何人かはそう考えているかもしれない。
春風がやや強かった。下町情緒を楽しみながら、7人は次なる目的地に向かう。皆の頭のなかでは、情景描写として文字化しているかもしれない。
「ここは田中角栄の出身校だ」と知ると、皆が足を止めた。館内の資料館が一般にも開放されている、と明記されていた。
見学を申し出ると、館長が説明してくれた。建築設計の専門学校で、田中角栄が長く校長に着いていた。戦前の女子たちも、建築設計の分野に進出していたと資料からわかった。
散策の途中で、スズメが死闘をくり広げていた。路上で、まさに殺し合いである。人間の存在など関係なく、激しく攻撃をしていた。
誰もがこんなすさまじいのは初めて見たという。
「オスのスズメが、メスを得るための死に物狂いの戦いかな」
そう解釈していた。