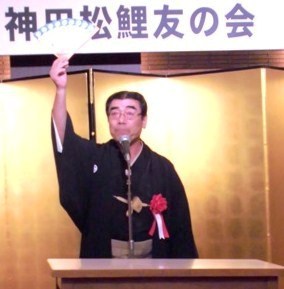「小説は腐らない」の格言通り。「千年杉」のアクセスが上昇中
日本ペンクラブの広報委員会の第1回会合が6月10日に開かれた。今回も、私は同委員会の委員に指名されたので、それに参加した。(任期は2年間)
この会合の後、同事務局の井出次長から、ふいに「電子文藝館『小説』に掲載作品された、千年杉のアクセスがすごいね」と前置きし、「穂高さんが自分で毎日何回もアクセスしているんじゃないの」と冷やかされた。
「まさか。掲載後は一度も開いていませんよ」
同作品が文学賞を受賞してから18年経った今、多くの人に読まれはじめたことで、新鮮な驚きを覚えた。と同時に、この作品は不思議な運命を持っているな、と感じ入った。
電子文藝館の作品は日本ペンクラブの歴代会長とか、過去からの著名作家の作品、および現役会員においては書籍、商業雑誌などに掲載された作品が採用される。
同委員会で採用が決定されると、どんな著名な作品でも、同委員2人による常識校正が行われる。
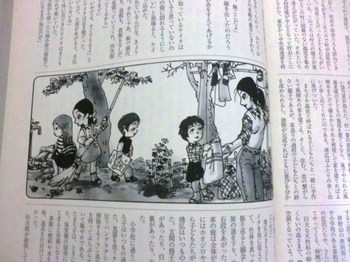 「千年杉」を担当した、神山さん(詩人)と眞有さん(大学教授)からは、
「千年杉」を担当した、神山さん(詩人)と眞有さん(大学教授)からは、
「校正の途中から内容に引き込まれ、夢中で読んでしまいました」
と賞賛のコメントが寄せられた。
私は原稿が手元を離れると、掲載されても、その作品をまず読まない。それはなぜか。作品はなんど読み直しても推敲しても、その都度、誤字・脱字、言い回しのおかしな点が見つかるもの。作品が世に出回った後で、自分の目でミスを発見すると、自身に失望を覚えるからである。
(自分の掲載作品は読まない、という作家もかなりいる)
2012年に、同ペンクラブ・電子文藝館に「千年杉」が掲載された。2か月くらい経った後、よみうり文化センター小説講座の受講生から、「先生、続きはいつ出るんですか?」と訊かれた。
「えっ、連載じゃないよ」
調べてみると、後半の3分の1が不掲載だった。もし、そのまま放置されていたならば、光が当たらず、見向きもされなかっただろう。
「掲載後は、作者がすぐチェックしないと困るな」
大原雄委員長からは叱責を受けた。
ITの技術的なミスで、すぐに修正された。
「井出さんもあのトラブルを知っているでしょ。あれ以来、私は千年杉を開いていませんよ。そんなに千年杉が読まれているんですか」
「アクセス数が突出して目立っているよ」
と教えてくれた。
千年杉は、第42回地上文学賞の受賞作品(平成7年1月発表)で、4人の選者の満場一致で決まった。当時の編集長が、
「選者全員が同一作品を推すなんて、この賞では稀有ですよ。実は、候補作品を選ぶとき、千年杉は選外でした。農事関係を対象とした賞がゆえに」
この作品は外せない、と強く主張し、候補作に推したのだという。
そんなことを思い出しながら、私は改めて18年前の作品「千年杉」を読み直してみた。