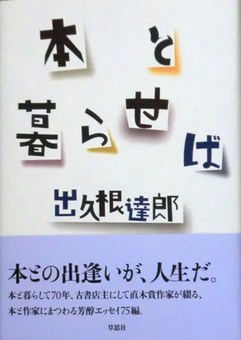小説は取材に裏づけられないと、面白くない。だから、私は書く上で取材人間に徹している。
「取材に行けば、かならず得るものがある。新発見に巡り合える」
それが私のモットーである。
無駄かな、と思っても、ささいな情報でも、あえて出かけていく。敷居が高くても、拒否は解っていても、ときには強引にアポを取って押しかけたりもする。
 歴史小説・仮題「天保の信州」を書く上で、安曇野(あずみの)市の大規模な拾ケ堰(じゅうかせき・用水路)の掘削事業は外せない。農民の提案から松本藩を巻き込み、紆余曲折の末に成功させた。結果として、荒れ地の扇状地の豊科が生まれ代わり、安曇野と名を変えるほど、豊かな農耕地になった。と同時に、風土と文化を変えた。
歴史小説・仮題「天保の信州」を書く上で、安曇野(あずみの)市の大規模な拾ケ堰(じゅうかせき・用水路)の掘削事業は外せない。農民の提案から松本藩を巻き込み、紆余曲折の末に成功させた。結果として、荒れ地の扇状地の豊科が生まれ代わり、安曇野と名を変えるほど、豊かな農耕地になった。と同時に、風土と文化を変えた。
人間どうしの戦い、人間と自然との闘い。そして、和睦(わぼく)へと運んでいく人間の知恵は、小説で描くに十二分に価値あるものだ。まずは現地を知る必要がある。
地元新聞が紹介したイベント「拾ケ堰開削と十返舎一九の藤森家滞在」10月25日に参加した。大糸線・島内駅8:40から、旗を持ったツアーだ。これまで登山、観光地で、よく見かける光景が、私にすれば初めてのツアー参加だった。
参加者は地元の人たちばかりで、東京からの参加は私ひとりだった。
奈良井川(ならいがわ・木曽川)の取水口から、拾ケ堰(じゅうかせき)の用水路が真横に伸びる。総延長15キロのうち、川の取水口から約3キロを歩いた。

本流の奈良井川は木曽の山奥から流れて、この安曇野にとどく。木曽の御嶽山で噴火事故を起こした後だけに、ちょっと複雑な心境だった。奈良井川をのぞき見れば、その水流は豊富だ。勢いが良く、水の音にも強い響きがあった。川底が段さになると、白波が立つ。東京で見る淀んだ穏かな川とはまったく違う。
イベントの主催者が、堰(用水路)の土地確保など如何に苦労したか、どう成し遂げたか、と道々に語ってくれる。
1799年(寛政11年)に、 庄屋・中島輪兵衛などが計画した。土地買収、測量、一方で住民の妨害などがあった。絵図面と見積願書を松本藩に差し出すまで、約17年の歳月がかかった。
やがて藩の許可が下りて着工となると、1816年(文化13年)の雪解けの 2月11日から工事に着手し、3か月で工事を完成させた。(新暦だと1か月遅れ)。投入された人足が5万3000人強で、まさに人力による突貫工事であった。
拾ケ堰は奈良井川の取水口から、総延長15キロへと真横に伸びていく。北アルプスの山奥から平野に縦に流れてくる川にいくつも出合う。
拾ケ堰はこれらの川と十文字の交差する。
「現代ならば、川底の地下に土管を埋めれば、流れるけれど? 江戸時代はどうしたのだろう」
参加者は口々に疑問を投げかけていた。
 「梓川といちど水を合流させ、あらためて水の取り入れ口を作った。梓川の真下を通るサイホン方式は、大正時代になってからできた」
「梓川といちど水を合流させ、あらためて水の取り入れ口を作った。梓川の真下を通るサイホン方式は、大正時代になってからできた」
案内者はそう説明していた。
「ちがうな」
私はあえて口にしなかった。
江戸時代にもサイホン方式があった。私はことし土木史学の専門家(大学助教授、水関連の専務理事)に取材し、その施工知識を持っていた。中島輪兵衛の記録にも明瞭に記録されている。この案内者は古い土木用語を知らないから、見落としているのだ。
「小説のなかで展開すればよいことだ」
あえて主催者に異論を唱えなかった。
3キロ歩いた後、信濃教育生涯学習センターで座学となった。成相新田組の大庄屋の藤森家善兵衞が当初、十か堰に乗り気でなかった。奈良井川の周辺を中心として、掘削予定地の約半数の土地を持っていた。それを供出するには抵抗があった。
各村は水不足がちで困っている。水が不足すれば、稲の育ちが悪く、稲穂が病気になる。凶作の都度、救助米を願い出たり、年貢の猶予を申し出るありさまだった。
「大庄屋の権力は強いのです。十か堰など作らなくても、自分たちはさして困らない」
他の村々は、長年、指をくわえていた。あるいは隠れて測量をした。
文化11年8月11日。十返舎一九が安曇野の藤森家にやってきた。一日泊まった。そこから藤森家の流れが前向きに変わった、と解説者の丸山さんが推論を述べていた。
 松本藩が856両、民間でも白沢民右衛門が2000両を寄付する。大事業だ。人気がある戯作者の一九が仲介の労を取った。その解釈は無理だな、と思った。
松本藩が856両、民間でも白沢民右衛門が2000両を寄付する。大事業だ。人気がある戯作者の一九が仲介の労を取った。その解釈は無理だな、と思った。
しかし、流れは変わったことは事実のようだ。やがて拾ケ関の完成につながった。
この座学で紹介された「安曇野文学」を2冊買い求めた。帰路のバスで読むと、同NO.29には、十返舎一九「御法花(みのりばな)」が翻刻版として載っていた。
一九が善光寺参りの途中で、安曇野の満願寺に滞在し、そこで得た逸話を小説化したものだ。読んでみると、奇抜な発想の講談の面白さがあった。
一九は江戸時代に執筆だけで食べられる人気作家だった。「御法花」の作中から、霊魂やキツネなどの登場を削除して読むと、「人間の業と慾」を巧く捉えている、なるほどな、と感心させられた。
一九の小説が木版で増刷続きとなるほど、全国に一躍その名を知らしめた。その背景には、江戸中期には寺小屋制度の発達があった。女児も簡単な読み書きができる時代になった。だから、平がなで、女子も読める絵本風で、一九作品は人気を馳せた。
勧善懲悪とか、野次サン・喜多さんの愉快な物語が爆発的に受けたのだ。
「安曇野文学」の「御法花」を読みながら、こんなにも漢字が使われていたのかな、当時の女子はこれだけ漢字があって読めたのかな、と疑問を持ちながら読み進んでしまった。この疑問が私の脳裏で彷徨していたから、感情移入して楽しめなかった面もある。
作品の解説で、現代用に漢字に置き換えて読みやすくしている、と説明があった。最初に明記してほしかった。
同誌のなかで、太田千代子作「山田多賀市『人間寄進』を読む」が目にとまった。安曇野を背景とした、悲惨な物語だと紹介している。読んでみたい気持ちになった。
同誌27号でも、一九の藤森家の訪問が取り上げられている。一九が訪問した8月11日は2016年8月11日から施行される祝日「山の日」と重なっている。
これも、奇縁だなと思った。