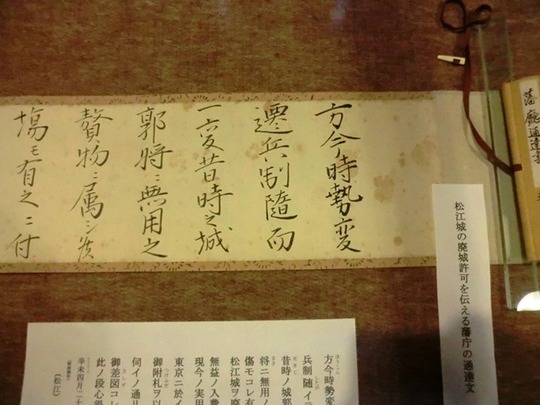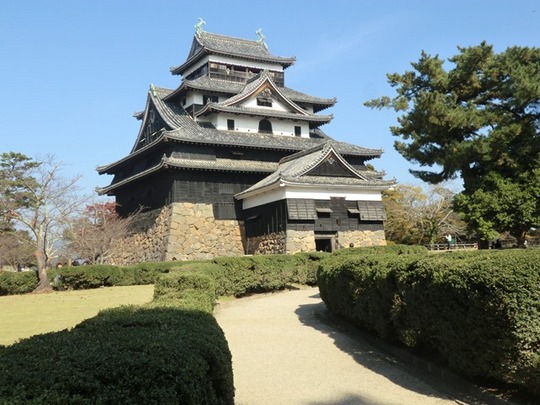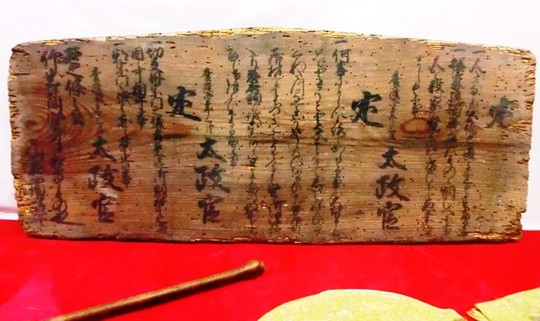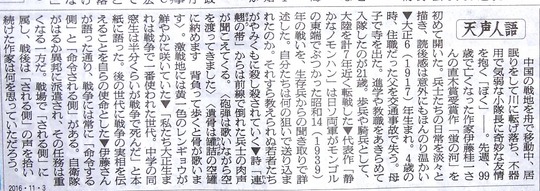新金線は大願成就なるか? 葛飾の夢をもとめて=櫻井 孝江
葛飾区内には、北から常磐線、京成線(本線と押上線)、総武線(快速・各駅)が東西に横切っている。
小松橋から新小岩駅方面を写す
しかし、南北を繋ぐ鉄道はない。亀有等から東西線の葛西へ行く時は、バスを利用するか、都心を通って大きく迂回して行くしか方法はない。
不便を感じている区民もいた。そこで、金町・新小岩間にある線路(貨物の新金(しんきん)線(せん))の利用を旅客用に考えた人々がいた。記者もその一人であった。
葛飾区内の南北の旅客鉄道の願いが、どのようになっているか 調べることにした。
明治30年12月27日(1897) 金町駅開業
大正15年7月1日(1926) 新金線開通(同時に新小岩操車場開設)
昭和3年7月10日(1928) 新小岩駅開業
操車場を停車場(駅)に変更した
昭和21年(1946) 新小岩駅にて貨物営業開始。
昭和38年(1963) 新中川開通(線路が一部変更になる。奥戸中学校あたり)
昭和39年(1964) 新金線電化
昭和43年(1968) 駅の貨物営業分離で、新小岩操車場駅開設
操車場跡
・区間は、新小岩信号場駅から金町駅迄である。
・距離は、6,6㎞の全線単線である。
2、新金線の今
現在の新金線のダイヤは下記の10本である。
① 金町駅発➡新小岩駅着
0027➡0038(日曜休)
0624➡0635
1017~1049➡1223~1053
2131➡2141
2250➡2301
② 新小岩駅発➡金町駅着
1523➡1533(日曜休)
1745➡1758
1920➡1930
1949➡1959
2230➡2241
『新金線に沿って15ヶ所の踏切がある』
新小岩寄りから、
奥中区(おくなかく)道(どう)・立石大通り・細田・東京街道・耕道・耕道第二・小松川街道・高砂・新堀・新宿新道・柴又・浜街道・三重田街道・第二新宿道・新宿道である。
(人・自転車のみ通行)
新宿新道は、国道6号線と交差している。その他は、のどかな住宅地の中である。
高砂付近で、金網で囲まれた線路を、金網の隙間から入って、反対側に歩いていく女性を見かけた。
『これからの展望』
 葛飾区内の南北の鉄道がないので、バス路線が区内の隅々まで行き渡ってきた。新金線沿線を取材していると、かつて、旅客化・複線化を考えていたのではないか と思える場があった。
葛飾区内の南北の鉄道がないので、バス路線が区内の隅々まで行き渡ってきた。新金線沿線を取材していると、かつて、旅客化・複線化を考えていたのではないか と思える場があった。
新中川を渡る陸橋に沿って、橋脚がもう一列ある。
橋を渡った線路沿いの一部には、盛り土が幅広くなっているところがある。線路際にある細田小学校の場所に駅を作る予定であった という噂もあった。
葛飾区都市計画マスタープラン地域別まちづくり勉強会のまとめ(平成21年9月 6日)には、金町・新宿地域と奥戸・新小岩地域から
○電車を走らせなくても、既存線路を活用した新交通システムを活用したい。
等の意見が出ていた。しかし、JRからは、「貨物線の廃止は、代替路線がないためできない。」と説明済みの返事であった。
平成28年区議会でのくどう きくじ議員の質問にも同じ回答が寄せられている。
区議のうめだ 信利さんが、今も新金線の活用を訴えている。
旅客化となると、国道と交差している部分の問題などがあり、難しくなり、現実化は厳しいと分かった。
2016.9.19~10.4取材 10.28編集
【情報使用(写真、時刻表、文章)の場合は、下記のクレジットを明記してください】
かつしかPPクラブ 櫻井 孝江