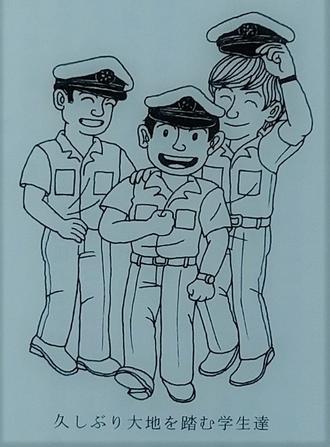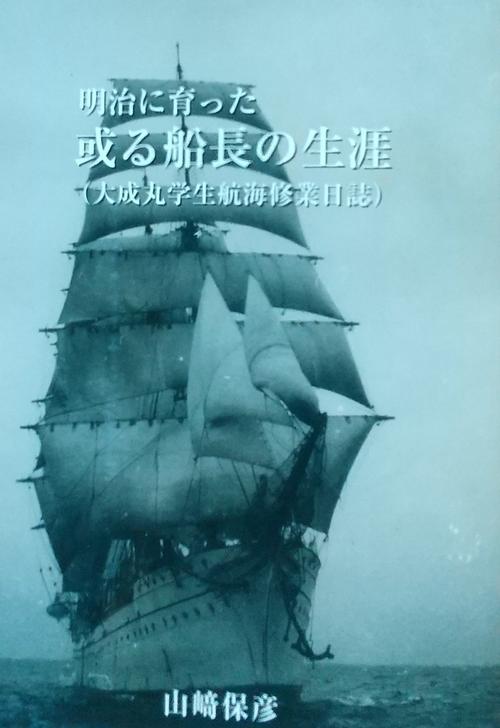戦争の宣戦布告(同日の演説)で、為政者らはいずれも平和ためだと声高にいう。
「われわれは戦争を望んでいるわけではない。ひたすら平和解決を望んでいる。和平を目的としてあらゆる努力を惜しまない」
聞く方は感動的である。
「この戦争は自国の防衛のためのもので、苦渋の決断です」
開戦には、決して積極的ではないとつけ加える。
その実、裏では暴力的で残虐な計画がおおむね隠されている。武器商人の利益が潜んでいたり、領土拡大の野望があったり、あるいは権力や宗教の色合いが色濃くあったりする。
*
戦争の火ぶたが切られると、双方とも為政者から虚偽と欺瞞とウソが飛び交う。もっともらしく言い放たれる。真実は終戦までおおむね判らないことが多い。情報を自分に有利に使う。それら作為的な大嘘をプロパガンダという。
これは戦争当事国だけでなく、報道する側においても国営放送が自国に不都合な点を隠す。民放がスポンサーの不利益だと忖度する。これも一種のプロパガンダだともいえる。
一例をしめすと、私がふいにNHKニュース番組を見たとき、ウクライナのゼレンスキー大統領がことし(2022)3月16日、米議会でオンライン形式で演説している光景が報じられた。
「あれ冒頭の大切なスピーチが削除されている、なぜだ? NHKにとって何が不都合なのだろう」と不可解だった。
TVが最大の情報源の年配者などは、ネットをみず、これでは正確な情報が得られない、と私は批判的な眼になった。
*
ゼレンスキー大統領が冒頭でこう述べていた。
『1941年12月7日の(日本による)真珠湾攻撃を思い出してほしい。空が戦闘機で黒くなった。2001年9月11日米同時多発テロを思い出してほしい。あなた方独立国家が空からの攻撃で、街が戦場になった。我々はロシアによる空からの攻撃で毎日、毎晩、この3週間、同じこと(米国が経験した空からの攻撃)を経験している」と述べた。その上で「ウクライナに飛行禁止区域を設定してほしいと願うのは、過剰ですか」と問いかけた。
NHKはそこまでをすべてカットしていた。
かたや、ゼレンスキー大統領がキング牧師の有名な演説『私には夢がある』という言葉を引用していた。きょうの私は、私には必要なものがあると申し上げます。私は空を守る必要があるのです」と述べた。
そして、ウクライナの都市へのミサイル攻撃による死者や負傷者を映した生々しい映像が流れた。
スピーチの最後はジョー・バイデン大統領に英語で語りかけ、「あなたは一国のリーダー、偉大な国のリーダーだ。世界のリーダーにもなってもらいたい。世界のリーダーであることは、平和のリーダであることだ」と締めくくった。
*
NHKがなぜ冒頭の肝心スピーチを流さなかったのか。
同大統領の演説のあと謎が解けてきた。かれこれ2-3時間も経つと、SNS上で『真珠湾攻撃が9.11と同じくくりでテロ扱いされた』とゼレンスキー大統領にたいする批判が、数千通の投稿となり、批判ごうごうとなった。
NHKの報道編集局はおおかた生々しく報じれば、ゼレンスキー大統領批判に「火に油を注ぐ」と思ったのだろう。これまでウクライナは侵略された被害者であり、視聴者の同情を中心テーマに報じてきた。
ところが一気に、それが真逆になった。報道関係者が日本人に不都合なことは流さない意識がはたらいたならば、これは情報操作である。
もとより大平洋戦争の戦時下で新聞・ラジオが、軍部に気づかい日本人に不都合な負け戦の戦況を流さないという姿勢、つまり「日本式のプロパガンダ」が今日まで底流で生きているのだと私は思った。
「SNS」を取り上げてみたい。

① 「日本の真珠湾攻撃は、軍港などの軍事施設を標的にしたのであって、民間人を標的にしたわけではない。日本は戦後どれだけアメリカとの関係を保つことを努力してきたことか。それを一瞬で壊しかねないことを平気で言いながら、ゼレンスキー大統領は日本にも援助を求める。この外交は無神経すぎる」
② 「ゼレンスキーは、相手の心情とかを考えず軽々しく発言しちゃうところがある。ウクライナ政府側が正しいことを主張していたとしても、結局はロシアが怒ったから侵略行為につながっているわけでしょう」
③ 「確かに真珠湾攻撃は良くない攻撃でした。日本も反省しています。これが演説をさせてほしいとお願いしてくる国の取る言動でしょうか?お願いする相手に失礼だと思います。日本国民の心情を考えると国会での演説は認め難い」
④ 「ウクライナ国民はロシアからの侵攻を受けて気の毒だと思います。でも、これはゼレンスキー氏のNATO加入の表明が少々強引だった部分が要因の1つになかったでしょう。フィンランドやスウェーデンもNATOには加入していません」
⑤ 「日本がアメリカを攻撃したのは事実。日本で演説するときには、東京大空襲や原爆の被害に言及するんだろうな。ソ連、ロシアの脅威を語るのに、終戦間際の不可侵条約破棄せずに攻撃したことも、満州での蛮行を持ち出す必要がある」
⑥ 「日本人の多くに、ウクライナを支援する気持ちを萎えさせた。アルカイダは無差別テロ。真珠湾攻撃は、敵の軍艦、敵基地攻撃。死傷者が出たのは同じだが、本質は違う」
⑦ 「わが国の政府や国会を挑発したり、同調を求めても、戦争当時国の一方に加担することはわが憲法の平和協調義務に反するから不可能だ、ということは理解しておいた方がいい」
⑧ 「日本の国会でやる時はちゃんと関東大空襲出してくださいね。それなら納得します」
⑨ 「ゼレンスキーの大統領としての資質。言葉の質が軽い。ウクライナ国民の安全を考えればロシアへの返答の拒否一辺倒はゼレンスキーの独りよがりだと思う。侵略されてウクライナ国民はゼレンスキーを支持しているというけど、停戦終戦ともなり興奮が覚めれば、本当にこんな大きな犠牲を被る必要があったのかと考え直すでしょう」
⑩ 「リルタイムでゼレンスキーの演説を聞いていて、真珠湾攻撃が出てきたところは、ああ、出た〜と思ったと同時に少なからず動揺した。同時に、そういう感情が湧いた自分自身も意外で、複雑な気持ちになった」
⑪ 「第二次世界大戦では、日本は原爆を2発や無差別大空襲を受け大量の民間人が殺戮された。ロシアにも侵攻され、未だに返らぬ国土が存在する。当時の戦勝国ルールに今も縛られているし、いつまでも過去の行為を反省させられ非難され続けている。ゼレンスキー大統領がドイツも経済優先だと批判されているが、経済を軸に復興したドイツを簡単に批判できるだろうか」
⑫ 「ゼレンスキーに対し正直懐疑的になりました。日本には原爆が落とされている問題を含め、日本がなぜあの当時アメリカに戦争をしかけなければならなかったのか? 歴史的な別の問題がある。戦時、日本で死んだ多くの人に対してあまりにも失礼過ぎる。ゼレンスキーはそれを理解していないで、この発言はいささか日本人全体に対して喧嘩を売っているとしか思えない」
⑬ 「日本の報道はウクライナで起きている戦争に同情しているだけで、結局やっている事はネタとして消費しているだけではないか」
⑭ 「日本人がウクライナの歴史を知らないように、真珠湾攻撃のイメージが無差別攻撃のように思われてるのかもしれない。真珠湾攻撃は事実だが、民間人を標的にしてはいないから、例に出されるのは不適切、不快、となる」
⑮ 「クライナを応援しているが、守るために寄付金で戦闘機を買ったり他国の武力を使ってロシアを攻撃してしまったら、核を落としたアメリカと変わらない。ロシア市民を殺してしまったら、きっとゼレンスキー大統領も偉大な英雄ではいられなくなる」
⑯ 「ゼレンスキーは日米開戦の歴史的事実も知らないで、真珠湾を引用したのは、日本はどうせアメリカに追随する国だと高をくくっているのでしょう。日本の国会で話をするなんて、無神経では」
⑰ 「NATOに入りたかったのは、自国の平和のためだったのに現状は戦争。挙句、停戦条件に中立国化でもいいと言ってる。落ち着く先がそれなら、今回の戦闘が全く意味のないことになる。一歩引いてみるとゼレンスキー大統領が世界大戦を引き起こしたがっているようにしか見えない。一般の国民は内心 終戦だけを願ってるんだと思うんだけど。力強さも大事だが、引くことも大事」
⑱ 「民間人を標的にしたジェノサイドという意味であの戦争から引用するなら、民間人攻撃を厳禁した真珠湾攻撃ではなく、東京大空襲、ヒロシマ、ナガサキが適切だが、まさか、アメリカ議会で持ち出すわけにはいかないからね」
⑲ 「ゼレンスキーは大統領選挙でロシアに支援を受けたにも関わらず、当選するやNATOに秋波を送り続ける態度がプーチンの怒りを沸点に達したことは、開戦時からみんな分かっていた。裏切られたと感じたプーチンの怒りも少し理解できた気がする」
⑳ 「日本人(黄色人種)は人間とは見なされずに核を実験的に投下されたわけだし、詳しい事情が分からないまま、日本がこれ以上ロシアを刺激するべきではないと思います。ゼレンスキー大統領のやり方に流されていくと、今の戦争がさらに世界に広がって行くと思われます」
21 「この戦争を止められるのはプーチンとゼレンスキーでもある。戦争を続ける事でリスクがあるのはプーチンとウクライナ国民だ。ゼレンスキーは国民や各国をあおって戦争を辞める気はないと思います。ウクライナの人々はかわいそうだが、冷静にゼレンスキーの評価を考えた方が良いと思います」
22 「ロシアが悪いのは百も承知だが、やはり双方の意見を聞くべき。それが平和のために議論するって事でしょう。国会で、プーチンの話も聞いてみたい」
*
ゼレンスキー氏がこの3月23日に日本の国会で演説すると固まった。SNSではさっそく、
「日本を戦争に引きこむような発言はやめてくれ。日本はウクライナの同盟国ではない。ロシアの標的にされたくない」
「真珠湾と9.11はまったく違うから。間違わないように」
「日本の立場からすれば、ウクライナは中国や北朝鮮の軍事強化に協力した国家だ。その結果、中朝にさえ警戒しなければならない事態になった」
「日本の最高機関で、ゼレンスキー氏が演説すれば、ロシアを全面的に敵にまわす。日本が参戦国とみられる。北方領土問題を考えると、リスクが大きすぎる」
「アメリカの言いなりで、ロシア制裁への参加やウクライナの肩入れは、憲法の平和精神に反する」
「日本は戦後70年近くロシアと時間をかけて北方領土問題や平和条約締結を議論してきた経緯がある。ウクライナは時間をかけて、ロシアと議論してきたのか」
「真珠湾攻撃の発言はとうてい容認できません」
「演説後、議員が拍手すれば、ゼレンスキー氏を支持していると受け止められる、極東でロシアと日本が緊張関係におよぶ」
「ロシアにたいして非常に危険だ。演説に反対だ」
ゼレンスキー大統領が米国議会で冒頭に「真珠湾攻撃」を引き合いに出したことから、大半が上記のような反発となり、国会で演説反対とか、なぜやるのか意味が判らないとか、ちょっと反対かな、居心地が悪いとか、SNSには怒涛(どとう)の如く巻き起こっています。
【参考資料・開戦時の議会での演説】
ドイツ・ヒットラーが議会で、
「ポーランドで、100万人ドイツ系住民が迫害を受けた。住居を追われている。ポーランドは国家総動員令を発してドイツに挑発している。不本意ながら、もう堪忍袋の緒が切れた。戦争の責任はポーランドにある。ドイツではない」
このような演説をしている。
東条英機は、1941年(昭和16年)12月08日に、
「宣戦の御詔勅が発せられました。アジア全域の平和は、これを念願する日本帝国のあらゆる努力にもかかわらず、遂に決裂のやむなきに至ったのであります。これまで政府はあらゆる手段を尽くし、対米国交調整の成立に努力してまいりました。彼(米)は従来の主張を一歩も譲らざるのみならず、かえって英蘭比と連合し、支那より我が陸海軍の無条件全面撤兵、南京政府の否認、日独伊三国条約の破棄を要求し、帝国の一方的譲歩を強要してまいりました。これに対し帝国は、あくまで平和的妥結の努力を続けてまいりましたが、米国はなんら反省の色を示さず、今日に至りました。もし帝国にして彼らの強要に屈従せんと、帝国の権威を失墜、支那事変の完遂を切り得たるのみならず、遂には帝国の存立をも危殆(きたい)に陥らしむる結果となるのであります。事ここに至りましては、帝国は現下の時局を打開し、自存自衛を全うするため、断固として立ちあがるのやむなきに至ったのであります」。
アメリカのルーズベルト大統領
「副大統領、下院議長、上院議員及び下院議員諸君。昨日、1941年12月7日――この日は汚名と共に記憶されることであろうか。アメリカ合衆国は大日本帝国の海軍及び空軍による意図的な奇襲攻撃を受けた。
合衆国は、同国との間に平和的関係を維持しており、日本の要請により、太平洋の平和維持に向け、同国の政府及び天皇との対話を続けてきた。
実際、日本の航空隊が米国のオアフ島に対する爆撃を開始した1時間後に、駐米日本大使とその同僚は、最近米国が送った書簡に対する公式回答を我が国の国務長官に提出した。この回答には、これ以上外交交渉を続けても無駄と思わせる記述こそあったものの、戦争や武力攻撃の警告や暗示は全くなかった。
次のことは記録されるべきであろう。ハワイから日本までの距離を鑑みれば、昨日の攻撃が数日前、あるいは事によると数週間前から周到に計画されていたことは明らかである。この間、日本政府は、持続的平和を希望するとの偽りの声明と表現で、合衆国を故意に欺こうとしてきた。
ハワイ諸島に対する昨日の攻撃は、米国の海軍力と軍事力に深刻な被害をもたらした。残念ながら、極めて多くの国民の命が失われたことをお伝えせねばならない。さらに、サンフランシスコとホノルルの間の公海上で、米国艦隊が魚雷攻撃を受けたとの報告も受けた」
プーチン大統領・国民向け演説 2022年2月24日、この日にロシアがウクライナを侵攻
「ロシアはNATOの東方拡大へつよく危機感をもっている。1980年代末、ソビエト連邦は弱体化し、その後、完全に崩壊した。私たちロシア人はしばらく自信を喪失した。あっという間に世界のパワーバランスが崩れたのだ。
NATOが1インチも東に拡大しないと我が国に約束した。しかしながら、西側諸国の無責任な政治家たちが露骨に、無遠慮にNATOの東方拡大し、その軍備がロシア国境へ接近している。
この30年間、私たちが粘り強く忍耐強く、ヨーロッパにおける対等かつ不可分の安全保障の原則についてNATO主要諸国と合意を形成しようと試みてきた。しかしながら、NATOは、ロシアのあらゆる抗議や懸念にもかかわらず、ロシアの国境のすぐ近くまで迫っている。
『政治とは汚れたものだ』とよく言われる。そうかもしれないが、国際関係の原則に反し、道徳と倫理の規範に反するし、ここまでしない。ここ数年で、アメリカ国内で真の「うその帝国」ができあがっている。正義と真実はどこにあるのだ?
さかのぼれば、国連安保理の承認なしにベオグラードに対する流血の軍事作戦を行い、ヨーロッパの中心で戦闘機やミサイルを使った。数週間にわたり、民間の都市や生活インフラを、絶え間なく爆撃した。
リビアに対して軍事力を不法に使い、リビア問題に関する国連安保理のあらゆる決定を曲解した結果、国家は完全に崩壊し、国際テロリズムの巨大な温床が生まれた。リビア人道的大惨事にみまわれ、いまだに止まらない長年にわたる内戦の沼にはまっている。
この地域全体の数十万人、数百万人もの人々が陥った悲劇は、北アフリカや中東からヨーロッパへ難民の大規模流出を引き起こしている。
シリアにもまた、同じような運命が用意されていた。シリア政府の同意と国連安保理の承認が無いまま、この国でアメリカと西側の連合が行った軍事活動は侵略、介入にほかならない。
何の法的根拠もなく行われたイラク侵攻だ。その口実とされたのはイラクに大量破壊兵器が存在するという信頼性の高い情報をアメリカが持っているとされていることだった。
アメリカの国務長官が、全世界を前にして、白い粉が入った試験管を振って見せ、これこそがイラクで開発されている化学兵器だと断言した。
あとになって、それはすべてデマであり、はったりであることが判明した。イラクに化学兵器など存在しなかったのだ。国連の壇上からもウソをついたのだ。信じがたい驚くべきことだが、事実は事実だ。その結果、大きな犠牲、破壊がもたらされ、テロリズムが一気に広がった。
国際法を軽視した例はこのかぎりではない。
90年代、2000年代初頭、ロシア南部の分離主義者や傭兵集団を支援していたとき、コーカサス地方の国際テロリズムを断ち切るまでの間に、私たちはどれだけの犠牲を払い、どれだけの損失を被ったことか。にもかかわらず、何の根拠もなく、私たちロシアを敵国と呼ぶ。
2021年12月、私たちは改めて、アメリカやその同盟諸国と、ヨーロッパの安全保障の原則とNATO不拡大について合意を成立させようと試みた。アメリカの立場は変わらい゛、自国の目標を追い求め、私たちの国益を無視している。
2014年にウクライナでクーデターを起こした勢力が、権力を乗っ取り、お飾りの選挙手続きによって、権力を維持し、紛争の平和的解決を完全に拒否した。
終わりの見えない長い8年もの間、私たちは、事態が平和的・政治的手段によって解決されるよう、あらゆる手を尽くしてきた。すべては徒労に帰した。
NATOによるウクライナ領土の軍事開発は受け入れがたい。NATO諸国の軍によって強化され、最新の武器が次々と供給されている。NATOが東に拡大するにつれ、我が国(ロシア)にとって状況は年を追うごとにどんどん悪化し、危険になってきている。
しかも、ここ数日、NATOの指導部は、みずからの軍備のロシア国境への接近を加速させている。私たちにとって受け入れがたいことだ。
ドンバスの人民共和国(ドンバスウクライナの東南部に位置する)はロシアに助けを求めてきた。ドンバスには数百万人の住民に対するジェノサイドがある。これを直ちに止める必要があったのだ。
第二次世界大戦の際、ヒトラーの片棒を担いだウクライナ民族主義一味の虐殺者たちが、無防備な人々を殺したのと同じように。彼らは公然と、ロシアの他の数々の領土も狙っている。さらに核兵器保有までも求めている。そんなことは絶対に許さない。
これを受け、国連憲章第7章51条と、ロシア安全保障会議の承認に基づき、また、本年2月22日に連邦議会が批准した、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国との友好および協力に関する条約を履行するため、特別な軍事作戦を実施する決定を下した。
その目的は、8年間、ウクライナ政府によって虐げられ、ジェノサイドにさらされてきた人々を保護することだ。そしてそのために、私たちはウクライナの非軍事化と非ナチ化を目指していく。また、ロシア国民を含む民間人に対し、数多くの血生臭い犯罪を犯してきた者たちを裁判にかけるつもりだ。
ただ、私たちの計画にウクライナ領土の占領は入っていない。国連憲章第1条に明記されている民族自決の権利を取り消すものでもない。私たちの政治の根底にあるのは、自由、つまり、誰もが自分と自分の子どもたちの未来を、自分で決めることのできる選択の自由だ。希望するすべての人々が、この権利、つまり選択の権利を行使できるようにすることが重要であると私たちは考えている」
『註釈』
プーチン大統領の侵攻は、ウクライナの「非武装化」と「中立化」、2014年にロシアが併合した南部クリミアでの主権承認などを求めるもの。
額面通りにとらえれば、ロシアの国境のすぐ近くまでNATO軍を入れるな、という国土防衛(自衛権)である。
SNSコメント:Yahoo!ニュースより
イラスト:中川有子
 これは30年ほど前に、「庭に小鳥を」という小冊子を、散歩の途中で見つけたことが発端となり作られたものだ。
これは30年ほど前に、「庭に小鳥を」という小冊子を、散歩の途中で見つけたことが発端となり作られたものだ。