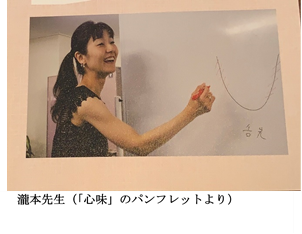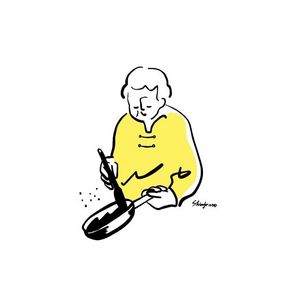私は60歳を過ぎた。コロナ禍が続く中、毎日の食事でより健康になれたらと思い、身体によいという薬膳料理の勉強を始めようと思った。それは、昨年秋のことだった。
近くに教室がないかと、ネットで調べてみると『心味(ここみ)』という薬膳料理教室があると知った。東京都内の三軒茶屋と横浜の青葉台の二か所に教室があるようだ。
私は自宅に近い青葉台に行くことにした。場所は最寄り駅で降りたあと、歩いて15分ほどの住宅地にある一戸建ての家である。(そこは先生のご実家だそうである)。
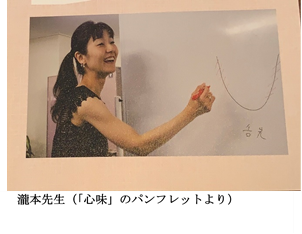 迎えてくれたのは若いすらりとした美しい女性の先生だった。一階の15畳ほどのリビングが教室になっており、生徒は女性ばかり5人である。一人ひとりの間には、アクリル板が立ててあり、コロナの感染対策にも配慮されている。
迎えてくれたのは若いすらりとした美しい女性の先生だった。一階の15畳ほどのリビングが教室になっており、生徒は女性ばかり5人である。一人ひとりの間には、アクリル板が立ててあり、コロナの感染対策にも配慮されている。
薬膳とは、東洋医学の理論を取り入れた健康料理である。西洋医学のように、からだの悪い部分だけを見て治療するのではなく、全体のバランスを見ながら、体内の環境を整えることで健康へと導いていくものだ。
2時間の講座の前半は、先生の講義を聴く。まずは身体(おもに内臓)の仕組みを勉強することから始まる。「肺の働きについて」「腎の働きについて」「冬の養生・陰陽の概要」などである。
講義の前には、必ず先生が入れたお茶をいただく。その日は、菊の花だけを用いた「菊花茶」だった。
 これは眼の疲れや喉の痛みによく、解毒、鎮静作用があり、高血圧にもよいと言われている。その効用もさることながら、ほのかな甘い香りの芳香成分が神経を刺激して、快い感情を与えてくれる。とても飲みやすいお茶である。
これは眼の疲れや喉の痛みによく、解毒、鎮静作用があり、高血圧にもよいと言われている。その効用もさることながら、ほのかな甘い香りの芳香成分が神経を刺激して、快い感情を与えてくれる。とても飲みやすいお茶である。
気持ちがリラックスしたところで、先生の講義が始まる。中国医学に基づいた論理なので、難しい漢字の熟語が多い。たとえば、肺の働きについては次のような説明があった。
「肺は呼吸の管理や、発声、汗の調整、外邪(がいじゃ)を追い出したり、水分代謝を管理したりします。肺の働きを支えているエネルギーは宗気(そうき)といい、これは清気(せいき)(肺が取り込んだ空気)と水穀(すいこく)精微(せいび)《脾(ひ)が作り出した栄養》でできています。」
という具合である。
難しい漢字が多く、先生の説明を聴き、内容はなんとか理解できても、とてもすぐに覚えられるものではない。
だが、そんな難しい話ばかりではない。
「よく、風邪をひいて鼻水が出ると、ネギやショウガで身体を温めるとよいと言われていますね。水溶性の透明な鼻水の場合は、身体が冷えているのでそれでよいですが、粘着性の色のついた鼻水になると、身体に熱がこもっているので、逆効果になります。その場合は、身体を冷やす大根、ごぼう、春菊などがよいですよ」などという有益な話もある。
先生は、時にはホワイトボードにわかりやすく図を描いたり、難しい理論の中に、親しみやすいエピソードなども加えて、薬膳の話を進めてくれる。
1時間の講義のあとは実践である。先生があらかじめ用意した薬膳料理を試食する。私にとって、毎回とても楽しみな時間である。
冬の養生に必要な、身体を温めたり、血の巡りをよくする食材としては、米、イモ類、黒豆、シナモン、鶏肉、にら、エビなどがある。昨年秋は、それらを取り入れた4品のメニューだった。
薬膳料理とは、薬のようで味気ないイメージだったが、食べてみると全く違う。野菜や肉の味がしっかり出ていて、とても美味しい。レシピを見ても、手に入りにくい食材はほとんどない。料理法も特殊なものではない。
身体にいい物を食べているという意識も手伝って、食べたあとは、元気になった気がした。
そこで私も先生のメニューを参考にして、自分なりの献立を作ってみた。

・黒豆のチーズリゾット
・カボチャと卵のサラダ
・鶏肉と山芋とレンコンの煮物
食べてみると、黒豆のチーズリゾットは、黒豆の量が多すぎて、煮込みが足りず、豆が固かった。それに、チーズと黒豆は相性が悪いようだ。
だが、他はまぁまぁの味だった。
その後、季節は冬から春へと変わり、月に一回、学ぶ内容も「春の養生」へと変わっていった。
5月には「梅雨の養生」を学んだ。梅雨どきは湿気が多いので、余分な水分が身体に溜まり、うまく排泄できないと様々な不調が出てくることがある。むくみやのぼせ、頭痛などである。
そこで、水分の排泄を助ける食材としては、あずき、そら豆、大豆などの豆類、とうもろこし、冬瓜(とうがん)、はまぐりなどがあるそうだ。
今回も先生のメニューを参考にして、自分なりの「梅雨の養生メニュー」を作ってみた。
 ・そら豆のごはん
・そら豆のごはん
・ソバの実のサラダ
・鶏肉のグリル、もずくソースがけ
・カボチャとにんじんの煮物
蕎麦の材料であるソバの実は、教室で先生が紹介してくれた食材である。ビタミン、ミネラルなどの栄養素が凝縮されている。
今回は少し茹でて、生野菜に混ぜて食べたが、ソバの実を使ったレシピは、他にも色々あるらしい。
鶏肉は油で焼いてあるが、もずくと一緒に食べることで、さっぱりとした味わいになった。
今回は、どれも失敗なく美味しく食べることができた。
薬膳調理は、季節や体調、それぞれの体質などによって臨機応変に選ぶ食材を変えていくので、奥が深い。
習い始めてからもうすぐ1年になるが、私は、まだその時に合った献立をすぐに考えるまでには至っていない。
これからも奥行きのある薬膳料理を学び、楽しく、美味しく食べて元気に過ごしたいものだ。
【了】