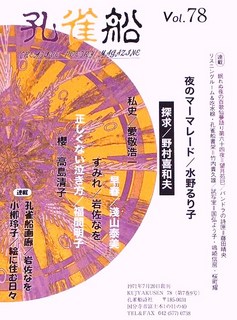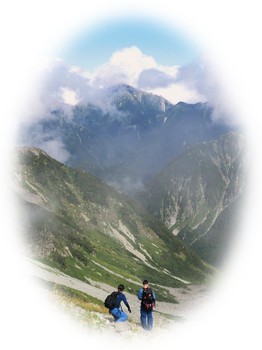【寄稿・エッセイ】鳥島と漂流者たち=久保田雅子
【作者紹介】
久保田雅子さん:画家、インテリア・デザイナー。長期にフランス滞在の経験から、幅広くエッセイにチャレンジしています
久保田雅子
鳥島と漂流者たち 久保田雅子
私がはじめて読んだ漂流物語は、野上弥生子氏の<海神丸>だった。
女性作家が壮絶な漂流状況を書いたことにおどろき、感動したものだ。と同時に、漂流物語にはことさら興味を持つようになった。
やがて、いろいろな物語を読むなかで伊豆諸島の無人島である、鳥島(東京から約600キロ)に何度も出会う。
アホウドリの生息地としても有名な火山島の、この島には江戸時代に数々の漂流した船が流れついた。この島のおかげ(存在)で生還できた漂流民は80名以上だという。
鎖国以前の日本は、天測航法技術を持っていて、太平洋を横断する航海もできた。御朱印船が活躍し、南洋諸国とも盛んに交易をしていた。
だが、江戸時代になると、鎖国政策のため船は国内運搬用のみの廻船となった。陸上の山見航法で、暴風雨などに巻きこまれて陸から遠ざかってしまうと、船位がわからなくなってしまうというお粗末なものだった。
収穫が終わった新米を江戸に運ぶ季節が、ちょうど冬の北西季節風で、船乗りの恐れる<大西風>のころだ。
もしも、黒潮に乗ってしまうと日本から遠く流されてしまう。
嵐の最中におみくじで占いをして、帆柱を切り捨てるという無知な行為から、天候が回復した時にはもはや帆船航海ができなくなり、漂流だ。
活火山の鳥島は食用になる植物もなく水もない。漂流者は洞窟を住まいとしてアホウドリと魚を食糧に、水は雨水を貯める工夫などをした。
1719年に漂着後、鳥島で20年もの長きに渡ってのサバイバル生活の後、生還を果たしたのは遠州(静岡県)の大鹿丸12名のうち3名だった。<鳥島漂着物語>(小林郁著)絶版。
このときは島が活動期で火口から火種を得て、夏には立ち去ってしまう渡り鳥のアホウドリの干し肉を作り、保存食として夏を過ごす工夫をしている。
20年後に島に漂着してきた江戸の宮本全八船17名とともに、伝馬舟でついに八丈島に帰着を果たす。