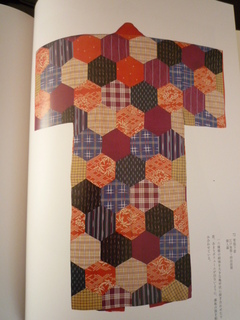【寄稿・エッセイ】 コツを明かす = 筒井 隆一
行きつけの居酒屋で、突き出しに『筍の木の芽焼き』が出てきた。新鮮な山椒の香りと筍の歯ごたえが、本格的な春を感じさせる。私の好物で、今宵も酒が進みそうだ。
 20年ほど前、家を建て替える前のわが家には、庭の片隅に孟宗竹の竹林があった。私の母は、関東大震災の被災体験から、大の地震嫌いだった。家の設計・計画をまとめる前に、まず庭に数株の竹を植え、竹林をつくった。根の張った竹林は地震に強い、という言い伝えを信じてか、地震が来れば真っ先にそこへ逃げ込もう、と竹を植えたらしい。
20年ほど前、家を建て替える前のわが家には、庭の片隅に孟宗竹の竹林があった。私の母は、関東大震災の被災体験から、大の地震嫌いだった。家の設計・計画をまとめる前に、まず庭に数株の竹を植え、竹林をつくった。根の張った竹林は地震に強い、という言い伝えを信じてか、地震が来れば真っ先にそこへ逃げ込もう、と竹を植えたらしい。
その竹が立派に育ち、毎年見事な筍が、にょきにょき出るようになった。
春先、会社の仲間がゴルフ帰りにわが家に立ち寄り、丁度食べ頃の筍を掘り上げ、持ち帰っていってもらうことになった。
その手伝いをするのが家内である。
「ちょっと顔を出しているのがあるわ、これがいいんじゃないかしら」
「そうですね、私は掘ったことないんですが、コツを教えて下さい」
仲間に頼まれると、家内は気軽にスコップを持ち、筍を傷つけず、慣れた手つきで掘り上げていった。やる気満々だ。力仕事には定評がある。
仲間は新鮮な筍を土産に貰った以上に、家内の器用で力強いスコップ捌きに、感心したのだろう。
いまもゴルフを共にする度に言う。
「筒井さんの奥様、筍を掘る時のどっしりした腰の入れ方、素晴らしかったですね」
「美味しい筍の味より、女房の仕事ぶりが忘れられないようだな。懐かしいね」
あのとき仲間が、家内に筍堀りのコツを聞いていた。
「このタイミングで足を踏ん張り、腰をグッと入れ、スコップを45度の角度で根元に差し込み……」
そう説明されても、言われたとおりにできない。
コツというのは技術とはひと味違い、文字や言葉で説明しにくい何かがある。家内も身体で覚えているが、仲間に説明はできない。技術のマニュアルでは書けない、それがコツなのだ。
先日小保方晴子さんが、
「細胞作製はコツがものを言う、全てのコツをクリアーできれば……」
と記者会見で答えていた。
筍堀りとは次元が違いレベルの高い生物化学の世界だが、煎じつめれば同じこと、コツを説明しろと言われてもできないし、分かって貰えないという話だろう。