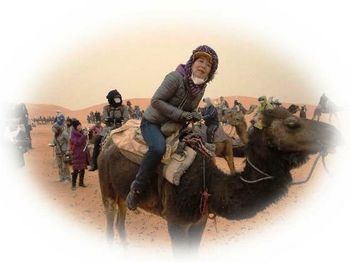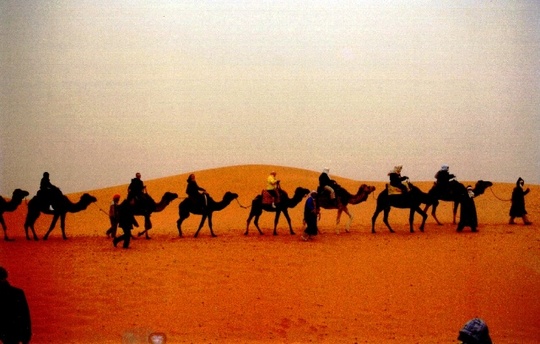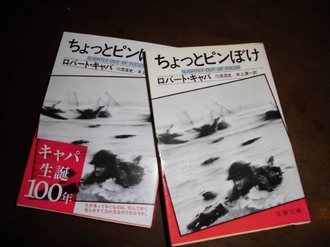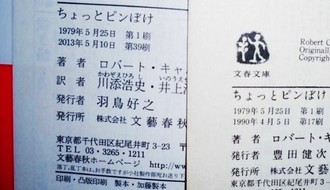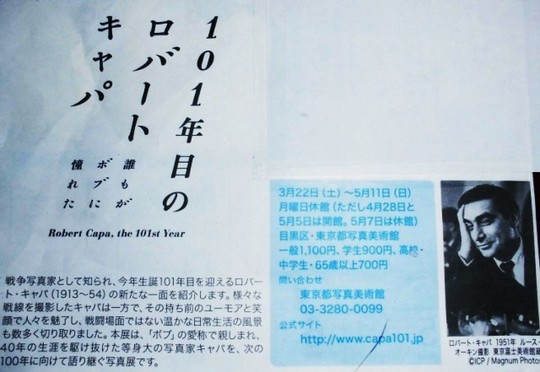【紀行・エッセイ】 靴 : 青山貴文
上野駅構内には、数年前に開店したスコッチグレイン靴店がある。入口左方の壁際の陳列台に沿って、奥に行くに従い高額な靴が整然と並んでいる。
 熊谷から東京に出かける度に、この店内を覗いては、紳士らしく高級感のある革靴を履いてみようかと思う。一方で逡巡してしまう。元来、私は靴は外見よりも歩き易さを優先し、余り高価でないものときめていた。
熊谷から東京に出かける度に、この店内を覗いては、紳士らしく高級感のある革靴を履いてみようかと思う。一方で逡巡してしまう。元来、私は靴は外見よりも歩き易さを優先し、余り高価でないものときめていた。
今春、この靴店で外観の良い高級の革靴を購入しようと、思い切って店内に踏み入る。最も奥の最上段の棚にある、先端の尖った駱駝色の品格のある革靴を指さして、近くにいた店員に声がけした。
「この靴をためしてみたいのですが」
30歳代のメガネを掛けた実直そうな店員は、私の茶色の合成皮のウオーキングシューズをちらっとみてから、
「どうぞ、ここに腰かけて履いてみてください」
という。すこし窮屈だが、なかなか見栄えがよく、短い脚も長く見える。店内を数歩あるいてみると、小指の外側が内革に当たって痛い。さらに、靴の先端半ばの艶のある革が折れそうで歩きにくい。過去にも、購入して間もなく、同じ個所に横しわが入り落胆した記憶がある。
「この類でもう少し足巾が広く、歩きやすい靴ありませんか」
店員は、笑みを浮かべて、奥の方から箱に入ったいくつかの靴をもってくる。いろいろ試すが、どうもしっくりいかず歩きにくい。
入口から中ほどの棚にある、先が心もち広い先端半ばにミシン目が入った、がっちりしたタイプを試してみた。今履いている靴とまではいかないが、まあまあ我慢できる。
「お客様には、このタイプの方がお似合いかと存じますが」
値札を観ると、先ほどのものよりはるかに安い。
しかし、(今回は、この店の1級品を望んでいるのだ。なにせ生涯最後の買い物になるかもしれないのだから)納得がいかない。
店員は、靴が変形するのをおそれる態度で、私の足元の1級品をそそくさと箱にしまいはじめる。
(安価な方が、歩きやすいし、自分に合っているな)
と再度2級品をいろいろ履いて歩いてみる。やはり、1級品よりはるかに歩きやすい。自分の足までが2級なのかと情けなくなったが、所詮は履物である。自分相応の安価な方を購入することにした。
安価とはいっても、私にとっては、今まで購入したこともない高価な革靴であることは否めない。
高価な靴といえば、この2級品とほぼ同じ値段の登山靴がある。5~6年前に購入したもので、趣味に使うものは、高くても躊躇はないし、少しももったいないと思わないから不思議だ。
黒色の革靴は、約10年前に購入したものがある。この2級品の半分の価格で、冠婚葬祭時に使用する以外は履かない。
愛用の靴は、なんと言っても今履いている1万円弱のウオーキングシューズだ。寿命は、2~3年と短いが、軽くて、凄く歩きやすい。雨天の日でも、東京でも、どこにでも出かけられる。
数日して、青空の広がった気持ちが良い日に、購入した革靴を箱から取り出した。海老茶色の艶のある皮革の手触りが愛おしい。この革独特のかすかな香りも心地よく鼻をくすぐる。
家の前の道路を試し歩きした。アスファルト上の小粒の石が、足裏に直に感じ、靴底が傷つくようで心配である。さらに近所の蔦屋(本屋)まで歩を進めてみた。つま先をまっすぐにして、小石の極力少ない個所を選んで、踵から着地して歩く。慣れるにつれ、歩く姿勢も良くなってきた。頭を上げておっとりと歩いていると、前方から自転車に乗った近所の奥さんが、親たし気に
「あら、青山さんどこへいらっしゃるの」
「いや、ちょっと本屋まで行ってきます」
と言葉少なく答えてから、姿勢を崩さず前を向いて歩く。いつものように、軽口がでない。(どうも、近所で履くような靴でもないな)と思いながら帰路に着いた。
購入時には、店員から、
「雨の日は革が痛みますから、なるべくなら履かないようにしてくださいね」
とアドバイスをうけている。天候がはっきりしない日は、履けない。
また、従来東京に出かけるときは、時間的余裕ができると、いろいろ名所旧跡を歩き回るようにしている。必然的に、安価なウオーキングシュウズか、高価な登山靴を履くようになる。
やっと手にした革靴は、真っ赤な靴枠を嵌めて、下駄箱で出番を待っている。
しかしながら、なかなか出番がない。