【写真エッセイ・寄稿】人生、思い通りには・・① = 斉藤永江
作者紹介:斉藤永江さん
彼女は栄養士で、製菓衛生士です。チョコレート製作を始め、洋菓子作りと和菓子作りに携わっています。傾聴ボランティアとして、葛飾区内の施設、および在宅のお年寄りを訪問する活動をしています。
朝日カルチャーセンター・新宿『フォトエッセイ』の受講生として、写真と叙述文に力を入れています。
人生、思い通りには・・① = 斉藤永江
世の中、自分の思ったようには進まない。
私は、2人の子どものお産で痛感した。
1988年7月20日に長女は産まれた。
妊娠期間の前半は、母子ともに順調に過ごした。7か月目に入ると、逆子の診断を受けた。本来、赤ちゃんは頭を下にして大きくなるべきところを足が下になっていた。
「逆子で破水をしてしまうと、赤ちゃんが産まれ難くなって危険ですから、逆子体操をして治してくださいね」
と先生から告げられた。
 四つん這いになってお尻をあげる。15分ほど同じ体勢でいると、お腹の中に空間ができるのか、不思議と赤ちゃんが動き出す。狭い中で必死に正しい場所に戻ろうとする様子が、薄いお腹の皮を通して伝わってくる。まだ見ぬ我が子が健気に思え「ガンバレガンバレ」と声をかけながら毎日、逆子矯正体操を繰り返した。
四つん這いになってお尻をあげる。15分ほど同じ体勢でいると、お腹の中に空間ができるのか、不思議と赤ちゃんが動き出す。狭い中で必死に正しい場所に戻ろうとする様子が、薄いお腹の皮を通して伝わってくる。まだ見ぬ我が子が健気に思え「ガンバレガンバレ」と声をかけながら毎日、逆子矯正体操を繰り返した。
1か月後の検診では正位に戻っていた。
(良かった、これで心配なく自然分娩に臨めるわ)
そんな安堵の日もつかの間、ある日、お腹の中で異常な動きをする気配に嫌な予感がした。
次の検診は半月後だった。
「あ~また逆子にもどっちゃってますね」先生は、エコー検査をしながら残念そうに私に告げた。
「やっぱりですか。なんて子なんでしょう、もう8か月目に入ったというのに。また体操しなくちゃいけませんね」
落胆する先生の気持ちを和ませようと、私はつとめて明るく話した。
連日の矯正体操がまた始まった。私の体もきつくなっていた。四つん這いになりながら、
(ちょっとあなた、頭が下なんだってば。体の向き間違ってるってば)
とお腹をさすり声をかけ続けた。
妊娠9か月目に突入し、赤ちゃんの体重は2000gを超えた。
「良かったですね。正位に戻ってますよ」
先生は、前回の落胆ぶりとは対照的に、この時期にこんなことがあるのかと愉快そうな口調だった。
「良かった。全く、やきもきさせる子ですね。いったいどんな子が産まれてくるのかしら」
(このままね、頭が下で正解だからね)
更に大きくなったお腹をさすり、絶え間なく言い聞かせ続けた。
臨月に入ると、赤ちゃんは2500gほどに成長し、お腹は一層大きくふくれた。
私は肩で呼吸をするようになり、胃が突き上げられ、大食の私があまり食べられなくなってきた。
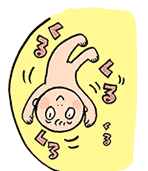 窮屈になった子宮の中でも、相変わらず元気によく動き、バタバタした手足がお腹の皮の上からでもつかめるのでは?と思うほどだった。
窮屈になった子宮の中でも、相変わらず元気によく動き、バタバタした手足がお腹の皮の上からでもつかめるのでは?と思うほどだった。
強く蹴られて痛みを感じることも多かった。
6月下旬、掃除機をかけた後に、体を休めようとソファに横たわっていた時だった。
お腹の中で異常な動きが始まる気配を感じ、ぎくりとした。(ちょっとぉ、何ガギガギ動いてるの?)
(頭が下だからね、今のままでいいのよ、動いちゃダメなのよ)
お腹を強くさすりながら赤ちゃんに言い聞かせた。
すると、体位移動など到底無理であろう窮屈なお腹の中で、ガガガと少しずつ回転していく様が感じられたのだ。
(ちょっと、だめだって。動いちゃだめだって)
時間にして、わずか数十秒の出来事だった。
お腹に目をやると、すでに赤ちゃんの頭がポコンと私の両胸の真下におさまっていた。
呆然とした。こんなことってあるのかしら?いつ産まれてもおかしくないほどに成長した赤ちゃんが、また逆子に戻ってしまうなんて。
私は、胸の谷間に鎮座している赤ちゃんの頭をこずいた。(先生に何て言ったら良いのよ)親身に検診してくれる先生の、がっかりする顔が浮かんだ。赤ちゃんや自分のことよりも、先生に申し訳なく思う気持ちが強い自分がおかしかった。
次の検診日まで必死に矯正体操したが、お腹の中の状態は、うんともすんとも変わることはなかった。
(ふん、体操したって戻ってあげないもんね)
すまし顔の赤ちゃんの顔が目に浮かんだ。安心して逆さまの体勢に落ち着いているようだった。
「先生、悲しいお知らせがあります」
臨月に入ってからの検診で、私は逆子に戻ってしまったことを告げた。
「まさかこの時期に・・・こんなことがあるんだね」
先生も半ばあきらめたようだ。
「体操はもうやめましょう、体に負担が掛かるからね。とにかく破水しないように気をつけてね」
と念をおした。
私はもはや神頼みしかないと、毎日、近くの帝釈天をお参りしては100円を投じた。
(破水しませんように。どうか無事に出産させて下さい。五体満足な子が産まれますように)
予定日の7月17日は、何事もなく過ぎていった。
私は、逆子騒動に疲れ果て、赤ちゃんさえ元気ならと、半ば投げやりになっていた。
















