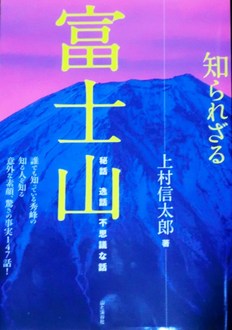【寄稿・エッセイ】 遺言状 = 横手 泰子
「10年先にはお母さんは居ない」
何かにつけて娘たちに言い続けた。気が付いたら十年を遥かに過ぎている。そこで最近では「死ぬまえに」と「最後の」が出てくる。
60歳の誕生日を迎える時、娘たちから何が欲しいか聞かれた。「かんじき」をリクエストした。おしゃれな「スノウシュウ」が届いた。積雪2メートル、雪が障害物を覆って行動範囲が広くなり、動物の足跡を追ったり、植物の冬芽を観察する好機だ。真冬でも水が湧き続ける沼に、アメマスの産卵も見に行ける。
「樹齢1000年のオンコ(イチイの方言)が最近見つかったから見に行きましょう」
東大演習林のA教官から声が掛った。
早速出かける。雪の林内を縫って歩き、汗が滲む頃たどり着いた。
A氏によると、長年林長を勤めたドロガメさん(本郷キャンパスで一度も講義をしたことのない東大教授)に聞いても山子さん達に聞いても、誰もしらなかった。鳥の研究が専門のA氏が偶然見つけたと言う。
樹齢300年、400年のエゾ松なら見本林で見られる。200年たつカツラのひこばえが2本見事に立っているのも見た。
1000年のオンコは大地に何本も根を張り、うねるように盛り上げて、不動の幹から、枝を四方に悠然と広げていた。千年と言う歳月風雨に耐え、雪に押しつぶされることもなく生き続けた、森の精は、どれだけ多くの鳥たちを休ませ、何を見て来たのだろう。言葉もなく立ちつくした。
2年先に80になる。「終活」という言葉が横行する。ほっといてくれ、と思っている。しかし、遺言状なるもの、書いておかねば、という気持ちは…ある。
幸か不幸か子ども達が争う様な財産など無い。私の遺骨は、一本の桐の木の根元に置いて欲しい。それが願いだ。願わくはその桐の木が1000年生き続けて欲しい。私はそれを見上げて眠っていたい。
「お前が産まれた時、植えた」
と言われた桐の木が並んでいた。
春になると薄紫の花がさいた。筒型のその花で、毎日遊んだ。本来、箪笥になるはずのその樹は、戦後の物不足の時代に下駄に加工されて、消えてしまった。故郷に向かう列車に乗ると、車窓から見える景色の中に桐の木が見える。「私の桐の木」と言う思いが心をよぎる。
今年の誕生日には、とりあえず「遺言状」の下書きでもしてみよう。本物になったりするかもしれない。
動物歳時記
介護犬アイ