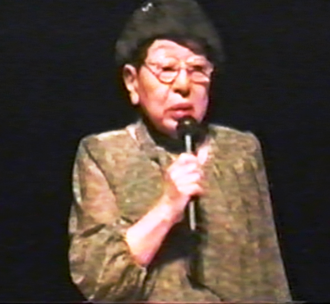【寄稿・エッセイ】 海辺のお花畑 = 林 荘八郎
江戸時代の版画家、安藤広重が金沢八景を描いた版画の中に「乙舳の帰帆」というのがある。乙舳(おっとも)は風光明媚な漁村であったようだ。漁を終えた数隻の帆かけ舟が沖から岸へ戻ってくる様子は周りの景色と溶け合い、美しい眺めだったことを物語っている。
しかし残念ながら、近年の道路の整備や住宅地の開発のため景観は少しずつ失われた。今では「八景」の一つだったと言われても信じ難い。一方、盛んだった乙舳の漁業は海岸の埋め立てに伴い廃れ、当時の漁業の様子は浜辺に僅かに残っている漁具の収納小屋、舟置き場、陸に揚げられたままの2、3の伝馬船で偲ぶことができるだけだ。
多くの漁師は漁業補償金を受け取って遊漁船に転業し、今は釣り客で賑わう所となった。そんな乙舳町に私は住んでいる。
その舟置き場の脇に10坪ほどの雑草地があった。利用価値のないスペースだ。だから雑草が茂った。雑草を刈るのは我が家の隣に住む元漁師で古老の暇つぶしの仕事になっていた。ところが古老が亡くなってから放置されたままだったので、我が家から近いこともあり私が雑草刈りを続けた。
2011年春にそこに花でも植えようかと思い、鍬で耕して雑草を根こそぎ取り払った。自分は農作業になど向いていないと思いながらも長靴を履いて畑を耕したときは、畑の持ち主になったようでちょっといい気分だった。
作業をしている時に何が始まったのかと野次馬が集まってきた。通りがかった町内会長に、
「勝手なことをしますが、ここは誰のものですか」と聞くと「関東財務局管理の管理地ということになっています」という。
無断使用することについては「多分文句は言ってこないでしょう」が返事だった。そのやりとりを聞いていた町内の古老は、
「ダメだと言ってきたら、ハイわかりましたといってやめれば良いんですよ」と笑った。
ご苦労なことだ、いつまで続くことやら、と素っ気ない人もいた。
家内もその一人だった。
間もなく気がついたことがあった。私が楽しそうに花を植えているのを見る目は、好意的なものばかりではなさそうだと。この町内にもうるさ型の主婦はいる。どのように見ているか、顔つきを見れば黙っていてもわかる。すれ違えば気配で感じる。
ある一家の顔つきは「国有地を勝手に利用している」と言いたげな明らかに非難の目に思えた。余計なことを始めてしまったかなという思いも抱いた。
やがて、その場所はゴミ集積場所に適しているということで、町内会は網で作ったタタミ一畳ほどの大きさのゴミかごを畑の中央に設置した。私は残るスペースに花を植え続けた。しかし園芸の知識がないし、失敗を重ねた。水不足でサルビアを全部枯らしたこともある。台風の時に波しぶきを浴びて花が全滅したこともあった。
町内には花作りをしている人がいるし応援してくれる人たちが現れた。むかし田舎で花を栽培した経験のある婆さん、いま植木鉢で熱心に花を育てている奥さん、散歩にきて咲きだした花を褒める人、自分の花壇の苗を持ってくる人、農作業をしていると親しみを感じてか声をかけてくる人。その人たちから感想も指導も頂く。毎朝ゴミ箱に来る奥様方もお礼や励ましの声をかけてくれるようになり、花を介して仲良しが次第に増えた。
畑の正面に住む80歳のご婦人は日当たりの良い部屋から釣舟が行き交うのを眺めながら毎日静かに花畑を監視している。
種を蒔いたばかりの畑が乱れているのに気づき何があったのだろうと思って佇んでいると、猫が来て畑を踏んづけていった、たくさんの雀が来て砂浴びしていった、子供たちが畑を駆け抜けていった、浜へ降りる人が畑を横切っていった、などと報告してくれる。朝夕の散歩でやってくる飼い犬は決まって畑で用を足していく。
みんなの畑だから仕様がないと言い聞かせている。
いまは朝起きて先ず足を向けるのは花畑だ。花は元気かと見に行く。花いじりを始めた当初はポットに入った花を買ってきて整然と植え畑が美しくなっているのが楽しかった。邪魔な雑草が出てきたら目の敵のように抜いていた。
そのうちに畑の様子が変わってきたことに気がついた。雑草ではなさそうな芽が多く出てきて、それが嘗て植えたことのある花の苗であることがわかった。その後は雑草だけ抜くことにしてあとは草が自然に育つことに任せることにした。そのためか整然とは咲いていないが、いろいろな花が元気よく咲いている畑となった。ここの土壌に合う草花も次第に分かってきた。
コスモスは放っておいても芽が出てきて秋に咲いてくれる。球根類は手間をかけなくてもどんどん増えるので有難い。私の花いじりはそのようなレベルだが、始めて6年経って大分花畑らしくなってきた。
花の中で私の最大の協力者は梅雨時に咲く野生の立ち葵だ。初めは花好きの漁師が道端に植えたものらしいが、生命力が強いので町内に広がり続け、今では乙舳町の名物にまでなっている。
この立ち葵がその時期にはお花畑を一層引き立ててくれる。
小さな花畑はキャンパスのようだ。今年の春は40本のチューリップが咲いた。「いつまで続くことやら」という目を意識しながら花いじりを続けている。