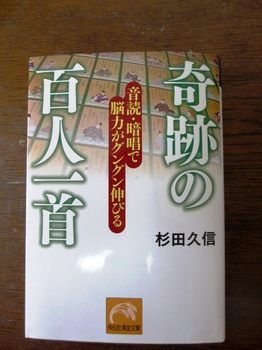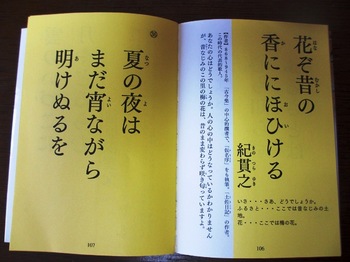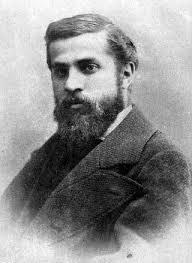【寄稿 エッセイ】 社宅も良し悪し : 月川 力江
九州から東京へ転勤の内示があった。社宅が二軒あるので選んで下さい、と物件が提案された。
一軒は世田谷区の梅ヶ丘に一〇〇坪の土地で、木造二階建ての古い家。もう一軒は東京二三区外のマンションだった。夫は頭から世田谷を希望する。理由は見えみえで広い庭にゴルフ練習用のネットを張るつもりだ。私は広い土地は落ち葉の掃除や、草取りを考えただけでも嫌だった。
都心から離れていても私はマンションが良いが、やはり夫の希望通りで世田谷を選び、東京へ来た。
落ち葉の時期を想像すると、頭が痛くなるほどの大きな木がある。家は古いが、立派な建物で、玄関脇の応接間はレトロな感じで電灯のスイッチひとつでも陶器のしゃれたものだった。
1ヶ月もしない頃、夜遅くお風呂に入った娘が「きゃ~っ」と大きな声を出した。
戸外で誰か怪しい足音がすると言う。庭の表側はきれいに清掃されていたが、裏庭はたくさんの枯葉が積もっていた。娘はすぐに110番に電話をした。その後は裏庭も掃除をして、お風呂も早い時間に入ることにした。
その後しばらくたって、朝起きてすぐに外玄関の郵便受けに、新聞を取りに行ったら白い物が落ちている。何だろうと近づくと、それは私の下着だった。
(あ~っ、しまった)と思った。前の日は家族で外食して帰りが遅くなり、洗濯物を取り入れるのを忘れていた。すぐに裏庭の干し場に行くと、夫と息子の物だけがある。朝食の時、
「昨夜、下着泥棒に入られて女性用の下着だけを盗まれたのよ。多分急いだのでしょうね、私の下着を落として行ったのよ」と言ったら息子が、
「落としていったのじゃないよ、お母さんのは捨てていったんだよ」
「え~っ どうして? 女性二人の下着やブラジャーなどをしっかり胸に抱えて逃げる時、慌てて落としたのよ」
「そうではない、『こんなババ用はいらない』と捨てたんだよ」
「ババ用じゃない、私のだって薄いピンクと淡い藤色よ」
「彼等は女の子の可愛いい花柄や、ビキニが欲しいんだよ」
側にいる夫はニヤニヤしているので、助けを求める気持ちで、
「貴方はどう思いますか?」
「俺はお母さんを傷つけるような事は答えない」
「それは答えたも同じじゃないですか」
家族四人で爆笑した日曜日の朝だった。
その後、数日たって私は家族には内緒で、夫と私の下着を干したままにして試してみた。
あ~ 下着泥棒は我が家には見向きもしないで素通りした。
エッセイ教室 2015年5月