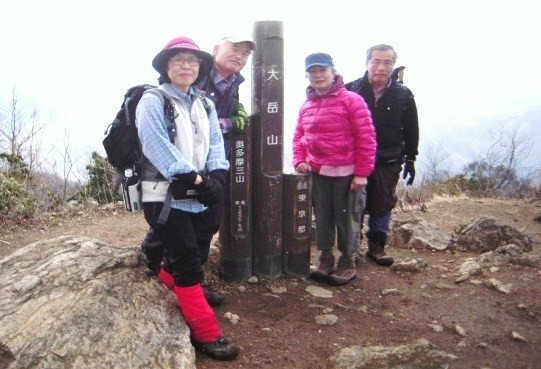【寄稿 エッセイ】免許取得 = 奥田 和美
車の普通免許を取得してから40年近くなる。スピードが好きで、女としては運転がうまい方だと思っている。
インドネシアに4年間住んでいて、いよいよ帰国する頃、車の免許を取得しようと思った。帰国したら、夫の実家に同居する予定だった。そこは駅から徒歩で三十分、バスを使うと十五分ほどの所だ。その上、坂が多い。車の免許は必需品である。
40年前のインドネシアでは、外国人は車の免許が取りやすいと聞いていた。好きな車種
が取れるから、日本の男性で大型免許まで取った人がいたそうだ。
教習所はなく、練習する広場があって、自分の車で運転の練習をするのだ。夜、夫に運転してもらい、その広場に行ってから私が運転する。エンジンのかけ方、アクセルの踏み方、ブレーキのかけ方、ライトの点け方、ハンドル操作などを教えてもらう。坂道発進を特訓した。一週間ほど練習して、試験場に行った。
夫は仕事中だったので、ディ(運転手)と一緒に出かけた。まずは標識の絵の描いてあるパネルの前に行く。試験官が指し棒で、
「これは何?」と尋ねる。私は片言のインドネシア語と手真似で、
「右折です」
と応えた。
「これは?」
「一方通行です」
試験官はあちこちと棒を指す。そのうち、
「これは進入禁止だね」
「はい」
「駐車禁止だね」
「はい」
次々と質問するが、私はうなずくだけでよかった。
いよいよ実施試験だ。ディが車を試験場に運ぶ。彼は心配して助手席に座ったが、試験官に車から出るように言われた。私は一人で運転するのだ。ディは窓にしがみついて、
「奥さん、そっとだよ、そおっと」
とアドバイスしてくれる。
前に進むのはできた。次にバックをしなさいと言われた。バックの練習はしていなかった。ハンドルをどちらに切ればどう動くかわからなかった。右に切ればバックは反対だから、左に行くだろうとアクセルを踏んだ。試験官がいない方向にと思ったのに、車はグンと動いて彼の方に向かった。
「ワーッ!」
大きなざわめきが起きた。試験場には大勢の受験者がいた。建物の屋上に鈴なりになって実施試験を見ている。順番を待っている現地の人たちだ。
「この奥さんは、本当は運転ができないんだ」
ディが告白した。
その後、誰がどのように手続きしたのかわからないが、免許証は十日ほどして私の手元に届いた。
帰国して、日本の普通免許に切り替えてもらう。パスポートや住民票を持って試験場に行った。筆記も実施試験もないはずだが、不安でいっぱいだった。
やっと日本の免許証をいただいた。ほっとした。試験場を出るとき、誰かに呼び止められるのではないかと、後ろ髪を捕まれた思いだった。