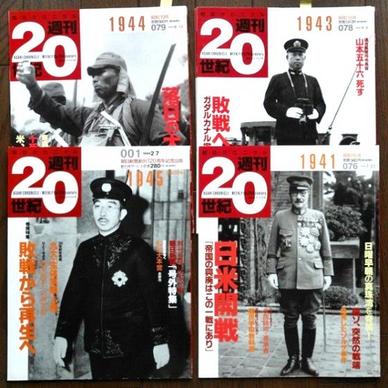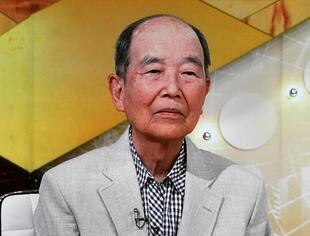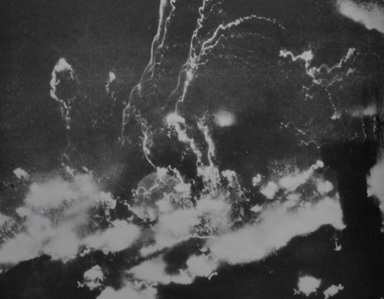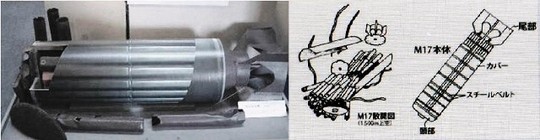【寄稿・エッセイ】故郷への墓参、文化文明日本の見事さ=二上薆
「お盆の休日、お墓参りをしましょう。車を出しますよ」
三男の温かい言葉にのって天候定まらぬも何とか晴れ間のある日、没落した生家のあった埼玉県岩槻の墓地を訪ねた。
車は出発点逗子市のガソリンスタンドに立ち寄る。ガソリンスタンドはほとんど立派な自動操作機で操作人員は一人か二人に過ぎない。それから横須賀羽田の湾岸高速道路を走る。道路は海岸を埋め立ててつくられたと思われる幅広い立派な道で横浜近辺の工場の煙突が海岸に立ち並び、いくつかの立派な鉄筋コンクリートの建物がならぶ。
横浜港付近の鉄橋はキチンとした溶接鉄板が施され、やがて羽田空港近くのトンネルを通過して道は埼玉方面に向かう隅田川沿いの見事な道路に入る。 川縁は緑の絨毯のようなあざやかさ、その先には鉄筋コンクリートのビルが連なる。やがて東北高速道路沿いの道に入り岩槻方面への静かな道に入る。
江戸から日光東照宮へ至る、第一の拠点埼玉県岩槻町は太田道灌が岩槻城を築き明治時代県庁所在地として活躍した。さらに東北線列車の要駅と目されたが断り雛人形の製造町となりその後、海外との連絡の拠点である無線電信の立派な建物は残したまま,さいたま市岩槻区となった。
見事な土蔵を従え、敷石と緑の芝生に飼かご部屋から出てきた見事な孔雀が戯れていたわが旧家は、没落し跡形もなくなり子女の学校入学とともに東京に移転する。幼少の子供時代。年末小作人が大勢集まっての宴会の、賑やかさ、中庭に横たう庭池の掃除のさわがしさ、幼児の想い出は尽きない。
菩提寺芳林寺は、祖父の建設した立派な墓石と永代供養の大きな石碑が残る。幼くして失われた姉たちへの別れを悲しんで東北線列車で墓参りした母親のお供の思い出が忘れられない。息子和尚がシベリアに抑留されてなかなか戻れないなどと前代和尚様の奥様と親しいわが母との語りも。
座敷に上げられ、町の名店の最中をいただき,寺の花畑からご供花頂き、御線香も差し出され大きな本堂にあるわがご先祖様の仏壇をまず拝んでから、大きな先祖の墓碑に参ったこと。墓碑のすぐそばは大きな森林であったが戦多くの新墓が建設され、本堂も⒋年前の東北大震災で倒され、寺は有料現金をバックアップする融資会社とつながって先祖慰安の仏事もそれぞれの費用をそのたびに請求され、永久扶養の石碑は形骸と化しており仏事は指定会社の指定する店で行われ費用も現実に参加者各人に、直に要望されるようなしきたりとなってしまった。
文化文明の豊かなビジネス国家日本、敷島の大和心は?
この考え方は朝河貫一の日本の禍記にも強く怖れられた考え方と強い共通認識がある。太平洋戦争の悲しみとともに、高年者、長期入院とともに筆の遅れ、いとしむ畏友の温情に改めて深い感謝の謝意を表したい。