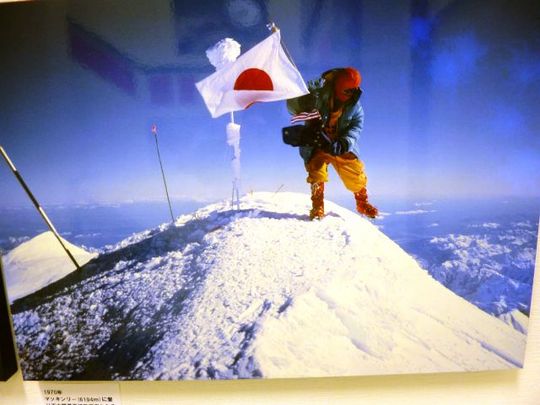【寄稿・写真エッセイ】 雨の柴又を歩く (上) = 阿河 紀子
ずっと京成沿線に暮らしている。それにもかかわらず、私は金町線に乗るのも初めてなら、柴又を歩くのも初めてだ。だから、「朝日カルチャーセンター千葉」主催の「柴又を歩く、撮る」の講座を楽しみにしていた。
当日は、あいにくの雨だった。その上、寒い。気分は上々と言うわけには、いかない。
「せっかく来たのだから、楽しまなければ」
と自分で自分を盛り上げながら、「柴又」の駅で下車する。
講師は、「写真エッセイ」でお世話になっている「穂高健一先生」である。

日本ペンクラブに所属する、高名な作家だと言うのに、先生自ら、テンション低めの受講生を盛り上げようと道の真ん中でポーズをとり被写体になる。
これでは、雨が降っているからと、私がテンションを下げてはいられない。本日のテーマは、「動きのある写真を撮る」「主役と脇役を考えながら撮る」である。
さぁ、気を取り直して、出発だ。駅前には有名な寅さんの像がある。
さっそくカメラを構える。ここで私たちが撮りたいのは「記念写真」ではない。
寅さんの像と撮られる人、撮る人との関係、場所や時間、季節などを説明無しに、どこまで表現できるかに挑戦する。難しい。
次から次へと、観光客が寅さんと一緒に写真を撮る。どの顔も笑っている。
寅さんは、今でも変わりなく人気者だ。
私たちが、カメラを構えているので、通りがかる人すら、カメラを意識する。
この若いカップル、一旦、寅さんの前から立ち去ったのに、再びカメラの前に登場する。
どうしたのかなと、様子を見ていると、どうも彼女の方が、カメラマンたちのモデルになろうと彼氏をそそのかしたようだ。
彼女の堂々としたモデルっぷりに比べて、彼の方は、目が泳いでいる。主導権は彼女にあるようだ。
心の中で「彼氏、頑張れ」つぶやきながら、小走りに一行を追いかけた。
帝釈天に続く雨の商店街は、予想以上に人通りが多かった。
軒先で一杯やっていた3人連れに穂高先生が「撮らしてもらっていいですか?」と声をかける。
快くモデルになってくれた。
私はこの眼光鋭いおじさんが気になって仕方がない。
「3人のご関係は?」
と尋ねると、その辺はうまく誤魔化されてしまったが、青年がモンゴル出身の「元力士」だったことを教えてくれた。
彼は引退後、100キロ以上あった体重を、ランニングでここまで減量したそうだ。
さらに行くと香ばしい美味しそうな臭いが鼻をくすぐる。焼き鳥やさんだ。通りがかる人が、思わず笑顔になっている。
焼いている彼の真剣な眼差しや、綺麗な手、繊細な指先に、私は、しばし見とれる。
先生は「煙を撮れ」と言う。
動きを煙で表現するのだ。
「くし刺し3年、焼き4年」などと言われている。
彼に「焼きになってから何年?」
と尋ねると、にっこり笑って「4年」と答えてくれた。
もうすぐ店を任してもらえるのかもしれない。
「頑張ってね」
と声をかけると、恥ずかしそうに頷いた。
【つづく】