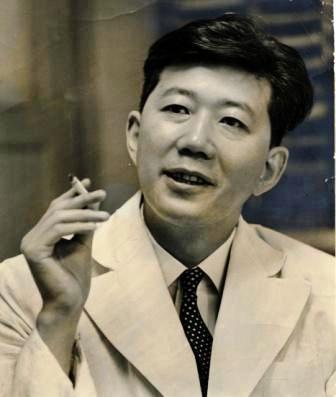日時:2015年7月28日(火)~31日(金) 3泊4日・曇り時々晴れ(一日目は一時雨)
メンバー : L佐治ひろみ、武部実、岩淵美枝子、脇野瑞枝、関本誠一 (計5名)
コース
【一日目】室堂~一の越~五色ヶ原山荘(泊)
【二日目】五色ヶ原山荘~越中沢岳~スゴ乗越小屋(泊)
【三日目】スゴ乗越小屋~薬師岳~太郎平小屋(泊)
【四日目】太郎平小屋~折立

今回行く薬師岳は、日本百名山とともに、花の百名山にも選ばれており、北アを代表する縦走コースに鎮座する山の一つだ。
薬師岳という山名は各地に多数ある。そのなかでも、最高峰で、人気ある山だ。ちなみに第2位は鳳凰三山の一峰(2730m)。
【一日目】
今春に開通した北陸新幹線で、富山駅についた。駅前のホテルで前泊する。
朝6時発の直行バスで、室堂に入る(9:30)。BT前で、水を補給してから出発する。しかし、学校登山の生徒さん達と一緒になって、思うように歩けない。
一の越でこの渋滞から逃れ、五色ヶ原に向かう。
天気は予報に反し、徐々に悪化する。鬼岳の雪渓をトラバースする頃は、見通しも悪くなって、雪上ステップを作ってくれた山小屋の尽力に感謝しながら、慎重に進む。
獅子岳を超え、まもなくザラ峠だ。戦国時代の武将・佐々成政の「さらさら越え」で、有名とか……。昔日伝説に思いを馳せながら、小休止する。ここからゆるやかな登りで、五色ヶ原だ。
この一帯は最盛期過ぎたと言っても、20種類以上の高山植物の宝庫で、咲きほこっている。
小雨降るなか、五色ヶ原山荘に到着する(16:00)。雨具などを乾燥室に干し、落ち着いたところで無事到着の乾杯!
【二日目】
5時起床。6時半に出発する。ここからエ久ケープない領域を進む。天気も回復して、登山道のまわりはお花畑が連続している。
鳶山を過ぎると、越中沢乗越に下り、次のピークである越中沢岳に到着(9:30)。ここで小休憩した後、急斜面を下ったところで、ランチタイムとなる。
さらに下ったのち、スゴノ頭の手前をトラバースした後、急な下りになる。鎖や梯子の難所だが、注意して下りきる。スゴ乗越に到着(13:00)。
休憩中、来年は日本縦断トレランにエントリー(予定?)のアスリートが通りがかる。かれらにコースタイムを聞いてビックリした!
剱岳の早月尾根を深夜に出発し、一日でスゴ乗越小屋とは……。その超人ぶりと、レースの厳しさを痛感する。
ここから緩やかに登ると、小屋に到着(14:10)。
【三日目】
5時に朝食をとった後、6時に出発。
今日は薬師岳に登る日だ。間岳、北薬師といくつかピークを越えるが、疲れも溜まって、一番キツイところだ。
今回の楽しみの一つの雷鳥に、まだ会ってない。遠くの雪渓に鳥らしきものが見え、鳴き声は聞こえるが確認できない。
標高3000m近いのに晴れると、日差しが強く、雷鳥も悲鳴をあげているような思いがした。
薬師岳に近づくにつれ、風が冷たく、一時は視界不良になった。山頂に到着した(11:10)ころには、雲が取れ、一瞬の晴天景色を満喫する。
薬師岳は北アルプス有数の大きな山だ。東側は氷河の痕跡(カール)があり、国の特別天然記念物に指定されている。
山頂には薬師如来を祀った小さな祠がある。三角点は祠の影に設置されていた。
下りは緩やかな南斜面を行き、途中の山荘で、昼食をとる。やがて、太郎平小屋に到着(15:00)。
【四日目】
折立へと、薬師岳、剱岳、それら立山連峰を眺めながら、整備された道を快調に下って行く。 折立に下山した(9:35)。最寄りの温泉に立ち寄り、反省会をする。
北ア山歩を無事に踏破した。名残惜しみながら、帰宅の途へ…お疲れさまです。
ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№194から転載
 青年を脱ぎ捨て
青年を脱ぎ捨て