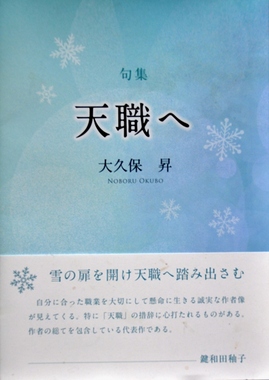標高2,415mから海岸Om 北アルプス北端・栂海新道縦走=栃金正一
1.期日 : 2016年7月26日(火)~29日(金)3泊4日
2.参加メンバ : L佐治 関本 藪亀 栃金
3.コース : 7/26日 移動日 平岩駅(バス)~白馬岳蓮華温泉ロッジ
7/27日 白馬岳蓮華温泉ロッジ ~ 白高地沢 ~ 花園三角点 ~ 吹上のコル ~ 朝日岳 ~ 朝日小屋
7/28日 朝日小屋 ~ 朝日岳 ~ 吹上のコル ~ 長栂山 ~ 黒岩山 ~ サワガニ山 ~ 犬ケ岳 ~ 栂海山荘
7/29日 栂海山荘 ~ 菊石山 ~ 下駒岳 ~ 白鳥山 ~ 尻高山 ~ 入道山 ~ 親不知海岸

【7/26】 今日は移動日で、平岩駅からバスに乗る。白馬岳の蓮華温泉ロッジに着くころは、雨が降ってきて、明日の山行が気にかかる。
【7/27】 早朝5:00の出発時には、ほぼ雨は上がっていた。
ロッジ前のキャンプ場への道を進むと、整備された木道に出る。滑り易い木道を慎重に下り、いくつかの湿原を抜けると、大きな白高地沢の河原に出る。
河原で休憩し、急斜面をグングン高度あげながら登ると、視界が開け、色とりどりのお花畑のなかに花園三角点を確認する。
ここの水場で早目の昼食をとる。ここからは、五輪尾根を一気に登り、山腹をトラバース気味に行くと、栂海新道の分岐である吹上のコルに到着。休憩の後は、広い歩きやすい斜面をジグザグに登って行く。
13:30、朝日岳に到着する。山頂は広々していて、展望指示盤がある。記念写真を撮り、朝日小屋に向かう。
広い平原のなかに建つ赤い三角屋根の、朝日小屋には14:20に到着した。
【7/28】 朝日小屋の豪華な食事をいただき、朝日を浴びながら、5:30に元気に出発する。6:30、朝日岳山頂に到着した。白馬岳、雪倉岳、剣岳・立山連峰が良く見える。
7:00、吹上のコルに到着。ここからいよいよ長い栂海新道に入る。シラビソの林を抜けると木道になり、照葉の池があり、周りはキスゲ等のお花畑になっており、とにかく美しい。
道は登りになり、途中ですこし道をそれ、長栂山に立ち寄る。アヤメ平の小さな雪渓を越えると、広々とした黒岩平の平原に出る。
ここで冷たい水を補給し、急斜面を登ると、黒岩山に到着。ここからは登り、下りの多い稜線を行く。サワガニ山を登り、北俣の水場で水を補給し、さらに犬ケ岳を登り、14:20、栂海山荘に到着する。
自炊だが寝具もあり、ゆっくりと寝られた。
【7/29】 早朝5:00に出発する。途中、黄蓮の水場で水を補給し、菊石山を過ぎ、急登の下駒岳を登り、小屋の建つ白鳥山に到着する。
ここからは下りとなり、標高が低く、とにかく暑い。最後の水場となるシキ割の水場で、水を補給し、尻高山を経て、最後のピークである入道山を登る。
栂海新道の入口のある国道8号には、14:20に到着。さらにここから海岸を目指し、階段を下り、目標の日本海海抜0メートルの親不知海岸に、15:00に到着した。
朝日岳から親不知海岸まで下る、お花畑でいっぱいの長大な尾根歩きを全員が無事に、縦走できた。天気にも恵まれ、思い出に残る山行となりました。
ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№206から転載