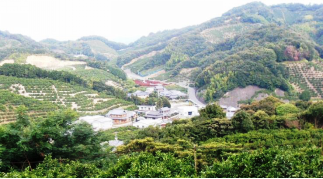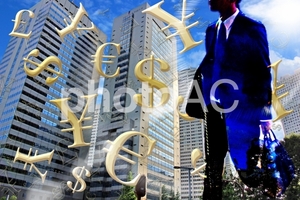【寄稿・掌品】 春終の三段峡 = 広島hiro子(1)
峡の春終は、智子にとり、かつて感じたことのない別物の趣きを放つことになる。
同じ景色でありながら、連れ行く人によって、情感の機微というそれぞれの彩が添られてゆく。心に映し出される風景は単なる色ではなく、こもごもの想いと共に、忘れ得ぬ一枚の絆をうつす瞬間だった。
それはどんな人間にも、ひとつあるいはいくつかを持っている自分自身にしか見ることができない風景なのだ。
 とおにソメイヨシノの見どころを過ぎた広島市内では、緑の桜葉に勢いを増し始めてきている。が、さすがに広島の奥地に位置する三段峡だけに、今が桜の盛りだ。
とおにソメイヨシノの見どころを過ぎた広島市内では、緑の桜葉に勢いを増し始めてきている。が、さすがに広島の奥地に位置する三段峡だけに、今が桜の盛りだ。
三段峡行きの路線バスの終点で降り立つと、智子はあたりを見渡した。
小さな古びた商店が数件並ぶ。例年よりは遅い桜の見ごろだと茶屋の主人が話してきた。今日は4月21日、春の終わりといえそうだ。
5月となれば、それは初夏の様相に変化する。今は残り少ない春を満喫するときだった。三段峡の桜は日本古来の山桜だ。自然特有の透けて見えそうな淡い色合いの花びらが、少しばかり舞いながら、まばらに訪れる客たちの歓迎をしているかのように見えた。
人ひとり分の間を空けて智子の前を歩くのは、今回の旅の友となった4歳年上の後藤信弘であった。
中背でもやや猫背に歩くために小さく見えたその後ろ姿は、25年前に見たまだ若かりし日の彼とあまり変わりない。変わったとすれば、顔こそしわを刻み、男性の割にはまつ毛を蓄えた美しい目であったものも瞼の筋肉が衰えてややたれ目がちにと変化してしまったことだろう。
50代半ばにして贅肉に悩まずに済んだのは、今に至っても裕福でいられなかった暮らしぶりからなのだろうか……。世間体ばかりを気にしていた元姑や後藤家一族の面子が思い浮かぶ。
後藤は、智子の25年前に別れた元夫であった。あまり余計なことは考えるまいと智子は思った。
(わざわざ松山から私に会いに来たのは、別れた息子の様子を知りたいためなんだから。でも、昨日、仕事中に会社の電話から呼び出されたときは心臓が飛び出るかと思うほどびっくりした。それにしてもわたしの仕事のミスが見つかって課がもめているときに架けてくるなんて、ほんとうに間の悪い人……)
一昨日の職場でのミスは痛かった。信託銀行でなくとも金融機関であれば、基本中の基本とされるルールである、
高齢者にリスクの高いものを勧めてはならないという絶対の決まりを、智子は単なる不注意であっさりと犯してしまっていた。昨日の昼に、総務から呼び出され、ぎゅうの目にあわされているさなかに、間の悪いあの人から連絡があったのだ。
開口一番に彼は言った。
「佑が結婚したと聞いたよ。はやめに時間をくれないか?」息子の結婚式は、もう一年近く前にすでに済ませている。実の父親の顔も覚えていない佑は、生みの父を結婚式に呼ぶ選択肢を持たなかった。
それは、智子とても同じことで、話題にさえ上らないものだった。智子の再婚後の結婚生活は20年にも及んでおり、後藤とのほんの1年半の生活は過去のものでしかなかったのだ。しかし、結婚式の招待はおろか、25年もの間一度も会わせる機会をもたせなかったことへの負い目が、智子を前向きにさせていた。
「いいよ、いつがいい?」
「急だけど・・今晩がいい」
こんな忙しい時に、やっぱり勝手な奴だとイラつき加減に思いながらも、夜にファミレスで会う約束をした。電話を切ってからも、法令違反という重大違反の文字が踊り、目がぐるぐるまわりそうだった。
今日の週末休日をはさみ、来週には本社への経緯書の始末や支店長をはじめとする上司たちの検印という詰めが待っている。考えれば考えるほど、胃がざわめき、気が滅入る。50歳を過ぎた年齢のせいにはできないが、智子はどの同僚より失敗を繰り返す問題社員であることにまちがいはなかった。
 現社会は女性活躍が持てはやされている。一般人から見れば、大企業に勤める花のキャリアウーマンと見られ、羨む職業なのだろう。しかし内情は相反して、同じ職場内において格差が定着している金融機関特有のドロドロした側面も持ち合わせていた。昔で言う窓際族であった。
現社会は女性活躍が持てはやされている。一般人から見れば、大企業に勤める花のキャリアウーマンと見られ、羨む職業なのだろう。しかし内情は相反して、同じ職場内において格差が定着している金融機関特有のドロドロした側面も持ち合わせていた。昔で言う窓際族であった。
魔の金曜は、仕事を終えても智子を落ち着かせなかった。二時間余り、夜のファミレスで互いの状況を話しているときも、後藤にまで責められるのではないかを身構えさせていた。
「俺なんか、悪いことは山ほどあったと思うよ。でも考えないことが一番だね。
いつかは時間が解決することが大半だ。そのままにしておけないことは片づけるとしても、感情的な落ち込みには、時間薬が一番だから。」
「ふうん、そうよね、わかっているから」
「わかっている顔には見えないけど?」
「私のことは、あなたと関係ないでしょ」
学生が多いファミレスの手前、小さく小声で話していても、智子の言葉はやはりドげドげしい。後藤もそれなりに負けてはいなかった。
後藤はコーヒーを飲み干すと、おもむろに煙草を吸い、横を向いたまま智子に言
「もう、帰ったほうがいい。ご主人に心配かけないように。今日のところは何も考えずに寝てくれ。その代わり、明日は休みだろ?久しぶりの広島だから、春の渓谷を堪能したいな、一緒に案内しておくれ。君もストレス発散した方がいいしね」
(前の呼び名、智、よびすてだったな。今は君、なんだ。……)
ふと昔をよぎる思いを断ち切るように智子は言ってのけた。
「タダの観光ガイドって、ほんと、相変わらず強引だわ。昔から私の意見なんて聞く耳持たないからこうなったっていうのに。でも、お互い配偶者も別の子供もいるんだから、今さら二人の縁なんてもうないけどね。お餞別に付き合ってあげるわよ」
後藤は礼も言わず、黙ってうなずいた。
半ば強引に三段峡の観光案内を押し付け、その夜はホテルに帰るという彼の口から、その日のうちに旅の目的を切り出すことはなかった。
翌日を迎え、薄曇りではあったものの、三段峡は山桜の見ごろだった。智子にとっては、正直せっかくの休みを返上され、うっとうしいというのが本音だったかもしれない。
それでも、なお癒しを必要とする智子のためにゆっくりと歩いているのだろう後藤の後を、智子は言葉もなくついて歩いた。ぬぐい切れようにないもやもやは仕事だけではないことを智子自身、気が付いてはいなかった。そんな複雑な悩みを抱えたままの智子と比べ、4月後半を過ぎ、遅い春の盛りを迎えた渓谷は、薄雲を交えつつ智子とは対照的に明るかった。
最初の入り口である赤い大橋から、透き通る豊かな流れが一面に拡がる。涼やかな風になぶられ、新緑の木々を軽やかに揺らす山のやさしさと、岩々をごうと勢い流れる力強さが、一挙に別世界を感じさせた。
後藤がゆっくりと先に歩をすすめているのを気にも留めず、智子は橋の下をのぞき込んだ。さすがに渓谷だけあって、流水をうけながらも岩々の模様を惜しげもなく見せつける。悴んでいた智子の五感を、くすぐっていくのが解かる。たった数十歩、別世界に入り込んだだけでも、雄大な自然の片鱗を受け、智子の何かが変わっていくのを感じた。
【つづく】