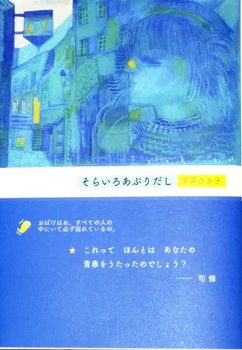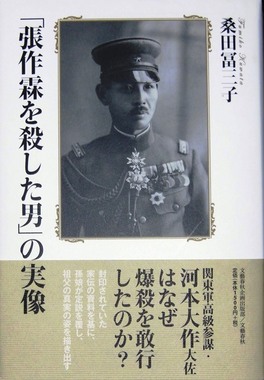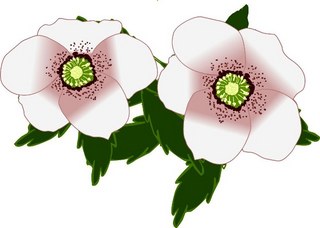【元気に百歳クラブ】 最後の海外二人旅 武智 康子
眼下に見えるのは、一面緑の草原、ところどころに深緑の森があり、赤い屋根が点在する田園風景である。そのはるか向こうに二本の滑走路が見える。アイスランドとは全く違う長閑な風景の空港である。
ここは、スコットランドの首府、エジンバラの郊外である。
夫と私は、アイスランドからロンドンに戻った三日後、私の希望もさることながら夫のもう一つの夢を叶えるため、スコットランドとイングランドの旅に出たのだ。
まず、空港から四キロほどの所の田園と森に囲まれたホテルを目指した。それは、翌日からこのホテルを出発点に四泊五日の現地のバスツアーに参加するためだ。
夫は、現役時代にスコットランドの鉄鋼会社の人に、エジンバラの高齢夫婦の愛のベンチの話を聞いていたので、それを自分の目で見たかったのだ。
参加者の大半は欧米各国からの人たちだが、その中に一組の日本人の新婚カップルがいた。海外旅行が初めてで不安そうだった彼らとは、この旅行が縁で今も文通が続いている。
バスは、緑の田園風景の中をエジンバラに向けてひた走り、街の中に入った。エジンバラ城は丘の上にある。坂の手前でバスを降りた私たちは、なだらかな坂をゆっくりと歩いた。私は夫に話しかけた。
「あの老夫婦も毎日こうやってこの坂を、上っていたのですね」と。夫も「多分、そうだね」といった。
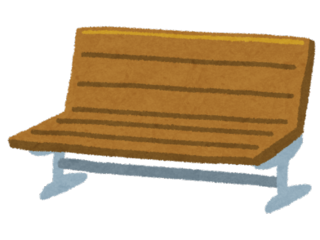 城の見学の後、私たち夫婦は庭園でそのベンチを探したが、見つからなかった。
城の見学の後、私たち夫婦は庭園でそのベンチを探したが、見つからなかった。
ガイドに尋ねると、そのベンチは坂の下の市民公園に移されたと、教えてくれた。私たち二人は、ちょっとだけでもそのベンチを見たいと、ガイドに頼み一足先に坂をくだった。
公園に入ると、入り口近くの大きな樹の下に幾つものベンチが並んでいた。そのうちの手前のほうの三つのベンチに、金属のプレートがつけられていた。古いのには、
「レテラ ラマーラの思い出の標
彼女は、夫と家族を愛し 二人はいつもこのベンチに座っていた。一九七三年二月十二日 他界」
と、あった。
夫は感慨深そうに眺め、私たちも座ってみた。何だか心が温かくなるような気分だった。
翌日は、新緑の森と湖と田園のスコットランドの湖水地方をめぐり、気分を癒してイングランドに入った。
まず最初にウエジウッドの工場で正式のアフタヌーンテイーを楽しんだ。
そして、ビジターセンターで私がいつものように新しい柄のコーヒーカップを二客求めている間に、このような店であまり買い物が好きではない夫が、自分のカフスボタンと私のためのペンダントを求めてプレゼントしてくれた。
私は嬉しかった。
今となっては、夫からの思い出の最後の贈り物として、カフスボタンとともに大切にしている。
そして、バスは南下して、いよいよ観光客の多いシェックスピアの街に入った。
しかし、シェックスピアセンターに入った途端、私の足が止まった。それは、看板の説明が英語より先に中国語の説明があったのだ。
私は、違和感を感じた。聞けば、中国からの寄付があったとのことだが、シェックスピアは世界的に有名な英国の作家である。
日本語の説明はなくとも、つたない英語力で英文を理解しようとした私には、ちょっとばかり悲しかった。しかし、中庭では、シェックスピアの戯曲「ベニスの商人」が演じられていた。もちろん英語である。私は、なんとなくホッとした。
その後、バスはバースやストーンヘンジ、コッツウオールズなどを回って、ロンドンに到着。皆と一緒の長旅は終わった。
ガイドの気配り、各国の人々との絆、見学以上に得ることが多かった素晴らしい旅だった。
夫とわたしは、ホテルに再チェックインして馴染みの日本食レストラン「菊」で久しぶりに日本食をあじわった。
次の日の午後、余りの爽やかな天気にリーゼントパークを散歩した。すると白と淡いオレンジ色が混じった花が咲いているマロニエの木の下に、エジンバラと同じようなベンチがあった。二人はそこに座った。
「こんなにゆっくりした海外旅行は、初めてですね。今までは、若さに任せて、また、欲張って走ってばかりでしたものね」
「そうだね。今度は、アイスランドにオーロラを見に行こう」
と、夫は話していたが、もう二度と海外二人旅はできなくなった。
だが、いつも海外出張では忙しくて行くことができなかった、夫の二つの願いを叶えられたこの旅が、私への大きなプレゼントとなって、今、私の心の支えとなっている。
イラスト:Googleイラスト・フリーより