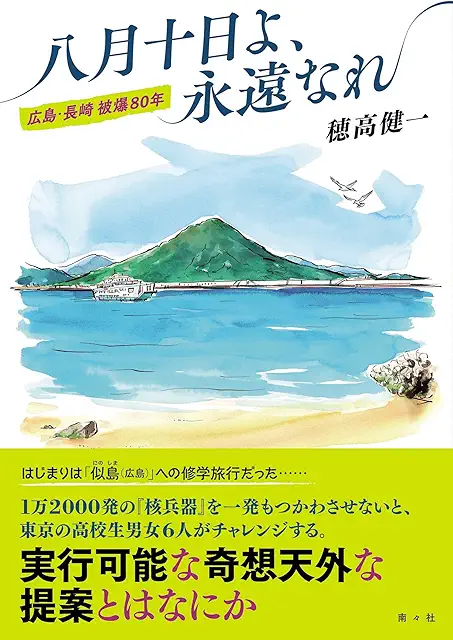【寄稿・エッセイ】 上野駅 = 横手 泰子
昭和21年4月1日、私は両親、妹二人の家族5人、台湾からの引き揚げ船で鹿児島に上陸した。そこから祖父母の住む青森まで、日本列島の列車移動が始まる。鹿児島の街は焼け野原だった。広島は黒焦げの立木だけが目についた。列車は買い出しの人でギュウギュウ詰めだった。
 上野駅に着いたとき、2日間休息した。待合室のコンクリ床に敷物を敷いた上で躯を休めた。そこには各方面から引き揚げ途中の数家族が入っていた。その中のある一家は、家族全員、豪華な毛皮のコートを着ていて、熱帯で育った私は眼を見張った。
上野駅に着いたとき、2日間休息した。待合室のコンクリ床に敷物を敷いた上で躯を休めた。そこには各方面から引き揚げ途中の数家族が入っていた。その中のある一家は、家族全員、豪華な毛皮のコートを着ていて、熱帯で育った私は眼を見張った。
植民地で育った私は、日常、『内地』という言葉を聞き続けた。『内地に帰る』ということに大きく夢をふくらませた。しかし、現実の夢は次々と破られた。
食事時になると、私たちにはきちんと食べ物が手渡された。すると、待合室の入り口にポツリポツリと子どもが立ち始める。アッという間に半円型の人垣が入り口をふさぐ。どの子どもも髪はボサボサ、やせ細った手足はアカまみれ、着ているものも大きすぎたり、破れていたりで汚れ放題なのだ。
私と同年代と思われるのに、子どもらしさなどまったく感じることはできない。その人垣を、私たち引き揚げ者の世話をしてくれる青年が「コラーッ」と追い払う。一瞬散り散りに立ち去るが、一日数回はイタチごっこが繰り返される。
浮浪児と呼ばれた彼らは、空襲で親を失った子どもたちなのだ。全員が空き缶を手に持ち、タバコの吸い殻を拾い歩く。食料はおそらく目につくと、掠め取るしかなかったのだろう。そのせいで世間から忌み嫌われたに違いない。
気がつくと、父が見知らぬ男性と話をしていた。そのうち、その男性が風呂敷をほどいて弁当箱を取り出した。ふたを開けると、パチンパチンと弁当箱を分解した。その中から現れたのは、久しぶりに見る真っ白いご飯だった。私はその白いご飯より小さくまとめられた弁当箱にびっくりしていた。
父の話によると、その人は「所用で松戸から出かけてきたが、用事が早く片づいてもう帰るので弁当は不要になった。お子さんたちに食べさせてあげてください」との嬉しい申し出だったそうだ。
私たちには両親もいて、支援組織もついている。孤児たちはだれも守ってくれる人もいないのに、なぜその白いご飯を私は食べたのだろうと、思い出すたび、長年後ろめたさを感じ続けた。
次の日、駅を出て、向かい側にある食堂にうどんを食べに行った。食堂はバラックと呼ばれた焼け跡の廃材を集めて造られており、道に面して一列に並んでいたが、その後ろ側には焼け跡が拡がっていた。店に入ると「食券を!」と言われて、母が大切そうに食券を渡すと、人数分のうどんが出てきた。店に入ってくる人は全員、『食券』の提出を求められていた。
昭和36年、結婚した私は、東京に住むことになった。東京生まれ、東京育ちの夫のあとを追いかけ、都内のあちこち歩き廻った。
その時はもう、東京の街は、焼け跡などなかったようにきれいになっていた。やがて子どもをつれてパンダを観に動物園へ、恐竜の骨を観に科学博物館へ、正倉院宝物展は国立博物館、音楽会、美術展と、上野には何10回と出かけたが、公園口ばかり利用するので、思い出すことはなかった。
ある日、浅草からバスに乗って降りたところが上野駅の正面だった。石造りの円柱が並んだ風景を見たとき、「あー、ここだった」と、一瞬で記憶が甦った。柱の根元にまどろんでいた浮浪児の姿が、幻のように浮かんだ。円柱に陽があたって、その温もりが心地よかったことだろう。
世界中の紛争地の映像が流れる。親を失った孤児たちの姿に胸が痛む。かつて日本にも、街をさ迷った子どもたちがいた。彼らがその後の経済成長の恩恵を受けて、無事、人生を歩んでいてほしい。折しも櫻の季節、花見客で賑わう上野駅に、そういう歴史があったことを忘れないでいたい。
元気に百歳クラブ 『エッセイ教室』 2014年4月作品