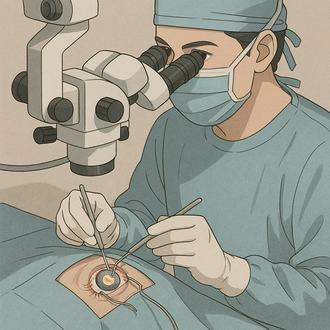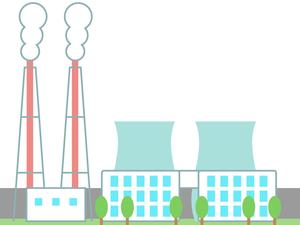【孔雀船106号 詩】 楽しい日本 田中圭介
束ねると新聞紙って重たいわ 首を傾げる地球みたいに
掌に括り紐が食い込む ひまわり畑は覚醒した骨たちの地中海性気候
あーたは草茫茫のモンスーン地帯でぼんやり目を覚まして
未だ魂が抜けたままなのにふわふわと古新聞を捨てに行かされる
頭のなかで小石を蹴飛ばし まだ濡れている小さな畑を跨いで
里芋の葉っぱの露玉と光の交点 ここは豊葦原之瑞穂国 ゴミ捨て場はそこ
傲慢に蔦延ったミントの匂いって堪らない臭いなのよね
密かに匍匐前進 辺りを窺いながら 根っこを絡ませて
胡瓜も茄子も平凡な暮らしまでいつの間にか包囲されてしまうのよ
いま俺って今日の天気図のどの辺りにいるのだろうか
夕焼け小焼けの赤とんぼで日が暮れて明日は曖昧に晴れたり曇ったり
冷たくなって硬直した古新聞は遺体のように重くなっている
罪のない幼虫だって踏み潰すのよ ここからここまでは私の畑なんだから
下心に沈殿している毒も密かに希釈し攪拌して散布するの
法蓮草を引き抜くときはニンフの顏 畑ってこうやって広げるの
隊列 台車のミサイル 人形の最敬礼 兵隊さん一つビールでも飲まないか
簡単にニュースが終わるとリモコンで選択するドラマは殺意でいっぱい
間引かれた大根の葉っぱの漬物がコッぷの横に据えられていて
あーたの世間って今朝の新聞紙なのよね
畑の方が少しだけ広いわ 空が眩しくて 無口の大根の白さが嬉しいの
地球だってまだまだ瑞々しいわ 神様って苔むしたお地蔵様お一人でいいの
囚われているのさ俺たち トマトの皮みたいに薄っぺらな大気のなか
鉄格子を揺さ振ってみる カンカン叩く 脱走できない安全地帯
新聞紙はテッシュぺーパーにリサイクルされてガラガラポンの残念賞さ
今時畑ってハウスの中なのよ 一直線に整列し季語を忘れた野菜たち
不感症の季節 計算された室温 テーブルは痛覚を失った歯の虫たちの咀嚼音
プランターに米を蒔いて水をかけていたお母さんもいたんだって
具体的に玄関のノブを回して外に出た
天と地の間は抽象的に春雨が降っている 大和ごころの美しい日本
郵便受けは裂けそうな大口で分厚い朝刊を銜えている
【関連情報】
孔雀船は105号の記念号となりました。1971年創刊です。
「孔雀船」頒価700円
発行所 孔雀船詩社編集室
発行責任者:望月苑巳
〒185-0031
東京都国分寺市富士本1-11-40
TEL&FAX 042(577)0738
メール teikakyou@jcom.home.ne.jp