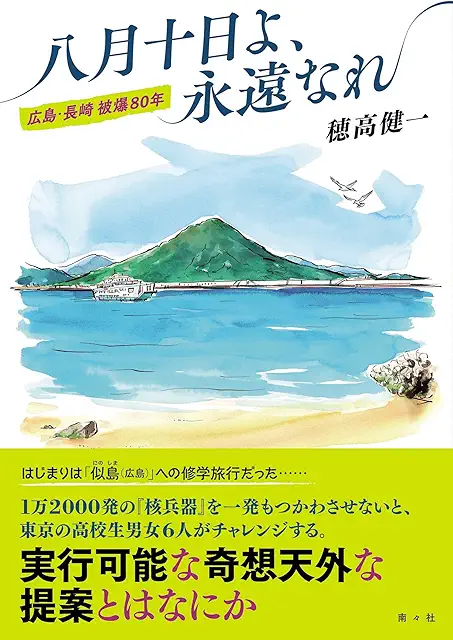小説取材ノート(3)閖上=阿鼻地獄を見てきた顔
仙台市に隣接する名取市の、閖上(ゆりあげ)漁港に出むいた。町は死んだというよりも、消えていた。視界のなかで確認できる構造物となると、破壊された東禅寺、1階が吹きさらしとなった笹カマボコの工場、そして原形が残る閖上中学校の三階建て校舎のみだった。他はすべて整地された更地で、建物の区画がわかる土台だけが残る、『無』の世界である。

「ここは魚市場だったんですよ。跡形もないけれど」
その敷地の横で、佐野謙三さんが車を停めた。閖上は赤貝、ほっき貝の有名な産地だという。
「港に係留する、漁船がまったくいなくなった。大震災の前は、この岸壁には漁船がびっしり詰まり、釣り人が竿を投げる隙間もないほどだったのに……」
と謙三さんは絶句していた。いまや漁船は10隻にも満たない。
「仙台や名取の人はだれもが、大地震のあと津波がここに来るとは予想していなかったんです」
3.11の大津波は約8メートルの高さで、海岸から襲いかかってきた。仙台平野は海岸からどこまでも平坦な地形だ。大津波の速度と勢いは収まらず、住民のほうは使い慣れた車で避難しようとした。だが、大渋滞で逃げきれなかった。
大津波は港の漁船を陸上の奥まで打ち上げ、人家をことごとく破壊し、人々の命を一度に奪っていった。数千人が逃げ切れずに死んだのだ。
7か月経ったいま、閖上の建造物や構造物の残骸や残材が、海岸の一角に集積されていた。5メートルほどの廃材の山が幾つも目立つ。それぞれ複数のシャベルカーが荒々しくつかみあげてダンプカーに積み込む。海岸から町全体を見渡しても、動きのある光景はその一連の作業しかなかった。
 周辺には古墳の形状に似た、高さ10メートルの盛り土が幾つもある。瓦礫撤廃の作業者たちが、もし次なる大津波に襲われたときに逃げる高台だという。
周辺には古墳の形状に似た、高さ10メートルの盛り土が幾つもある。瓦礫撤廃の作業者たちが、もし次なる大津波に襲われたときに逃げる高台だという。
漁港だけに、船を海上から陸に引き揚げる船台レールがある。ひん曲がっている。その先には倒壊家屋の廃材、ゴムタイヤ、布団、漁具、家具、材木とあらゆるものが山積みされていた。一区画だけでも7台のシャベルカーがそのアームをせわしなく動かしていた。
約3メートルほど離れた場所には、木製の険しい形相の仏像が一体置かれていた。しゃがんで手を合わせると、目線がちょうど合う高さだった。その顔は目がつりあがり、口もとは歪み、いまなお阿鼻地獄のなかにいる表情に思えた。
仏像を見つけた作業員が、おおかた廃棄物として処理するには忍び難く、取りおいているのだろう。安置して供養されている様子ではない。いましがた発見された像かもしれない。
私がいつまでも凝視していると、仏像のほうから、
「住民はみな平穏に生きていたのに、一瞬にして死者となり、今なお無間地獄をさ迷い、苦しみを受けている。あなたの筆で、世に知らせてほしい」
と訴えている表情に思えた。少なくとも、仏像が私の心をとらえて放さなかった。
被災地・閖上の中央というよりも、海寄りに小高い日和山(ひよりやま)があった。古より、海の見張り場所としての役目があった。 3.11の大津波では、この頂上に流された家屋が乗っていたという。
鳥居をくぐり、階段を上ると、東日本大震災慰霊の塔婆が立てられていた。供え物もあった。

日和山から見る、町並みは民家の土台だけで、その光景がどこまでも続いていた。大津波がすべてを奪ったのだ。彼方の仙台港の沖合には白波が見える。
「まるで津波とオーバーラップして見えるな……」
謙三さんがつぶやいた。
3人の女性が鳥居下からやってきた。一人は博多、もう一人は横浜、案内人は地元の人だと、それそれが話す内容から、そう読み取れた。
「だれがお亡くなりになったのですか」
こちらからそう訊くには、まだ尚早の雰囲気が残る霊地だった。3人は静かに手を合わせてから立ち去った。また、別人が来て手を合わせていた。
被災地の中央にある東禅寺に向かった。見た目にも耐震性がある強固な寺だが、庇などが崩れ落ちていた。補修すれば、廃寺にはならないだろう。
大地震が発生した時に、一度は避難した住職だったが、過去帳を取りに寺に戻り、津波に巻き込まれて命を亡くされているようだ。

同寺の墓地はまるで竜巻に遭ったように、殆どの墓柱が倒壊していた。地震直後から、いっさい手付かずの状態にある。
私の眼には、まるで「被災地の歴史保存」のように映った。少なくとも、私が最初に見た、地震・津波の惨事そのものだった。なぜ未整理なのか。想像力で推量してみた。
同寺の檀家の殆どは周辺に住む人々だろう。大津波で逝ってしまった。生きながらえて避難できた人でも、いまなお仮住まいの身だろう。おおかた職は得られず、生きているだけで精一杯。とても墓地の修復まで手が回らないのだろう。
あるいは行政からの規制で、墓地には手がつけられないのかもしれない。
3.11の直後から、日本人の秩序の良さが世界中に駆け巡った。ほとんどの日本人はそれを誇らしく思ったものだ。それは事実に反していたようだ。
大震災の後、被災地の周辺は極度のガソリン不足に陥った。3月の東北は寒さが厳しく、買い出しの足も車だ。だれもがガソリンスタンドで行列をなした。
 「被災地では、放置された車から、ガソリンが抜き取られる窃盗が横行していたんです。窓ガラスを破り、遺留品もことごとく盗られる。金品すら奪われる事件が起きていたんです。ボクの知人でも、何人もが被害に遭っています」
「被災地では、放置された車から、ガソリンが抜き取られる窃盗が横行していたんです。窓ガラスを破り、遺留品もことごとく盗られる。金品すら奪われる事件が起きていたんです。ボクの知人でも、何人もが被害に遭っています」
警察は被災者の救出、行方不明の捜索で、治安確保にたいして警察官を避けなかった。無法地帯になった。やがて、立ち入り禁止地域を設けた。
日本のメディアはそれら裏面、闇の部分を殆ど伝えなかったのだ。『秩序ある、崇高な民族』それをいまさら覆したくなかったのか。 もしそうだとすれば、報道機関の作為が、結果として日本人の狡さと汚さになってしまう。
この先、小説家たちが作中で、無法地帯の窃盗団を強調し、それが世界に流れれば、「日本は報道関係すら隠ぺい体質の民族なのか」とみなされるだろう。つまり、「伝えないのは隠しているのと同じ」、という認識が欠けているのだ。
日本のメディアはこれまでも被災者の遺体すら写真や映像で伝えてこなかった。日本人は誰もが、数万人の死者が出ても、一人として遺体を知らない。だから、被災の実感がすぐ薄れてしまうのだ。
少なくとも、日本では国内で起きた大被害なのに、ジャーナリストたちの奇妙な倫理規制で、被災地の真の状況を知ることができないのだ。
被災地の真実が写真で観られなくても、小説は読者を疑似体験させることができる。『文学はジャーナリストが伝えない真実を描くことができる』。私はそれを肝に銘じた。
閖上中学校のグランドには3隻の漁船が座礁船のように打ち上げられていた。建物の時計台は2時45分を指す。地震発生から約1時間後、大津波で時計は止まったのか。無人の校舎には、立ち入ることができた。夕暮れ前で、電気など一切なく、うす暗い。内心、不気味さが漂う。
津波が教室や通路に入り込んだ、その痕跡が各教室で確認できた。音楽室の楽器などは泥水で汚れている。一方で、1階通路の陳列ケースには、賞状とか、トロフィーが輝いていた。各教室の壁面には生徒たちの作品が並ぶ。黒板には『祝・卒業』と書かれ、バラの花が飾られている。3.11の教室がそっくりタイムスリップしていた。

図工室に入ると、3体の泥で汚れた石膏ボートが目についた。津波が突如として教室に海水が浸入した。「助けて」と悲鳴を上げて逃げ惑う生徒たち。それを見ていた顔はいまや泥でふさがれている。しかし、泥で目隠しされても、死にたくなかっただろう、中学生や教師たちの阿鼻地獄を知る像なのだ。
3階のテラスから周辺をみつめた。多くの命が奪われた広大な廃墟の町から、いまなお住民たちの「助けて」という絶叫が聞こえてくるようだ。
生きながらえた人は、この災害で人生がどのように狂ったのか。災害は人間の心や精神をどう変えさせたのか。私はすでに作品のテーマをそこに絞りこんでいる。
小説は想像力が重要だが、できるかぎり生の声を聞き、苦しみや痛みを知り、それを作中に反映させたい。この先の取材で、だれがどのように語ってくれるのか。被害者は作家に対して胸襟を開いてくれるのだろうか。ともかく、現地を歩くだけだ。【つづ゜く】
・
取材先の人物、企業、絞り込まれた地区名は、被災者のプライバシーの尊重、および取材源の守秘義務から仮名としています。(小説の人物名に近いところです)